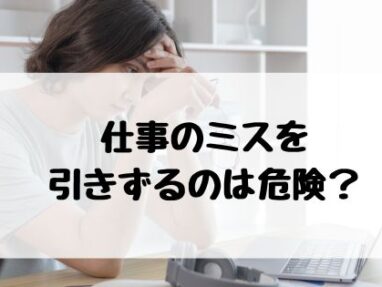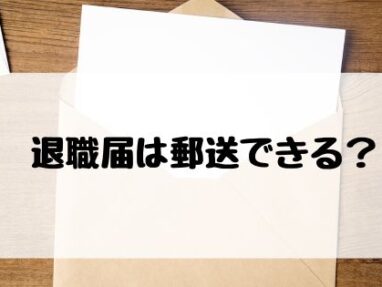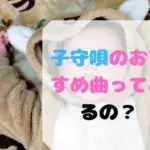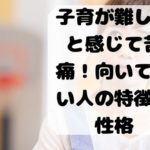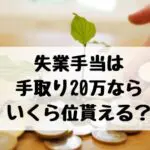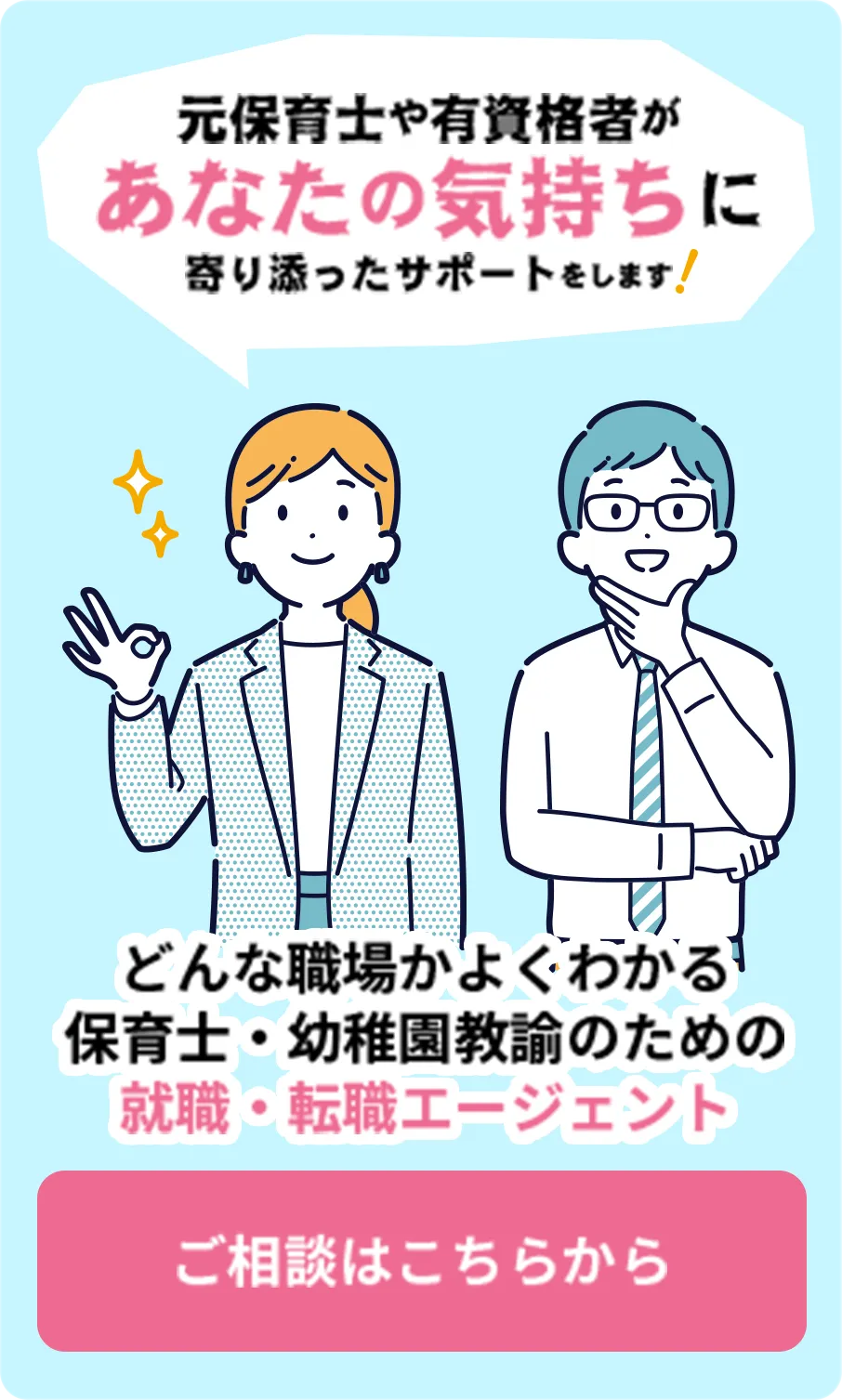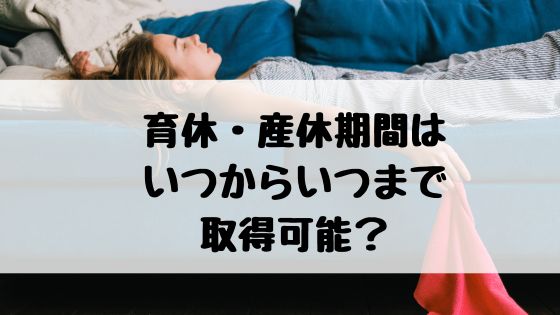
今の時代、女性がキャリアウーマンとして活躍することは珍しくなくなりました。
昔は、結婚すると男性は仕事を頑張り、女性は専業主婦になり家庭を守るものだという風潮がありましたが、最近では女性の社会進出が進んでおり、仕事と家事を上手く両立しながらワーク・ライフ・バランスを図る人も増えています。
女性は子どもを授かったら、出産や育児をする必要があるため会社に産休・育休を取得する人もいます。
出産や子育てのために会社を長期間休むことは、国が法律によって定めているのですが、なかには自分が抜けることで仕事が回らなくなるんじゃないか、あるいは迷惑がかかるのではと思う人もいるでしょう。
育休・産休についての理解を深めて、最適なタイミングで取得することが大切です。
今回は、育休・産休期間はいつからいつまで取得可能なのかや、それぞれの給料・条件や注意点などについて解説していきます。
Contents
育休期間とは?
育休は正確に言いますと「育児休業制度」のことで、家庭で子どもを育てる為に今の仕事を休業する制度です。
女性が子どもを授かった時は、最初に産休に入ってから育休を取る流れになります。
育休や産休と聞くと、女性だけに許された制度だと思う方も多いのではないでしょうか。
実は、育休は男性の方でも取得可能です。
ただし、男女とも育休を取得する際はある一定の条件を満たしている必要があるので、確認してから会社に伝えるようにしてください。
育児休業制度の育休期間は、産休が終了した次の日~育児のために子どもが1歳の誕生日を迎えるまでの間で、自由に希望日数を設定することができます。
お仕事に関連する記事はこちら⇒年間休日120日以上はホワイト企業?休みが多い業界や優良企業の判断基準
産休期間とは?
産休は「産前休業・産後休業」の2つの制度の種類があります。
産前休業とは、子どもを出産する前の段階で準備期間として会社を休業するものです。
産前休業の期間は、子どもを出産する予定日の42日前から取得が可能です。
そして、もう一つの産後休業とは赤ちゃんを産んでから、母親が体力を回復させるために会社を休業するものです。
産後休業の期間は、産前休業と違って8週間の休業を取ることが法律で義務付けられています。
産後休業を取得中に、もし働きたいと会社に願い出ても本人の意志とは関係が無く、仕事をその間は再開できない仕組みになっているので注意しましょう。
産休と言っても、子どもを出産前と後の制度があることは意外にも、あまり社会人に認知されていないのではないでしょうか。
子どもを授かって出産する段階で、初めて産休・育休について考える人も多いので無理もありません。
産休は子どもを産む全ての女性が取得できる制度となっています。
育休期間はいつからいつまで取得可能?
企業に勤めている従業員が、結婚や妊娠で寿退社するのはとてもおめでたいことです。
しかしながら、優秀すぎる社員だったら抜けた穴をカバーできるような人材がいないかもしれません。
企業側は結婚や妊娠で退職していく従業員のカバーを素早く行わないと、場合によっては生産性や業務効率の低下を招く恐れもあるでしょう。
退職する人材と比べたら、産休・育休でしばらく会社を休む従業員は、また復帰してバリバリ仕事を行ってくれるはずなので生産性や業務効率の低下は一時的な可能性があります。
ですので、産休・育休を取得する社会人の方は長期間、会社を休むことに対して申し訳ないとか、迷惑をかけてしまうことになると過剰に思う必要はありません。
育休期間は、男性と女性のどちらも取得可能とお伝えしましたが具体例が無いと、イマイチ理解しにくい人もいるのではないでしょうか。
女性の場合は、産休が終了した次の日~育児のために子どもが1歳の誕生日を迎えるまでの間、休業することができます。
つまり、例えば2023年3月1日に出産したら産休期間が終わった翌日の2023年4月27日~2024年2月28日まで育休を取得することが可能ということです。
男性の場合は、子どもを奥さんが出産した日から子どもが、1歳の誕生日を迎える前日まで申請した期間で休業可能です。
つまり、例えば2023年3月1日に子どもが産まれたら、2023年3月1日~2024年2月28日まで育休の取得ができます。
産休期間はいつからいつまで取得可能?
産休は産前休業・産後休業と2パターンあるとお伝えしてきましたが、産後休業だけしか知らない社会人もいてせっかく出産前にも会社を休むことができるのに、もったいないことをしているケースもあります。
産前休業の期間は、子どもが産まれる予定日の6週間前から会社に申請して取得できるようになっています。
産後休業の場合は、子どもを出産した次の日から8週間まで会社に申請して取得可能です。
具体的に言いますと、奥さんの出産予定日が2023年2月7日の場合は、例えば産前休業は2023年12月28日から、産後休業は2023年4月4日まで取得ができるということです。
ただし、あくまで出産予定日が決まっていてもその通りに子どもが産まれてくるとは限りません。
ですので、出産予定日がズレてしまい、会社側と本人の仕事の復帰時期を改めて、スケジューリングしなければいけなくなる可能性もあるでしょう。
体調不良になってしまったり、双子ができたりした場合も産休のタイミングを考えるのが難しくなるはずですので、そのような時は会社と相談しながら取得するようにした方が良いでしょう。
育休・産休期間中の給料事情について解説
育休・産休を取得することに対して理解が深まったはずですが、働けなくなる期間があるのでブランクが長いと給料面が心配になる人は多いのではないでしょうか。
休業している間は、会社の戦力になれないので他の従業員にしわ寄せが来てないのかや、迷惑になっていないのか不安に思う人もいるはずです。
それと同時に、仕事ができないことでその間の給料はどうなるのか不安になる人も多いのではないでしょうか。
育休・産休期間中の給料事情について解説していきます。
給料
基本的に、一般企業のビジネスパーソンは産休・育休中の給料を絶対に、支給しなければいけないという決まりはありません。
そのため、給料がでるのかは勤め先次第ということになります。
産休・育休の制度についてや、細かい内訳に関しては就職・転職の面接の時に聞くこともできるので、これから社会人生活を歩もうと思っている方は将来的に考えて気になる場合、産休・育休について働く前に聞いておくのは大切です。
公務員ですと、産休中は働いている期間だと認められて給料が支払われるでしょう。
一般企業で産休・育休中に給料が支給される場合は、日割り計算で出すところが多いと言われています。
賞与
そもそも、一般企業のビジネスパーソンに基本的に産休・育休中の給料を絶対に支給するという決まりが無いため賞与も同じです。
会社によって、給料を支給するところは賞与・ボーナスも出る可能性があります。
給料を貰うのは、労働者の権利として当たり前ですが、賞与・ボーナスに関しては会社の業績や経営状況なども関わっているので、産休・育休中に関わらず、支給しなければいけないわけではありません。
子どもの出産や育児を見越して、ある程度の貯金をしていると産休や育休中にお金に困らないようにできるかもしれないので、貯蓄計画を立てておくのも良いでしょう。
育休・産休の取得条件はある?
社会人で子どもの出産や育児に関係する場合にありがたい制度の育休・産休ですが、正社員しか取得できないと思い込んでいる人もいるのではないでしょうか。
正社員は会社の福利厚生サービスが、他の雇用形態と比べて優遇されていますが、育休制度に関してはアルバイト、派遣社員、パート社員、契約社員でも取得可能です。
育休の取得条件は、特に無く入社して1年経過していなくても原則的には取得することができるでしょう。
子どもが1歳6ヵ月に達する日までに、契約期間の満了や、継続した契約がされることを前提としています。
労使協定で「入社して1年未満・週の所定労働日数が2日以下・雇用継続が1年以内で終わる」などの時は、対象外とされる場合もあるため、その場合は取得ができないので注意してください。
産休の場合は、男女雇用機会均等法によって経営者は従業員の妊娠・出産を理由に解雇はできないようになっています。
産休を取得する条件に特別何かがあるわけでも無なく、正社員以外の雇用形態でも取得することができます。
育休・産休を取得する際の注意点
育休・産休を取得する際の注意点を解説していきます。
申請しないと国や自治体などのサポートが受けれない場合も
育休や産休を取得するならば、勤め先に黙ってても良いと思っていると、後で大変なことになるかもしれないので注意が必要です。
きちんと申請しないと、国や自治体、会社から色々なサポートが受けられなくなってしまうので忘れずに申請することが大切です。
子どもを妊娠したら、早めに会社に相談して今後の予定を話し合っておきましょう。
会社は従業員に給料を支払う義務は無し
お伝えしたように、産休・育休中は会社が給料を支払う義務はありませんから、あまり当てにしないようにした方が良いでしょう。
勤め先によっては、給料を支給するところもあるかもしれませんが、いつも通りに月給が満額支給ではない可能性もあります。
産休・育休中に従業員に給料が支給されるのかは、会社によりけりなので気になる人は勤め先にあらかじめ聞いておくと、慌てずに対処できるかもしれません。
産休は女性だけ、育休は女性・男性の両方
産休・育休に関して、なんとなく知っているけれど取得する機会がなかなか無いからか、勘違いしている社会人の方もいます。
産休と育休は女性だけしか取得できないと思い込んでいる人は意外と多いようです。
産休は子どもを産むことに関して取得するので、男性には無関係ですが育休は男性、女性の両方が取得できます。
早産や出産予定日が遅くても産休は取得できる
子どもを授かっても、誰にも明確に出産する日にちを当てることはできません。
そのため、この日程期間に子どもが産まれるだろうという出産予定日を決めます。
あくまで予定なので、出産予定日よりも早産になったり逆に遅くなったりする可能性もあるでしょう。
出産予定日よりも遅く産まれた際は、予定日から子どもを産んだ日までの日数も産前休業に含むことが可能です。
早産の場合は、子どもを産んだ日の翌日から産後休業を取得することができます。
育休・産休と合わせて有給休暇を取るのもあり
会社によっては、従業員が育休・産休中に給料の支給が無いところも多いので、最悪の場合は無給で過ごさなければいけなくなるかもしれません。
そうならないためにも、国や自治体からサポート支援や手当などを受けられるように申請することが大切です。
そして、育休・産休と合わせて有給休暇を取ることも考えましょう。
有給休暇を使うと、会社に迷惑がかかるので普段は使いづらいと悩んでしまう人もいますが、こういう時こそ思いきって取得することが大切です。
有給休暇は人によって、取得日数や支給額などが変わってくるのでどの位貰えるのかを、事前に把握しておくことをおすすめします。
社会保険料が免除される場合も
勤め先の企業が年金事務所、健康保険組合に申し出をしていると社会保険料が免除となる場合があります。
産休・育休中の社会保険料とは厚生年金・健康保険で、基本的に休業する月から休業が終わる前月までが免除対象の期間です。
社会保険料の免除期間でも被保険者として扱われるので、保険料を支払っているとみなされます。
育休中に2人目ができたら産休・育休は取得できる
1人目の子どもを産んで育休中に、2人目を授かる人もいるでしょう。
育休中に2人目を妊娠しても、産休・育休を申請すれば基本的には取得することができますが、どのくらいの休暇になりそうなのかは会社と話し合って決めることが大切です。
子ども授かるということはおめでたいですから、会社に対して後ろめたい気持ちになる必要はありません。
まとめ
社会人の子育てをサポートするために、企業では育休・産休制度が使えるようにしています。
産休は女性だけの特権ですが、育休は男性と女性のどちらも申請すれば取得可能です。
産休・育休中の給料は、公務員の職業の方には必ず支給となっていますが、一般企業のビジネスパーソンは会社によって支給の有無は違いがあるので注意しましょう。
この記事の監修は

保育のせかい 代表 森 大輔
2017年 保育のせかい 創業。保育士資格・訪問介護員資格を保有。2021年 幼保連携型認定こども園を開園するとともに、運営法人として、社会福祉法人の理事長に就任。
その他 学校法人の理事・株式会社の取締役を兼任中。
「役に立った!」と思ったらいいね!してね(^-^)
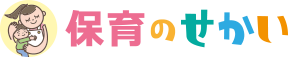

 2023.07.18
2023.07.18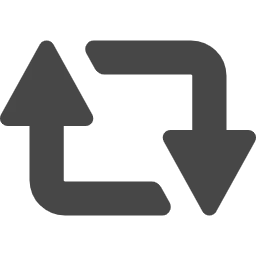 2024.07.28
2024.07.28