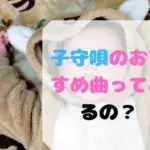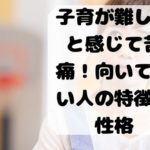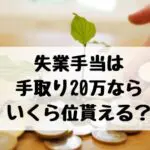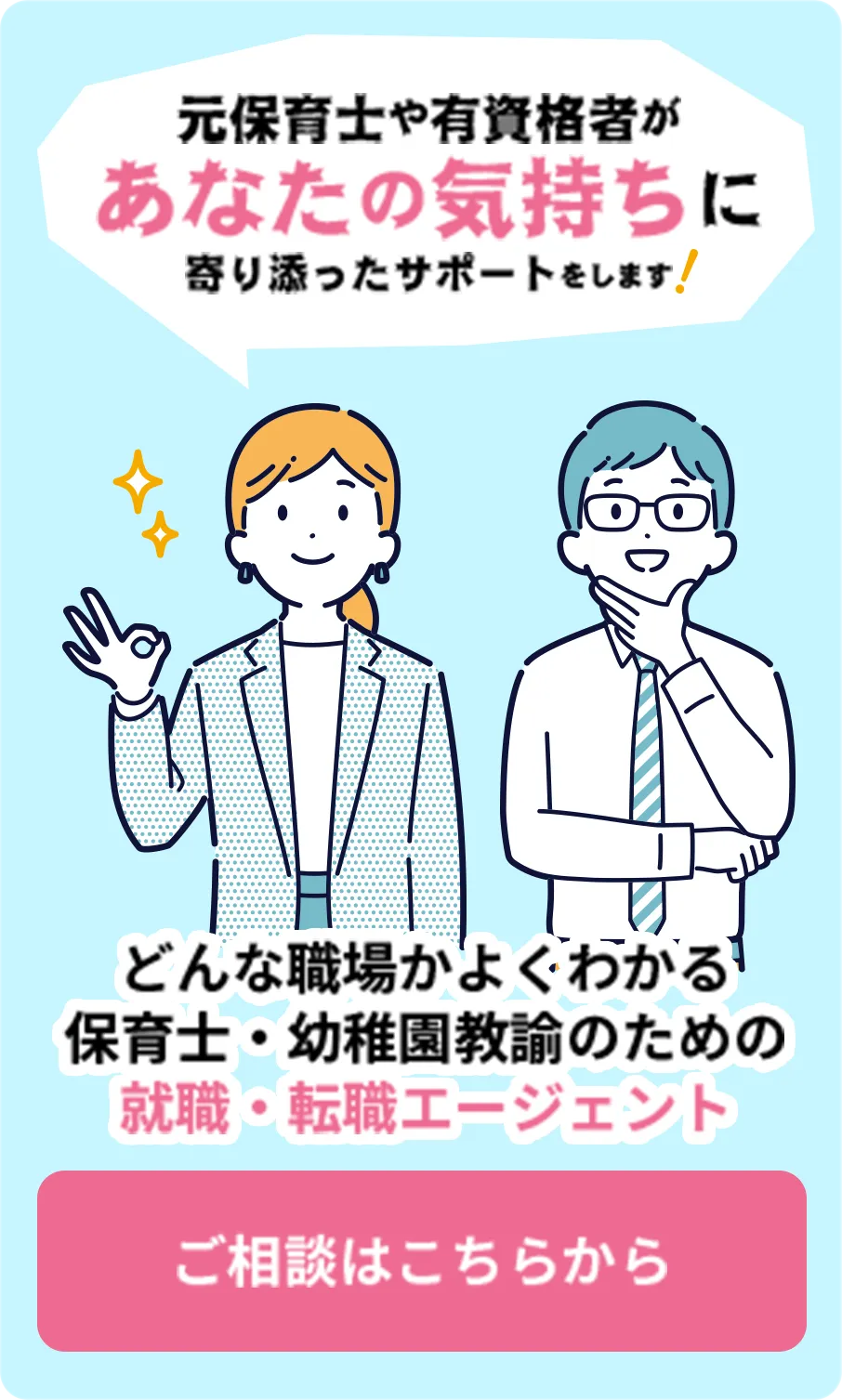転職活動で履歴書を準備する中で、保育士資格の正式名称や認定機関の書き方に迷っていませんか?
普段は意識しない項目だからこそ、いざというときに自信が持てず、不安に感じてしまうものです。
本記事では、保育士資格の正式名称や、複数の組織が関わる認定機関の仕組みを整理します。
ぜひ参考にして、自信を持って転職活動の第一歩を踏み出してください。
Contents
保育士資格の正式名称や認定機関について
履歴書を書く際に迷いやすい、保育士資格の正式名称や認定機関。
実は、制度を管轄する組織と試験を行う組織、登録を認定する組織はそれぞれ異なります。
ここでは、資格制度の仕組みに関わる以下7つを解説します。
- 正式名称は保育士資格である
- こども家庭庁が資格制度を管轄する
- 全国保育士養成協議会が試験を実施する
- 都道府県知事が保育士登録を認定する
- 登録事務処理センターが事務手続きを担当する
- 保母資格から保育士資格へ変更された
- 保育士資格と幼稚園教諭免許の管轄省庁が異なる
それぞれ見ていきましょう。
正式名称は保育士資格である
履歴書などの書面に取得資格を記入する際は、「保育士資格」と記載するのが正しい書き方になります。
「保育士資格登録」や「保育士資格取得」といった表現は、資格の正式名称ではなく、手続きや状況を表す言葉です。
余計な情報を加えてしまうと、かえって正式名称を理解していないという印象を与えかねません。
資格名は、保育士証に記載されているとおりに正しく記入することが肝心です。
転職活動の第一歩として、まずは正確な名称を覚えておきましょう。
こども家庭庁が資格制度を管轄する
保育士資格の制度全体を管轄しているのは、こども家庭庁です。
これは、2023年4月に新しく設置された行政機関になります。
それ以前は厚生労働省が管轄していましたが、現在は保育行政と共に移管されました。
こども家庭庁は、保育士の資質向上や制度の基準作りなど、いわば保育士資格のルールを定める役割を担っています。
履歴書に記載する認定機関名ではありませんが、保育士という専門職の根幹を支える重要な組織です。
国の保育政策を担う機関として覚えておくとよいでしょう。
参考資料:厚生労働省「こども家庭庁について」
全国保育士養成協議会が試験を実施する
年に2回実施される保育士試験の運営は、全国保育士養成協議会が指定機関として行っています。
厚生労働大臣から指定を受けた試験運営機関として、試験問題の作成や採点、合格者の決定などを担います。
ただし、あくまで役割は試験の実施であり、保育士資格そのものを認定する機関ではありません。
養成施設を卒業した人には直接関係ありませんが、保育士試験を経て資格を取得した人は、運営団体として知っておくと知識が深まります。
都道府県知事が保育士登録を認定する
保育士資格の認定機関、すなわち保育士登録を行う権限を持つのは、各都道府県知事です。
指定保育士養成施設を卒業した方は、申請書提出時点の住民票住所地がある都道府県に登録します。
一方、保育士試験に合格した方は、保育士試験の合格地である都道府県に登録することになります。
その申請を法的に認めて保育士として登録するのが、知事の役割です。
そのため、履歴書の資格欄に発行元や認定機関を記載する場合、保育士証を発行した都道府県知事の名前を書くのが正解となります。
登録事務処理センターが事務手続きを担当する
実際の申請書類の受付や保育士証の発行といった事務手続きは「保育士登録事務処理センター」が一括して担当しています。
センターは、社会福祉法人 日本保育協会によって運営されています。
全国の保育士登録に関する手続きを一本化し、効率的に処理する役割です。
申請者は、このセンターに書類を郵送して手続きを進めます。
いわば、都道府県知事の事務代行を担う「全国統一窓口」と考えると分かりやすいでしょう。
保母資格から保育士資格へ変更された
保育士資格は、かつて「保母資格」という名称でした。
しかし、1999年4月1日に資格の名称が男女共用である「保育士資格」に変更。
2003年11月29日の児童福祉法改正により、国家資格として法的に位置づけられました。
現在でも法改正以前に取得した保母資格自体は有効です。
ただし、保育士として業務に就くには保育士登録手続きを行い、保育士証の交付を受ける必要があります。
履歴書に記載する際は、保育士として働く意志を示すためにも「保育士資格」と書くのが一般的です。
保母資格から保育士資格への切り替え手続きは「保育士登録事務処理センター」を通して行えます。
保育士資格と幼稚園教諭免許の管轄省庁が異なる
保育士資格と幼稚園教諭免許は、どちらも子どもと関わる専門職ですが、成り立ちや管轄省庁が異なります。
保育士資格が、こども家庭庁の管轄する「福祉」の資格であるのに対し、幼稚園教諭免許は、文部科学省が管轄する「教育」の免許です。
この違いから、働く施設や対象となる子どもの年齢、求められる役割にも差が生まれます。
両方の資格を持つことで、保育と教育の両面から子どもを支援できる人材として、キャリアの幅を大きく広げられるでしょう。
履歴書への保育士資格の正しい書き方
ここでは、転職活動でつまずかないための、履歴書への正しい書き方8つを紹介します。
- 保育士証に記されている「取得年月日」を記載する
- 指定保育士養成施設卒業者は学校名を記載する
- 保育士試験合格者は都道府県知事名を記載する
- 新卒者は取得見込みと記載する
- 保育士免許ではなく保育士資格と記載する
- 複数資格は個別に記載する
- 幼稚園教諭免許状より保育士資格を先に記載する
- キャリアアップ研修修了証はその他欄または職務経歴書に記載する
詳しく見ていきましょう。
保育士証に記されている「取得年月日」を記載する
履歴書に書く日付は、保育士証に記載されている「取得年月日」です。
養成施設の卒業日は、保育士試験の合格日ではないため注意しましょう。
指定保育士養成施設を卒業して資格を取得した場合、卒業年月日が資格の取得年月日となります。
一方、保育士試験に合格して資格を取得した場合、合格日が取得年月日となります。
これらの日付は、保育士登録を行うための資格を得た日です。
保育士として法的に業務に就くことが認められるのは、都道府県知事に登録申請を行い、保育士証が交付された日です。
指定保育士養成施設卒業者は学校名を記載する
指定保育士養成施設、つまり大学や短期大学、専門学校を卒業して資格を得た場合、履歴書にはその学校名を記載します。
これは、資格取得の根拠がその学校の卒業にあることを示すためです。
たとえば「令和〇年3月〇〇短期大学保育科卒業」のように書きます。
この場合、認定機関名として都道府県知事の名前を書く必要はありません。
学校を卒業した事実そのものが、資格の証明となります。
保育士試験合格者は都道府県知事名を記載する
保育士試験に合格して資格を取得した場合、履歴書には保育士登録を行った都道府県知事名を記載します。
保育士証の「登録先」または「交付者」の欄に記載されている正式な名称を書きましょう。
たとえば「令和〇年〇月〇日保育士資格登録(東京都知事)」のように記載します。
これは、保育士資格を法的に認定したのがその都道府県知事であることを示すためです。
試験の実施団体である、全国保育士養成協議会の名前を書かないように注意してください。
新卒者は取得見込みと記載する
卒業を控えた学生など、まだ保育士証が手元にない場合は「取得見込み」と記載します。
たとえば「令和〇年3月保育士資格取得見込み」のように、取得予定の年月と合わせて書きましょう。
資格取得が卒業と同時であれば、学校名と卒業見込みの年月を記載しても構いません。
資格があることを前提に採用選考が進むため、確実に取得できる見込みがある場合にのみ記載することが大切です。
内定後に資格が取れないと、内定取り消しになる可能性もあります。
保育士免許ではなく保育士資格と記載する
保育士の資格は、一般的に「免許」ではなく「資格」と呼びます。
履歴書にも「保育士免許」ではなく「保育士資格」と正しく記載しましょう。
なお、保育士資格には更新制度がありません。
一度取得すれば、生涯有効な資格となります。
こうした言葉の正確な使い分けができると、採用担当者に知識があるという印象を与えられます。
複数の資格は個別に記載する
保育士資格のほかに幼稚園教諭免許状など、複数の資格を持っている場合は、まとめて書かずに一行ずつ個別に記載するのが有用です。
たとえば「保育士資格・幼稚園教諭免許状取得」と一行で書くのは避けましょう。
それぞれの資格には、異なる取得年月日や認定機関が存在するためです。
一行ずつ丁寧に書くことで、あなたの持つスキルや経歴を正確に、分かりやすく伝えられます。
採用担当者にとっても見やすく、丁寧な仕事ができる人材であるという印象にもつながるでしょう。
幼稚園教諭免許状より保育士資格を先に記載する
保育園や児童福祉施設など、保育士としての就職を希望する場合は、保育士資格を先に記載するのが肝心です。
複数の資格を持っている場合、応募する職種にもっとも関連性の高いものから書くのが履歴書の基本です。
これにより、採用担当者はあなたがその職場で働く意欲が高いことを一目で理解できます。
たとえば、幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方を持っていても、保育園の求人では保育士資格を上に書くことで、目に留まりやすくなるでしょう。
キャリアアップ研修修了証はその他欄または職務経歴書に記載する
保育士キャリアアップ研修などで得た修了証は、専門性を示すうえで有効ですが、国家資格である保育士資格とは区別して記載するのが望ましいです。
履歴書の「資格・免許」欄には保育士資格などを書き、研修の修了実績は「特技・自己PR」欄や、職務経歴書で具体的にアピールしましょう。
たとえば「乳児保育の専門研修を修了し、0歳児の豊かな発達を促す知識を深めました」のように記述できます。
そうすることで、資格欄がすっきりと見やすくなり、強みをより効果的に伝えられます。
保育士資格を生かせる職場は保育園以外にも!キャリアの選択肢
保育士資格は保育園だけでなく、以下のさまざまな場所で求められる価値あるスキルです。
- 児童養護施設や乳児院
- 企業内保育所や院内保育所
- 学童保育や放課後等デイサービス
- ベビーシッターやフリーランス
それぞれ見ていきましょう。
児童養護施設や乳児院
さまざまな事情で家族と離れて暮らす子どもたちを支えるのが、児童養護施設や乳児院です。
保育士は子どもたちの生活全般に深く関わり、安心できる環境を整える役割を担います。
食事や入浴、学習のサポートはもちろん、心のケアも大切な仕事です。
保育園とは異なり、子どもたちの「生活の場」であるため、より一人ひとりの人生に寄り添った長期的な支援が求められます。
企業内保育所や院内保育所
企業のオフィスや病院内に設置され、従業員の子どもを預かるのが企業内保育所や院内保育所です。
保護者の勤務形態に合わせた柔軟な保育が特徴で、一般的な保育園に比べて小規模な場合が多くあります。
土日祝日が休みであったり、残業が少なかったりするなど、運営母体の福利厚生が適用されることも魅力の1つです。
ワークライフバランスを重視しながら、保育の専門性を発揮したい人にとって働きやすい選択肢といえるでしょう。
学童保育や放課後等デイサービス
学童保育や放課後等デイサービスは、おもに小学生の子どもを対象とする施設です。
保育園とは異なり、子どもたちの放課後の時間を安全で豊かにすることが役割です。
仕事内容は、宿題のサポートや遊びの見守り、イベントの企画・運営など多岐にわたります。
より年齢の高い子どもたちと関わるため、対等な目線でのコミュニケーション能力や、自主性を尊重する姿勢が求められるでしょう。
とくに、障がいのある子どもを支援する放課後等デイサービスでは、療育に関する専門知識も生かせます。
ベビーシッターやフリーランスは
施設に所属せず、個人で保育サービスを提供する働き方です。
ベビーシッターとして派遣会社に登録したり、独立してフリーランスとして活動したりと形態はさまざまです。
最大の魅力は、自分のペースで働ける自由度の高さにあります。
勤務時間や時給、担当する子どもの年齢などを自分で決められるため、家庭との両立もしやすいでしょう。
保護者と密に連携を取りながら、一人ひとりの子どもの成長に合わせたオーダーメイドの保育を提供することに、大きな喜びを感じる人も多いです。
まとめ:保育士の認定機関は都道府県知事!正しい知識でキャリアアップを
正しい知識で応募書類の準備が整ったら、次はいよいよ理想の職場探しです。
「保育のせかい」は、現役の保育士や保育所の代表者が監修を行っており、保育業界のリアルな情報を反映した求人情報を提供しています。
アドバイザーの多くが保育士の有資格者であるため、現場を理解したうえでの的確なサポートを受けられるのも特徴です。
大阪の保育士求人なら「保育のせかい」へお任せください。
この記事の監修者

森 大輔(Mori Daisuke)
保育のせかい 代表
《資格》
保育士、幼稚園教諭、訪問介護員
《経歴》
2017年 保育のせかい 創業。2021年 幼保連携型認定こども園を開園するとともに、運営法人として、社会福祉法人の理事長に就任。その他 学校法人の理事・株式会社の取締役を兼任中。
「役に立った!」と思ったらいいね!してね(^-^)
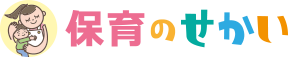

 2025.09.24
2025.09.24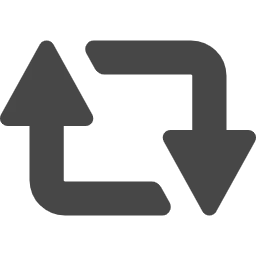 2025.11.12
2025.11.12