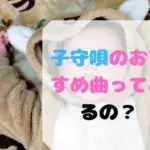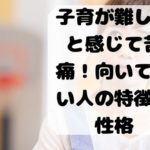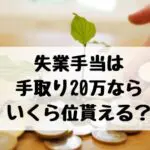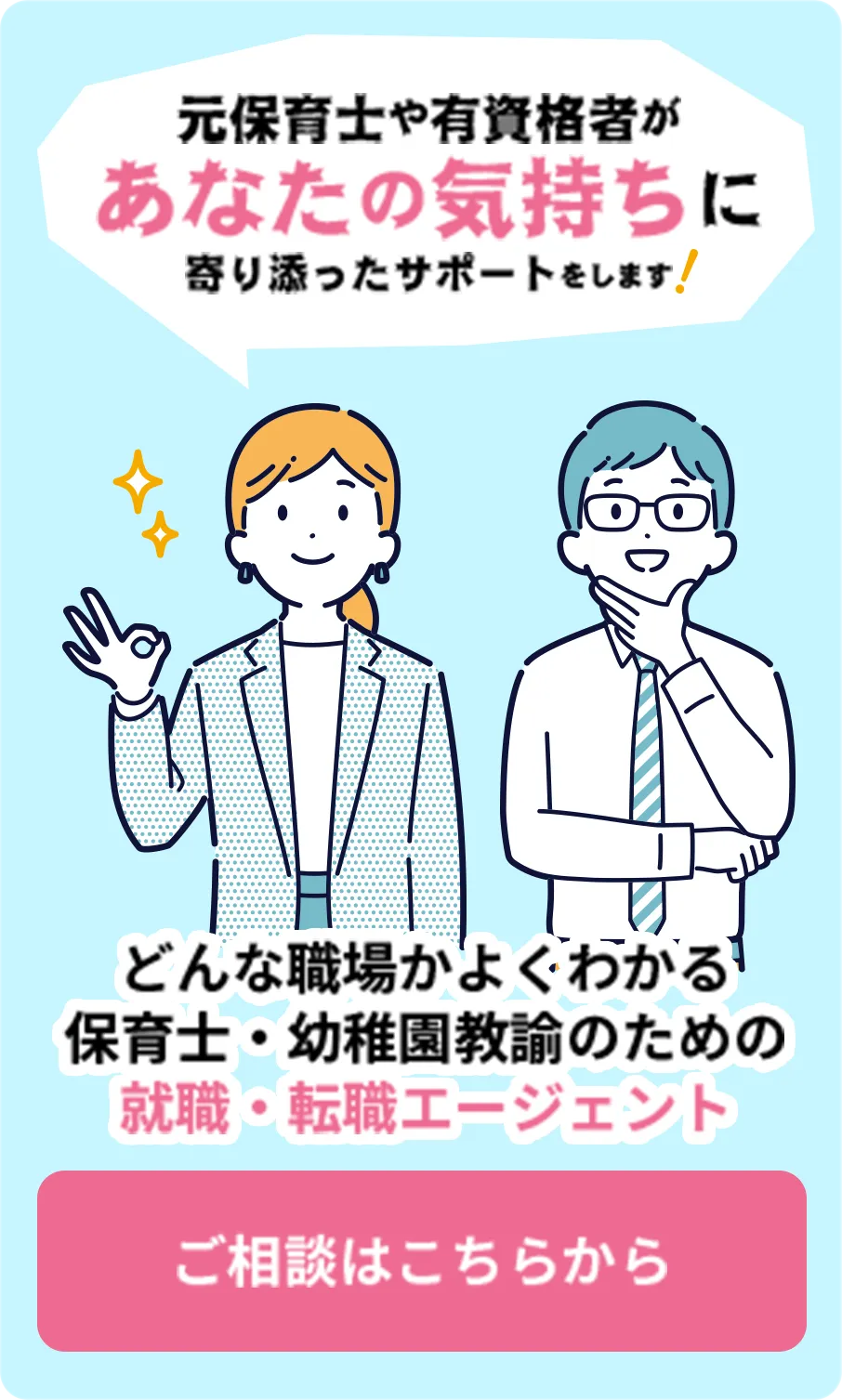保育士としてキャリアを続けたいけれど、子育てや介護など家庭の事情でフルタイム勤務が難しいと感じていませんか?
給料がどれくらい変わるのか、そもそも今の職場で時短勤務が認められるのか、さまざまな不安や疑問があるかもしれません。
本記事では、保育士の時短勤務に関する国の最新ルールから気になる給料の目安、今の職場で円満に希望を伝えるための方法を解説します。
ぜひ最後までお読みいただき、ご自身に合った働き方を見つけるためのヒントにしてください。
Contents
保育士の働き方の基本原則

保育士が働くうえでの基本的なルールは、国によって定められています。
以前は働き方に関する定義が曖昧な部分もありましたが、近年保育士の多様な働き方に対応するために見直しが進められました。
ここでは、以下3つのポイントを見ていきましょう。
- 国の原則は常勤保育士での配置
- 令和5年4月以降は常勤保育士の定義が明確化
- 常勤定義の変更による柔軟な働き方への対応
これらを理解することで、時短勤務の可能性や課題が見えてきます。
参考資料:厚生労働省「短時間保育士及び常勤保育士の取扱いについて」
国の原則は常勤保育士での配置
国の制度では、保育園の職員配置は「常勤の保育士」で行うことが基本原則です。
これは、子どもたちの心と体の健全な発達を支えるため、また保護者との連携を図るうえで、常勤保育士の存在が重視されているためです。
短時間勤務の保育士では、日々の細かな様子の共有や、一貫性のある関わりが難しくなる場合も。
そのため、保育の質を確保する観点から、まずは常勤保育士で必要な人数を確保することが望ましいと考えられています。
この原則は、働き方が多様化する現在でも維持されています。
令和5年4月以降は常勤保育士の定義が明確化
これまで曖昧だった「常勤保育士」の定義は、令和5年4月21日のこども家庭庁からの通知によって明確になりました。
この通知により、全国的な判断基準が示されています。
新しい定義では、以下のいずれかにあてはまる者が、常勤保育士とされます。
- 園の就業規則で常勤の勤務時間として月120時間以上と定められ、その時間数に達している者
- 1日6時間以上かつ月20日以上勤務する者
このどちらにも該当しない場合は、短時間勤務の保育士と位置づけられます。
参考資料:こども家庭庁「保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について(通知)」
常勤定義の変更による柔軟な働き方への対応
常勤保育士の定義が明確になったことで、これまでより柔軟な働き方が常勤として認められやすくなりました。
とくに「月120時間以上」という基準が設けられたことが大きなポイントです。
これにより、週の出勤日数が少なくても合計勤務時間が基準を満たす働き方が、園の就業規則次第で常勤として扱えるようになります。
この見直しは、子育て中の方などがライフスタイルに合わせて働き続けられるようにするためです。
多様な働き方を後押しし、保育士確保を円滑にすることを目的としています。
関連記事:保育士は休憩時間を取りづらい?理由と改善する方法を解説
保育士は時短勤務できない?

常勤での勤務が原則とはいえ、時短勤務が全くできないわけではありません。
保育士不足や待機児童問題といった社会的な課題に対応するため、国は特例的な措置を設けています。
ここでは、保育士の時短勤務を可能にする以下2つを説明します。
- 待機児童解消のための特例措置
- 特例措置の活用自治体と現状
それぞれ見ていきましょう。
待機児童解消のための特例措置
令和3年3月の厚生労働省通知により、待機児童解消のための暫定的な特例措置が設けられました。
この措置は、保育士不足により空き定員があるにもかかわらず、子どもを受け入れられない保育所を対象としています。
通常は常勤保育士の配置が原則ですが、この特例により短時間保育士の活用が認められるようになりました。
ただし、この措置はあくまで「暫定的」なものであり、常勤保育士の確保に向けた努力を続けることが前提となっています。
また、適用には市町村の判断が必要となるため、すべての保育所で利用できるわけではありません。
特例措置の活用自治体と現状
令和4年3月時点で、この特例措置を活用している自治体は4つ(秋田県大館市、茨城県つくばみらい市、埼玉県草加市、兵庫県加古川市)にとどまっています。
各自治体での活用施設数も1~4施設程度と限定的です。
この背景には、特例措置の条件が厳しいことがあります。
とはいえ、保育士確保を円滑に行う観点から、この制度は多様な働き方に対応し、保育士の確保に貢献することが期待されています。
保育士として時短勤務を希望する場合は、勤務地の自治体がこの特例措置をどのように扱っているかを確認することが大切です。
保育士が時短勤務で働く場合の給料は?

時短勤務になると、給料は基本的に勤務時間に応じて減少します。
給与は「基本給×(時短勤務の時間÷もともとの常勤の勤務時間)」で計算されるのが一般的です。
ボーナスについても同様に、算定基準が変わり減額されることがほとんどです。
また、職員の給与の元になる国の補助金(処遇改善等加算)は、常勤職員の人数が影響します。
なお、処遇改善等加算の算定では、1日6時間以上かつ月20日以上勤務している場合は常勤職員として扱われます。
この基準を満たせば、その職員は処遇改善等加算の算定において常勤職員とみなされ、その経験年数が加算額の算定に影響を与えることに。
満たさない場合は園の収入に影響が出る可能性もあるため、勤務時間を決める際は考慮しましょう。
保育士が希望の働き方を実現するために

時短勤務という希望を実現するには、制度の知識だけでなく、周囲の理解を得ながら円滑に話を進める工夫が欠かせません。
ただ自分の希望を伝えるだけでは、うまくいかないこともあります。
ここでは、希望の働き方を叶えるための行動を5つ紹介します。
- 家族の理解と協力を得る
- 周りの保育士たちに事前に説明する
- 園に希望を円満に伝える
- 限られた時間で成果を出す
- 時短勤務を拒否されたときに交渉する
それぞれ見ていきましょう。
家族の理解と協力を得る
時短勤務を始める前に、まず家族と話し合うことが大切です。
収入が減ることで家計にどのような影響があるか、具体的な数字を出して検討しましょう。
また、家事や育児の分担についても、具体的なスケジュールを作成して共有することが重要です。
たとえば、朝の準備は配偶者が担当し、夕方の迎えは時短勤務をする側が行うなど、役割分担を明確にします。
実家のサポートが得られる場合は、どの程度協力してもらえるかも確認しておきましょう。
家族全員が納得し、協力体制が整っていることで、職場でも自信を持って時短勤務を申請できるようになります。
周りの保育士たちに事前に説明する
時短勤務の申請前に、一緒に働く保育士たちに事情を説明しておくことで、理解と協力を得やすくなります。
とくに、同じクラスを担当する保育士には、自分が不在の時間帯の業務について相談しておきましょう。
「申し訳ない」という気持ちだけでなく、「自分ができることは精一杯やる」という前向きな姿勢を示すことが大切です。
たとえば、書類作成や行事準備など、できる業務は積極的に引き受ける姿勢を見せることで、同僚の理解を得やすくなります。
また、時短勤務になっても変わらず質の高い保育を提供することを約束し、実践することで信頼関係を維持できます。
園に希望を円満に伝える
園長や主任に時短勤務の希望を伝える際は、タイミングと伝え方が肝心です。
年度の切り替え時期や、職員配置を検討する時期の2〜3ヶ月前に相談を始めるのが理想的です。
面談では、時短勤務を希望する理由を具体的に説明し、いつからいつまでの期間を希望するかを明確にしましょう。
時短勤務でも担える業務内容や、ほかの職員への負担を最小限にする工夫についても提案します。
たとえば、「午前中は責任を持って担当し、午後はほかの先生と分担する」など、業務分担案を準備しておくことで、園側も検討しやすくなります。
限られた時間で成果を出す
時短勤務では、限られた時間内で効率的に業務をこなす必要があります。
まず、1日の業務をリスト化し、優先順位をつけて取り組みましょう。
保育の質を落とさないために、子どもと接する時間は最優先に確保します。
書類作成や環境整備などは、隙間時間を有効活用して進めます。
また、デジタルツールを活用して業務効率化を図ることも有用です。
たとえば、連絡帳のアプリ化や、行事準備のテンプレート化などで時間短縮が可能です。
さらに、ほかの職員との情報共有を密にし、引き継ぎノートを充実させることで、不在時もスムーズに保育が進むようにしましょう。
時短勤務を拒否されたときに交渉する
園から時短勤務を拒否された場合でも、すぐに諦める必要はありません。
まず、拒否の理由を具体的に聞き、解決策を一緒に考える姿勢を示しましょう。
職員不足が理由であれば、段階的な時短勤務の導入や、繁忙期を避けた期間限定の時短勤務を提案することもできます。
また、育児・介護休業法では3歳未満の子を養育する労働者の時短勤務が権利として認められていることを、冷静に伝えることも大切です。
それでも理解が得られない場合は、労働基準監督署や市町村の労働相談窓口に相談することも検討しましょう。
ただし、あくまで円満解決を目指し、対立的な態度は避けることが肝要です。
今の園で時短勤務が難しい場合

現在の職場で時短勤務の実現が困難な場合、転職という選択肢を検討することも必要かもしれません。
保育士不足の現状では、多様な働き方を認める園も増えてきています。
ここでは、以下3つのポイントを押さえて、自分に合った職場を見つけましょう。
- 本当に働きやすい園を見極める
- 多様な働き方に対応する園を選ぶ
- 転職エージェントを上手に活用する
転職は大きな決断ですが、適切な準備と情報収集で成功の可能性が高まります。
本当に働きやすい園を見極める
転職を考える際にもっとも重要なのは、求人票の条件面だけでなく「本当に働きやすい園か」を見極めることです。
そのためには、実際にその園で働く保育士の口コミを参考にしましょう。
インターネットの口コミサイトなどには、現場のリアルな声が書かれていることがあります。
可能であれば園見学を申し込み、職場の雰囲気や保育士たちの表情を自分の目で確かめるのがおすすめです。
職員同士が楽しそうに会話しているか、子どもたちへの接し方はどうかなど、求人票だけでは分からない情報から、働きやすさを判断しましょう。
多様な働き方に対応する園を選ぶ
時短勤務を希望するなら、そもそも多様な働き方に理解のある園を選ぶことが近道です。
園のホームページや求人情報で「育休・産休からの復帰実績多数」や「短時間正社員制度あり」といった記載があるかを確認しましょう。
面接の際には、実際に時短勤務で働いている職員が何人いるのか、どのような役割を担っているのかを具体的に質問してみるのもよい方法です。
前例が多ければ、働く際にもスムーズに話が進む可能性が高まります。
働き方の柔軟性は、園選びの重要な指標になります。
転職エージェントを上手に活用する
働きやすい園を自分1人で探すのは、時間も労力もかかり大変です。
そこで、保育士専門の転職エージェントを上手に活用するのがおすすめです。
転職エージェントは、一般には公開されていない「非公開求人」を多数持っていることがあります。
また、担当のキャリアアドバイザーが、希望に合った求人を紹介してくれます。
さらに、園の内部事情や職場の雰囲気といった、個人では得にくい情報を提供してくれるのも大きなメリットです。
面接の日程調整や条件交渉なども代行してくれるため、忙しい方にとって心強い味方になります。
まとめ:保育士として自分に合った時短勤務スタイルを見つけよう

保育士の時短勤務は、国の制度や園の方針で複雑に感じられるかもしれません。
しかし、正しい知識を持って行動すれば、希望の働き方を実現できる可能性があります。
今の職場で難しいと感じても、諦める必要はありません。
「保育のせかい」は、現役の保育士や園の経営者が監修する転職求人サイトです。
保育業界のリアルな情報を反映した求人から、「時短・扶養内」といったこだわりの条件で職場を探せます。
また、アドバイザーの多くが保育士の有資格者です。
あなたに合う働き方が見つかるよう、全力でサポートいたします。
大阪の保育士求人なら「保育のせかい」へお任せください。
この記事の監修者

森 大輔(Mori Daisuke)
保育のせかい 代表
《資格》
保育士、幼稚園教諭、訪問介護員
《経歴》
2017年 保育のせかい 創業。2021年 幼保連携型認定こども園を開園するとともに、運営法人として、社会福祉法人の理事長に就任。その他 学校法人の理事・株式会社の取締役を兼任中。
「役に立った!」と思ったらいいね!してね(^-^)
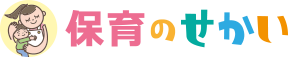

 2025.07.17
2025.07.17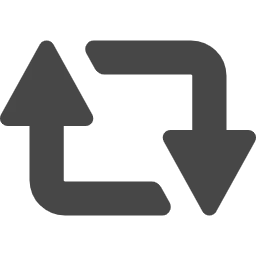 2025.09.09
2025.09.09