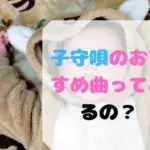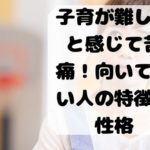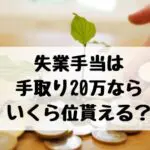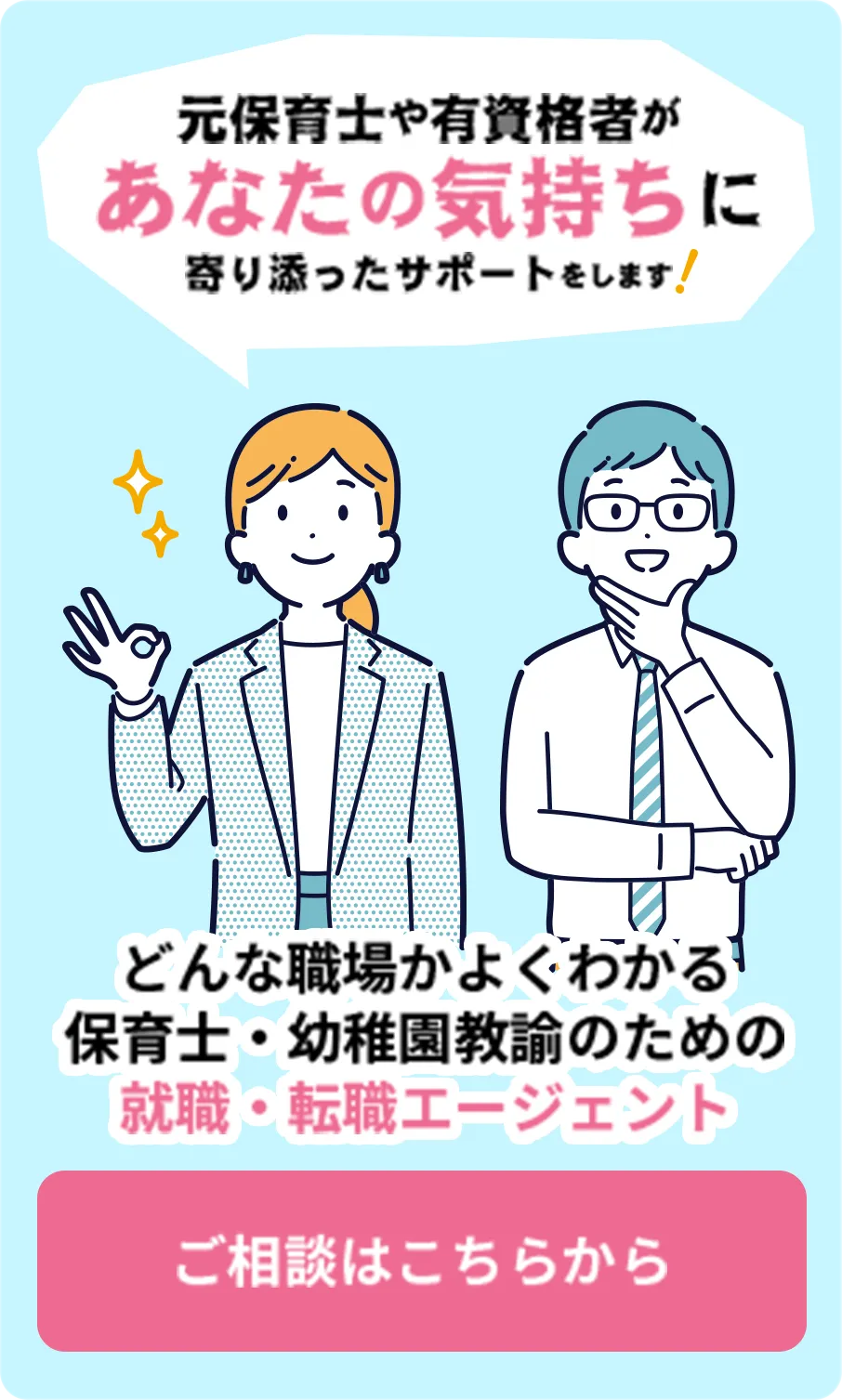保育士として働き始め、そろそろ一人暮らしを考えたいけれど、お給料で本当に生活できるのか不安に感じていませんか?
周りの友人たちが自立していく中で、焦りを感じることもあるかもしれません。
結論からいうと、いくつかのポイントを押さえれば保育士でも一人暮らしは十分に可能です。
本記事では、一人暮らしにかかる費用や実際に使える家賃補助制度、日々の生活で役立つ具体的な節約術を解説します。
ぜひ参考にして、経済的な不安を解消し、理想の一人暮らしへの一歩を踏み出してください。
Contents
ポイントを押さえれば保育士の一人暮らしは可能

保育士のお給料で一人暮らしをするのは、決して簡単なことではありません。
しかし、事前に必要なお金や生活費をきちんと把握し、計画を立てれば十分に実現可能です。
大切なのは、漠然とした不安を具体的な数字に置き換えてみることです。
ここでは、一人暮らしを始める前に知っておきたいお金の知識を2つのポイントに分けて解説します。
- 最初に必要となる初期費用の総額
- 毎月かかり続ける生活費の内訳
これらのお金に関する知識は、不安を解消するための大切な第一歩となります。
最初に必要となる初期費用の総額
一人暮らしを始めるには、まずまとまった初期費用が必要です。
一般的に、家賃の4ヶ月から6ヶ月分が目安とされています。
たとえば家賃6万円の部屋なら、24万円から36万円ほど準備しておくと安心でしょう。
おもな内訳は敷金や礼金、仲介手数料、前家賃などです。このほかに引っ越し費用や、生活に必要な家具や家電をそろえる費用もかかります。
金額が大きいため、計画的に貯金を始めることが、一人暮らしの夢を叶えるための鍵となります。
毎月かかり続ける生活費の内訳
一人暮らしでは、毎月一定の生活費がかかり続けます。
あらかじめ、どのようなことにお金が必要か内訳を把握しておくことが大切です。
おもな支出項目として、家賃や食費、水道光熱費、通信費などがあげられます。
そのほかにも、日用品の購入や友人との交際費、洋服代なども必要です。
これらの支出を合計して、毎月の手取り収入の範囲内に収まるように計画を立てなくてはなりません。
自分の収入でやりくりできるか、一度試算してみることをおすすめします。
国の政策で保育士の給料は着実に上がっている

保育士の給料は、ほかの職種に比べて低い水準にあることが課題とされてきました。
しかし近年、その状況は少しずつ変化しています。
国も保育士不足の解消に向けて、給与水準を引き上げるための政策を積極的に進めているからです。
ここでは、保育士の給料を後押しする国の動きについて、以下2つを説明します。
- 月額9,000円アップの処遇改善策とは
- 今後のさらなる賃上げへの期待
こうした国の後押しもあり、保育士がより安心して働ける未来への兆しが見えています。
月額9,000円アップの処遇改善策とは
2022年2月から実施された処遇改善策により、保育士の給料は月額9,000円(3%程度)引き上げられました。
この制度は「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の一環として実施され、全国の保育士が対象です。
処遇改善加算は基本給に上乗せされる形で支給され、賞与にも反映されるため、年収ベースでは10万円以上の増加につながります。
さらに、経験年数に応じた処遇改善等加算Ⅰや、キャリアアップに応じた処遇改善等加算Ⅱも併用できるため、実質的な収入アップはより大きくなります。
これらの制度を活用すれば、一人暮らしの経済的な不安も軽減されるでしょう。
今後のさらなる賃上げへの期待
政府は保育士の処遇改善を継続的に進める方針を示しており、今後も段階的な賃上げが期待されています。
2024年度には物価上昇に対応した賃上げも検討され、全産業平均との格差縮小を目指した取り組みが進んでいます。
保育士不足の解消に向けて、各自治体独自の支援も実施。
たとえば大阪市では、保育士の人材確保や離職防止のため、保育士の宿舎借り上げ費用を補助する制度が設けられています。
キャリアアップ研修の受講により、月額4万円の加算を受けられる制度も整備されました。
これらの政策により、保育士として働き続けることで、将来的により安定した生活が送れる見通しが立っています。
関連記事:保育士の給料はいつから上がる?処遇改善の最新情報と今後の見通しを解説
保育士の手取り額別一人暮らしでの生活費例

一人暮らしの計画を立てるうえで、自分の収入でどのような生活が送れるのか、具体的なイメージを持つことが重要です。
手取り額によって、家賃にかけられる金額や毎月の貯金額は大きく変わってきます。
ここでは、3つの手取り額を例に、一人暮らしの生活費シミュレーションを紹介します。
- 手取り15万円
- 手取り18万円
- 手取り20万円
自分の収入に近い例を参考に、無理のない家計プランを考えてみましょう。
手取り15万円
手取り15万円での一人暮らしは、徹底した節約が必要ですが、工夫次第で十分に可能です。
家賃は4万円以内に抑え、郊外や築年数の古い物件を選ぶことがポイントとなります。
| 費目 | 金額 | 節約のコツ |
| 家賃 | 4万円 | 郊外・築古物件を選択 |
| 食費 | 2万円 | 自炊と給食利用を徹底 |
| 水道光熱費 | 8,000円 | 節電・節水を心がける |
| 通信費 | 8,000円 | 格安SIM必須 |
| 日用品 | 5,000円 | 100円ショップ活用 |
| 交際費 | 1万円 | 無料イベント中心 |
| その他 | 9,000円 | 医療費など最低限 |
| 貯金 | 3万円 | 緊急時の備え |
| 残金 | 2万円 | 予備費として確保 |
最初は大変ですが、節約スキルが身につけば、将来の生活にも役立ちます。
手取り18万円
手取り18万円になると、生活に少しゆとりが生まれ、節約と楽しみのバランスが取れるようになります。
家賃も5〜6万円程度まで選択肢が広がり、駅から近い物件も視野に入ってきます。
| 費目 | 金額 | 使い方のポイント |
| 家賃 | 5万5,000円 | 駅近・セキュリティ重視 |
| 食費 | 2万5,000円 | 週1回の外食も可能 |
| 水道光熱費 | 1万円 | 快適な室温を維持 |
| 通信費 | 1万円 | 動画サービスも利用可 |
| 日用品・被服費 | 1万円 | 必要なものを購入 |
| 交際費・娯楽費 | 1万5,000円 | 友人との外出も楽しめる |
| その他 | 1万円 | 美容院など自己投資 |
| 貯金 | 3万円 | 将来への備え |
| 予備費 | 1万5,000円 | 急な出費に対応 |
月に1〜2回の外食や、友人との交流も無理なく楽しめます。また、趣味や自己投資にもお金を使えるため、仕事のストレス解消にもつながるでしょう。年間36万円の貯金ができれば、旅行や資格取得なども計画的に実現できます。
手取り20万円
手取り20万円あれば、都心部でも安定した一人暮らしが送れます。
家賃は6〜7万円まで選択肢が広がり、立地や設備面で妥協する必要がなくなります。
| 費目 | 金額 | 充実した生活のために |
| 家賃 | 6万5,000円 | 都心・築浅物件も可能 |
| 食費 | 3万円 | 食材の質にもこだわれる |
| 水道光熱費 | 1万2,000円 | 快適な生活環境 |
| 通信費 | 1万円 | 最新機種・高速回線 |
| 日用品・被服費 | 1万5,000円 | ブランド品も購入可 |
| 交際費・娯楽費 | 2万円 | 趣味を充実させられる |
| その他 | 1万3,000円 | 習い事や自己投資 |
| 貯金 | 3万5,000円 | 確実な資産形成 |
生活の質を保ちながら、毎月3万円以上の貯金も可能です。
年間42万円の貯金ができれば、将来の結婚資金や車の購入も現実的になります。
また、キャリアアップのための研修費用や、長期休暇での海外旅行なども計画できるため、充実した保育士ライフを送れるでしょう。
保育士の家賃負担を軽減させる制度の活用

保育士の一人暮らしを支援する制度は充実しており、これらを活用すれば家賃負担を大幅に軽減できます。
制度を知らずに諦めてしまうのはもったいないことです。
ここでは、以下2つの支援制度について説明します。
- 国の宿舎借り上げ支援事業
- 園が用意する住宅手当や社宅
これらの制度を上手に活用して、経済的な負担を減らしましょう。
宿舎借り上げ支援事業
大阪市では、保育士宿舎借り上げ支援事業として、保育士の人材確保や離職防止を目的とした宿舎借り上げ費用への補助を行っています。
1人あたり月額最大8万2,000円(補助対象経費と比較していずれか低い方の額)の補助が受けられる場合があります。
この制度は、保育士の人材確保と定着を目的として、多くの自治体で実施。対象となるのは、採用から5〜10年目までの常勤保育士で、自治体により条件は異なります。
補助を受けるには、保育所等を経営する者が保育士のために借り上げた宿舎に居住することが条件です。この制度を利用すれば、実質的な家賃負担は1〜2万円程度に抑えられ、手取り15万円でも十分な生活が可能になります。
園が用意する住宅手当や社宅
多くの保育園では、独自の住宅支援制度を設けています。
住宅手当は月額5000円〜3万円程度が一般的で、給与に上乗せして支給されます。
大手の社会福祉法人や株式会社が運営する保育園では、より充実した住宅手当を用意していることが多いです。
また、保育園が所有または借り上げた社宅を格安で提供するケースもあります。社宅の家賃は相場の半額以下に設定されることが多く、月額2〜3万円で入居できる場合も。
さらに、光熱費込みの寮を完備している園もあり、生活費を大幅に節約できます。
就職活動の際は、給与だけでなく住宅支援制度の有無も選択基準として確認しましょう。
保育士が一人暮らしを始める場合の流れ

一人暮らしをしたいと思っても、なにから手をつけてよいか分からず、なかなか一歩を踏み出せない人も多いかもしれません。
しかし、やるべきことを順番に整理すれば、スムーズに準備を進められます。
ここでは、一人暮らしを始める際の具体的な流れを4つ紹介します。
- 使える制度の確認と親への相談
- 物件探しと不動産屋への相談
- 家賃補助の申請と入居契約
- 引っ越しと各種手続き
それぞれ見ていきましょう。
使える制度の確認と親への相談
一人暮らしを始める前に、まず利用できる支援制度を確認しましょう。
勤務先の保育園に住宅手当や社宅制度があるか、自治体の宿舎借り上げ支援事業の対象になるかを人事担当者に確認します。
制度の詳細や申請条件、必要書類も同時に聞いておくとよいでしょう。
次に、親への相談も重要です。
初期費用の援助や連帯保証人をお願いする可能性もあるため、早めに話し合いましょう。
一人暮らしの理由や計画、毎月の収支見込みを具体的に説明すれば、理解を得やすくなります。
親の不安を解消するためにも、生活設計を示すことが大切です。
物件探しと不動産屋への相談
支援制度の確認が済んだら、具体的な物件探しを始めます。
宿舎借り上げ支援事業を利用する場合は、園が指定する不動産会社や物件から選ぶことになります。
自由に物件を選べる場合は、通勤時間30分以内、家賃は手取りの3分の1以下を目安に探しましょう。
不動産屋には保育士であることを伝え、収入証明書や在職証明書を準備します。
女性の一人暮らしの場合は2階以上、オートロック付きなど、セキュリティ面も重視することが大切です。
内見の際は日当たりや騒音、周辺環境もチェックしましょう。
複数の物件を比較検討し、生活をイメージしながら選ぶことが成功のポイントです。
家賃補助の申請と入居契約
物件が決まったら、家賃補助の申請手続きを進めます。
宿舎借り上げ支援事業の場合、園を通じて自治体に申請書類を提出します。
必要書類は住民票や所得証明書、雇用契約書などで、園の担当者がサポートしてくれることが多いです。
申請から承認まで2〜4週間程度かかるため、入居希望日から逆算して準備を進めます。
承認が下りたら、正式な入居契約を結びます。
契約時には印鑑、身分証明書、連帯保証人の書類が必要です。
初期費用の支払いも同時に行うため、事前に資金を準備しておきましょう。
契約内容は隅々まで確認し、不明な点は遠慮なく質問することが大切です。
引っ越しと各種手続き
入居契約が完了したら、引っ越しの準備を始めます。
引っ越し業者は複数社から見積もりを取り、料金とサービスを比較して選びましょう。
単身パックなら3〜5万円程度で済むことが多いです。
荷造りは計画的に進め、不要なものは処分して荷物を減らします。
引っ越し後は役所での転入届、電気・ガス・水道の開通手続き、インターネットの契約などが必要です。
郵便物の転送手続きも忘れずに行いましょう。
職場への住所変更届も速やかに提出します。
新生活に必要な家具や家電は、最初は最小限に抑え、徐々にそろえていくのが経済的です。
1つずつ確実に手続きを進めることで、新生活を気持ちよくスタートできます。
保育士の一人暮らしにおすすめの節約方法

保育士の給料でも、工夫次第で余裕のある生活が送れます。
日々の小さな節約の積み重ねが、月末の家計に大きな差を生み出します。
以下4つの節約方法を実践しましょう。
- 昼食は給食を利用する
- 週末にまとめて自炊する
- 固定費を全体的に見直す
- 節約がつらい場合は転職も考える
詳しく解説します。
昼食は給食を利用する
保育園の給食は、保育士にとって大きな節約ポイントです。
多くの保育園では、職員も200〜300円程度で給食を食べられます。
外食なら1食800円以上かかることを考えると、月20日勤務で1万円以上の節約になります。
給食は栄養バランスも考えられており、健康面でも魅力的です。
献立表を見ながら、夕食との重複を避ける工夫をすれば、食事の偏りも防げます。
給食の調理方法を参考にして、自炊のレパートリーを増やすことも可能です。
ただし、アレルギーがある場合は事前に栄養士に相談し、代替メニューの対応を確認しておきましょう。
この制度を活用すれば、食費を大幅に削減できます。
週末にまとめて自炊する
平日は保育の仕事で疲れているため、週末にまとめて料理を作り置きすることがおすすめです。
日曜日に2〜3時間かけて、5日分の主菜と副菜を準備しておけば、平日は温めるだけで済みます。
カレーやシチューなどの煮込み料理、ハンバーグなどは冷凍保存も可能です。
野菜は下茹でして小分け冷凍しておくと、調理時間を短縮できます。
1週間分の食材をまとめ買いすることで、単価も安くなり、月の食費を2万円程度に抑えられるでしょう。
また、同じメニューが続かないよう、味付けを変えるなどの工夫も大切です。
料理が苦手な人は、簡単なレシピ本やアプリを活用してみましょう。
固定費を全体的に見直す
毎月必ず支払う固定費の見直しは、大きな節約効果があります。
スマホは格安SIMに変更すれば、月額3000円程度に抑えられます。
電気・ガスも、新電力会社への切り替えで年間1万円以上安くなることも。
不要なサブスクリプションサービスは解約し、本当に必要なものだけを残します。
保険も、若いうちは最低限の保障で十分なことが多いです。
家賃以外の固定費を1万円削減できれば、年間12万円の節約に。
また、ポイントカードやキャッシュレス決済を活用すれば、日用品の購入でもポイント還元を受けられます。
これらの見直しは最初だけ手間がかかりますが、一度設定すれば継続的な節約効果が期待できます。
節約がつらい場合は転職も考える
節約を頑張っても生活が苦しい場合は、転職を視野に入れることも大切です。
令和7年1月の保育士の有効求人倍率は3.78倍と高く、より条件のよい職場を見つけやすい状況です。
都市部では人材不足から、初任給20万円以上や住宅手当3万円以上を提示する園も増えています。
公立保育園なら公務員として安定した収入が得られ、退職金制度も充実しています。企業内保育所や院内保育所は、一般的な保育園より給与水準が高い傾向にあります。
転職活動では給与だけでなく、住宅支援制度や福利厚生も含めて総合的に判断しましょう。
今の職場で経験を積みながら、よりよい条件の職場をさがすことで、生活の質を向上させられます。
まとめ:保育のせかいは一人暮らしに挑戦する保育士を応援しています
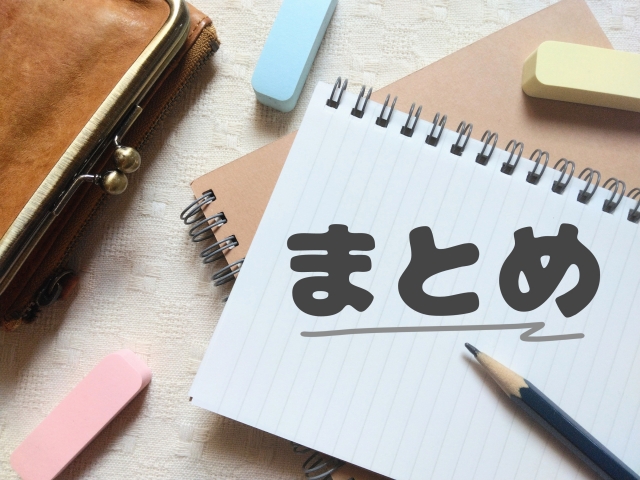
保育士の一人暮らしは、給料面での不安があっても、制度の活用と工夫次第で十分に実現可能です。
もし今の職場で一人暮らしが難しいと感じたら、よりよい条件の職場をさがすことも選択肢の1つです。
「保育のせかい」では、保育士の有資格者であるアドバイザーが、希望に合った職場探しをサポートします。
「求人を教えてもらう」から相談することも、「自分で求人をさがす」ことも可能です。
大阪の保育士求人なら「保育のせかい」へお任せください。
この記事の監修者

森 大輔(Mori Daisuke)
保育のせかい 代表
《資格》
保育士、幼稚園教諭、訪問介護員
《経歴》
2017年 保育のせかい 創業。2021年 幼保連携型認定こども園を開園するとともに、運営法人として、社会福祉法人の理事長に就任。その他 学校法人の理事・株式会社の取締役を兼任中。
「役に立った!」と思ったらいいね!してね(^-^)
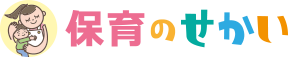

 2025.07.18
2025.07.18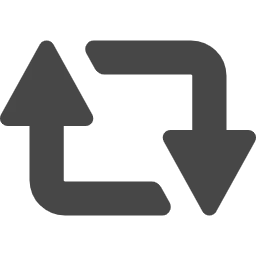 2025.09.09
2025.09.09