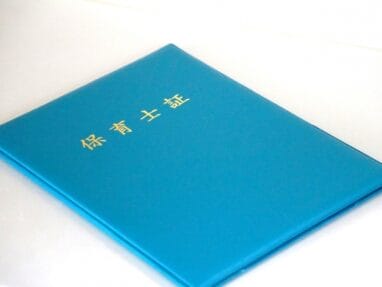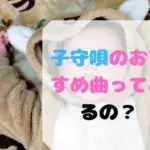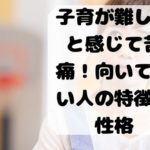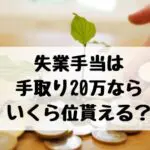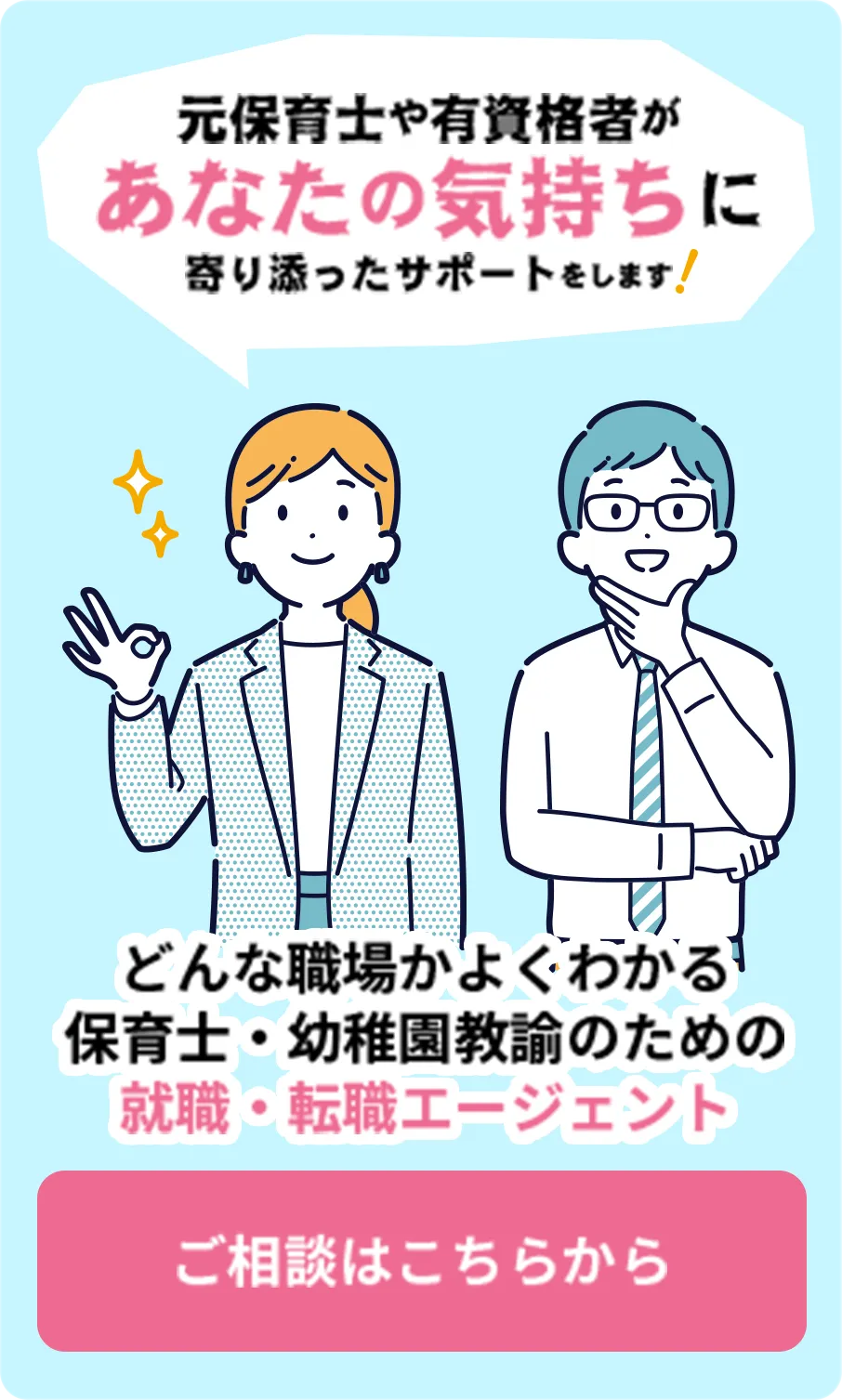保育園選びは、子どもと家族にとって大切なライフイベントの1つです。
しかし、園の種類や申し込み方法など、はじめての保活では不安や疑問が多くつきものです。
本記事では、保育園の種類や保育園を選ぶときのポイントを解説します。
家庭の優先順位に合った園を選ぶために、必要な基礎知識を身につけましょう。
Contents
保育園選びでよくある悩み

はじめて保活に取り組む家庭は、情報の多さや判断基準の曖昧さに悩まされがちです。
具体的には、下記の悩みがよくあげられます。
- どの保育園がよいのか判断基準が分からない
- 情報が多すぎて優先順位をつけられない
- 保活のスケジュールや手続きに不安がある
- 何からはじめればよいか分からず行動に移せない
- 家庭によって重視する点が違い、正解が見えにくい
悩んだときは、家庭ごとに「譲れない条件」や「理想の保育環境」を整理するのがおすすめです。
園の見学や情報収集を通じて、少しずつ判断を固めていきましょう。
保育園の種類

ここでは、保育園の種類ごとの特徴を解説します。
- 認可保育園
- 認可外保育園
- 企業主導型・小規模保育・幼保連携型こども園との違い
詳しく見ていきましょう。
認可保育園
認可保育園は、厚生労働省の定める設置基準をクリアし、各自治体から正式に認可された保育施設です。
定員や施設面積、職員数などが厳しく定められており、安全性・保育の質の面で一定の安心感があります。
保育料は世帯収入に応じて決まり、公的助成によって比較的低額で利用できる点が魅力です。
申し込みは自治体を通じて行われるのが基本で、選考には保護者の就労状況などが影響します。
希望の園がある場合は、早めに情報収集をはじめるのがポイントです。
認可外保育園
認可外保育園は、国の設置基準には該当しないものの、自治体に届け出て運営されている保育施設です。
保育時間や方針の自由度が高く、延長・夜間・休日保育に対応している園もあります。
運営は法人や個人事業者など多様で、保育内容や環境は園によって大きく異なります。
安全性に不安を持つ方もいるでしょう。
しかし、各自治体による立入検査や監督が行われているため、一定の運営水準は保たれているのが特徴です。
認可にこだわらず、柔軟な保育ニーズに対応したい家庭におすすめです。
企業主導型・小規模保育・幼保連携型こども園との違い
認可・認可外保育園に加えて、近年は家庭の多様なニーズに応える新しい保育施設が増えています。
企業主導型・小規模保育・幼保連携型の特徴を、下記にまとめましたので、参考にしてください。
| 種類 | 対象年齢 | 特徴 | 利用のしやすさ |
|---|---|---|---|
| 企業主導型保育園 | 0歳~就学前 | ・企業が設置主体 ・柔軟な保育時間 ・地域枠あり | 比較的入りやすい |
| 小規模保育園 | 0~2歳 | ・少人数制 ・家庭的な保育 ・地域密着型 | 定員が少なく倍率高め |
| 幼保連携型認定こども園 | 0歳~就学前 | ・教育と保育の一体運営 ・長時間保育にも対応 | 認可保育園と同様の選考が必要 |
参考:
企業主導型保育事業|制度紹介
こども家庭庁|小規模保育所における対象年齢拡大措置の全国展開について
こども家庭庁|認定こども園概要
小規模保育園は家庭的な雰囲気が魅力ですが、定員が少ないため、希望者が集中する地域では競争率が高くなりがちです。
企業主導型は地域住民も利用でき、保育時間の柔軟さから働き方との相性がよい場合もあります。
一方、幼保連携型こども園は、教育と保育の両立を重視したい家庭に適しています。
家庭の事情や子どもの年齢に応じて、それぞれの施設の特徴を理解しながら選択肢を広げましょう。
保育園を選ぶときの5つの重要ポイント

保育園を選ぶときは、下記5つのポイントを押さえましょう。
- 毎日通園しやすい立地か
- 保育時間が家庭の働き方に合っているか
- 園の雰囲気や先生の接し方が子どもに合っているか
- 給食や衛生管理が安心できる内容か
- 費用や保護者の負担が無理のない範囲か
詳しく解説します。
1.毎日通園しやすい立地か
通園のしやすさは、保育園選びで現実的かつ重要なポイントです。
自宅・職場から近い園を選ぶだけでなく、下記のポイントも考慮しましょう。
- 雨の日の通園手段
- 兄弟姉妹との送迎ルート
- 駅からの距離
通勤経路にある園なら、朝の慌ただしさも軽減されます。
保育園によっては、ベビーカーや自転車の預かりスペースがないことがあります。
事前の見学や問い合わせで確認しましょう。
2.保育時間が家庭の働き方に合っているか
保育時間や延長保育の有無は、共働き家庭にとって重要なポイントです。
標準的な開園時間は、認可園で7時半〜18時半前後です。
なお、園ごとに延長時間や土曜開園の有無が異なります。
また、同じ園でも年齢によって保育可能な時間帯が違うケースもあるため注意しましょう。
仕事が不規則な方や、時短勤務からフルタイムに切り替える予定がある方は、柔軟な時間設定の園を選ぶと安心です。
3.園の雰囲気や先生の接し方が子どもに合っているか
保育園は下記のように、それぞれ特色が異なります。
- のびのび系
- 勉強系
- 宗教色のある園
子どもが安心して通える雰囲気かどうかは、見学時に確認できる部分もあります。
また、保護者参加型の行事を多く取り入れている園もあるため、家庭の状況に合っているかも確認しておくと安心です。
4.給食や衛生管理が安心できる内容か
子どもが毎日口にする給食や園内の衛生管理体制は、保護者が安心して預けるために重要なポイントです。
とくに以下の項目は、事前にチェックしておきましょう。
- 手作り給食の有無
- 食物アレルギーへの対応状況
- 感染症対策(換気・消毒・手洗い指導など)
小規模園では調理室の有無が園によって異なり、自園調理のほかに外部委託・配食サービスを採用しているケースもあります。
また、布団・おむつ・エプロンなどを毎日持ち帰る必要があるかは、日々の負担に直結する要素です。
近年では、保護者の負担軽減を目的に、レンタルサービスの導入や園内での洗濯対応を行っている園も増えています。
5.費用や保護者の負担が無理のない範囲か
保育料だけでなく、保育園に通うにはさまざまな費用が発生します。
具体的な費用の項目は、下記のとおりです。
- 延長保育料
- 給食費
- 教材費
- 行事費
認可保育園では、世帯収入に応じて保育料が決定される仕組みで、3〜5歳児は基本的に無償化の対象です。
ただし、無償化の対象でも、実費負担が発生する場合も。
一方、認可外保育園は保育料が一律で設定されていることが多く、認可園より高額になる傾向があります。
手作りグッズの持参や頻繁な保護者会の参加など、金銭面以外の負担も見落とせません。
自分たちの生活スタイルや、経済状況に無理のない範囲で続けられる園を選びましょう。
保育園の見学でチェックすべきポイント

保育園の見学では、パンフレットや公式サイトでは伝わらない実際の雰囲気や、職員の対応などを自分の目で確かめられます。
とくに以下のポイントは、入園後の満足度にも大きく関わるため、重点的に確認しましょう。
- 園内の清潔感や安全対策
- 子どもたちの様子
- 保育士の接し方
- 給食やアレルギー対応の体制
- 外遊びの頻度や園庭・近隣環境の活用状況
延長保育や連絡手段、持ち帰り物の有無なども園によって差があります。
気になる点は事前に質問リストを作っておきましょう。
保活スケジュールと準備の流れ

保育園選びにおいて、いつから何をはじめればよいのか分からず、不安を感じる保護者は多いでしょう。
ここでは、下記の順番に沿って、保活の進め方を解説します。
- 保育園探しをはじめる時期
- 申し込み~内定通知の流れ
- 激戦区で希望の園に入るための対策
詳しく見ていきましょう。
保育園探しをはじめる時期
保活は、早ければ早いほど有利になる傾向があります。
4月入園を目指す場合は、前年の春〜初夏には情報収集をはじめるのが理想的です。
0歳児クラスの申し込みでは、妊娠中から動きはじめる家庭も珍しくありません。
まずは自治体の保育課で入園案内を入手し、自宅から通える園をピックアップしましょう。
地域によっては「点数制」での選考となるため、自分の世帯がどれくらいの点数になるのかを確認しておく必要もあります。
認可園と並行して、認証・認可外園も検討することで選択肢が広がります。
申し込み~内定通知の流れ
認可保育園の申し込みは、一般的に10月〜11月に行われ、結果通知は1月〜2月に届きます。
申請に必要な書類は多岐にわたるため、早めに準備をはじめておくと安心です。
下記のように、職場に提出依頼が必要なものもあるため注意しましょう。
- 就労証明
- 勤務予定証明
- 家庭状況の書類
なお保活において、希望する保育園の数に全国共通の上限はありません。
できるだけ多くの園を記入しておくことで、入園のチャンスが広がります。
ただし、自治体によって希望できる園の数や記入方法が異なるため、自治体の募集要項を確認しましょう。
すべての希望園で不承諾となるケースもあるため、認可外保育園も候補に含めておくと、柔軟に対応できます。
激戦区で希望の園に入るための対策
待機児童が多い激戦区では、希望の園に入園するための工夫が必要です。
まず、自分の「保活点数(調整指数)」を把握し、前年の内定ボーダーを確認して希望順位を戦略的に決めましょう。
見学を通じて「ここなら通わせてもよい」と思える園が複数あれば、希望欄は可能な限りすべて埋めるのがおすすめです。
また、自治体によっては加点対象となる条件もあります。
以下のような項目に当てはまる場合は、あらかじめ確認しておきましょう。
- 兄弟姉妹が同じ園に通っている(兄弟枠)
- 1人親世帯(1人親加点)
- 育児休業明けでの復職予定
さらに、認可外や企業主導型なども並行して申し込みを進めておけば、保育の選択肢と安心感が広がります。
まとめ:優先順位を整理して、子どもと家庭に合った保育園を見つけよう

保育園選びで迷ったときは「子どもが安心できる環境」と「家庭の生活リズムに合うこと」を軸に、優先順位を整理しましょう。
見学や情報収集を通して、数字や評判だけでなく相性も大切にすると、納得のいく選択ができます。
また、保育士・幼稚園教諭として、働く方のキャリア選びには「保育のせかい」をご利用ください。
現役の保育士や園の経営者が監修する求人情報をもとに、保育業界に特化した転職支援を行っています。
保育士資格を持つアドバイザーが親身に対応しますので、転職を考えている方は一度ご相談ください。
この記事の監修者

森 大輔(Mori Daisuke)
保育のせかい 代表
《資格》
保育士、幼稚園教諭、訪問介護員
《経歴》
2017年 保育のせかい 創業。2021年 幼保連携型認定こども園を開園するとともに、運営法人として、社会福祉法人の理事長に就任。その他 学校法人の理事・株式会社の取締役を兼任中。
「役に立った!」と思ったらいいね!してね(^-^)
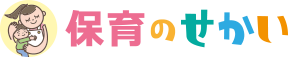

 2025.06.30
2025.06.30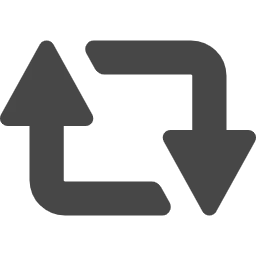 2025.07.02
2025.07.02