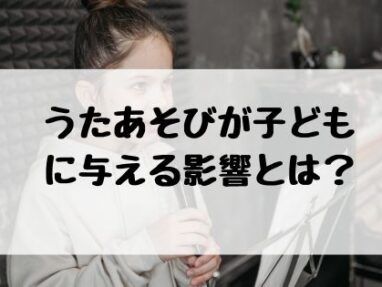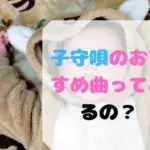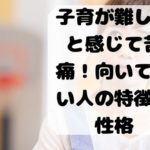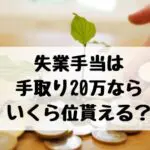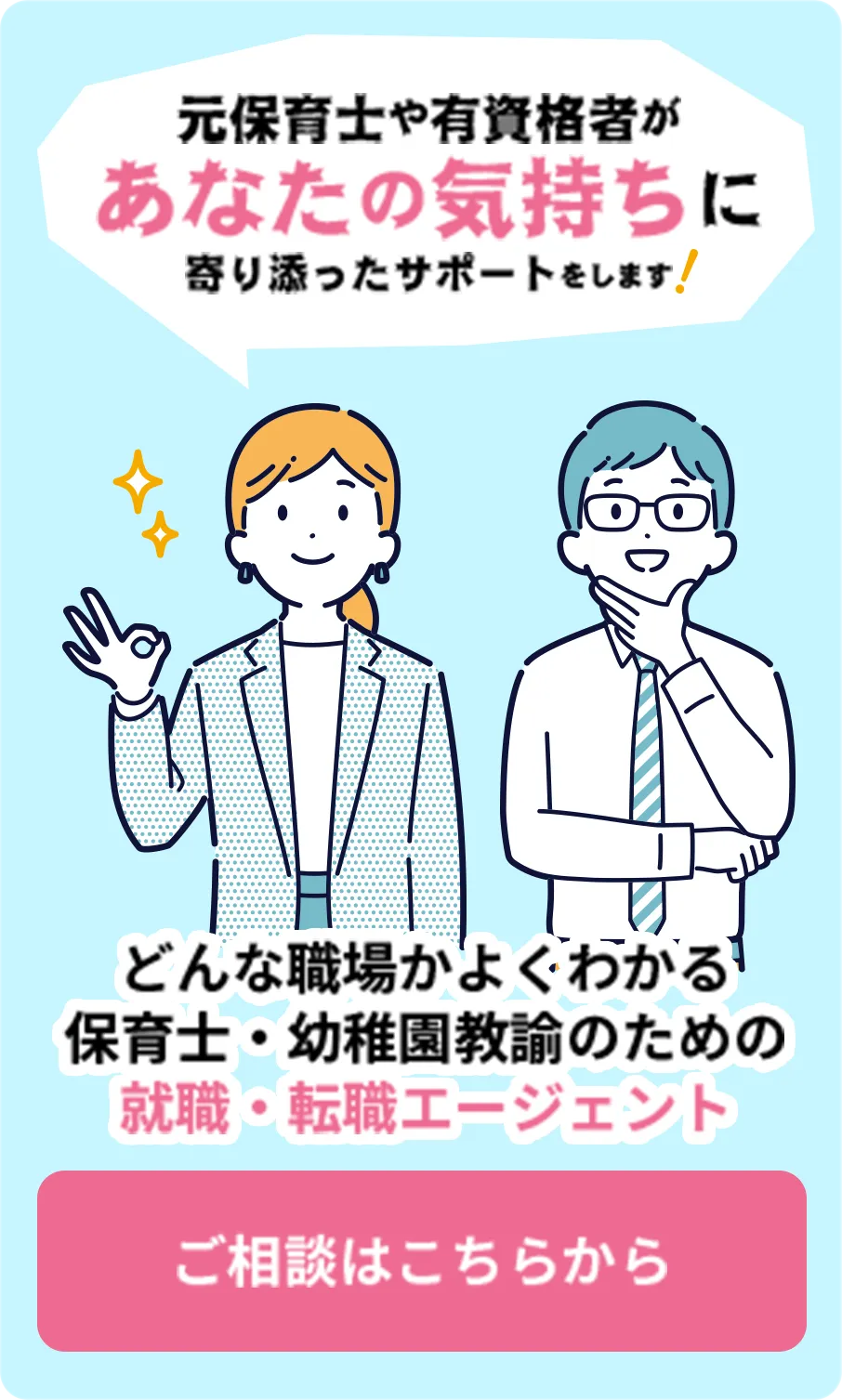保育園の作品展は、担当者にとって大きなプレッシャーがかかる行事の1つです。
テーマ決めや準備に追われ、どうすれば子どもたちの成長を見せられるか悩むことも多いでしょう。
しかし、作品展は園の保育方針を保護者や外部に伝える絶好の機会でもあります。
本記事では、作品展のねらいや準備の流れ、子どもたちが夢中になるテーマ例や年齢別のアイデアを解説します。
ぜひ参考にしていただき、子どもたちの成長を最大限に引き出す作品展を実現してください。
Contents
保育園の作品展とは?
保育園の作品展は、子どもたちが1年を通して製作した絵や工作などを展示し、保護者に披露する行事です。
ここでは、作品展が持つ3つの側面を解説します。
- 子どもの1年間の成長を発表する場
- 保護者と子どもの成長を共有する機会
- 保育方針を伝える重要なイベント
作品展が持つ意味を深く理解することで、より充実したイベントにできるでしょう。
子どもの1年間の成長を発表する場
作品展は、子どもたちの1年間の成長を発表する集大成の場です。
たとえば、最初はなぐり描きしかできなかった子が、人の顔を描けるようになるなど、その成長は顕著です。
作品は、子どもたちがさまざまな素材に触れ、試行錯誤しながら表現する力を身につけてきた証といえるでしょう。
完成した作品だけでなく、そこに至るまでの過程すべてが、子どもたちの学びと成長の物語です。
この成長の軌跡を、作品展を通して多くの人と分かち合うことに大きな意味があります。
保護者と子どもの成長を共有する機会
作品展は、保護者にとって子どもの園での様子や成長を具体的に知れる貴重な機会です。
普段の送り迎えだけでは見えにくい、子どもたちの創造力や集中力、友だちと協力する姿などを作品から感じ取れます。
自分の子どもの作品を見つける喜びはもちろん、ほかの子どもたちの作品を見ることで、クラス全体の成長や雰囲気も伝わるでしょう。
保護者が子どもの成長を実感し、園への理解と信頼を深めるためのコミュニケーションの場となります。
子ども自身も、自分の作品を保護者に見てもらうことで、大きな喜びと自信を得られます。
保育方針を伝える重要なイベント
作品展は、園の保育理念や教育方針を具体的な形で示す重要なイベントです。
子ども主体の保育を掲げる園では、大人が手を加えすぎない自由な表現が作品に表れます。
環境教育に力を入れる園なら、廃材を活用した作品が多く展示されるでしょう。
展示方法にも園の姿勢が表れ、全員の作品を平等に展示する園、個性を重視して展示スペースを工夫する園など、それぞれの考え方が反映されます。
保育士のかかわり方も作品から読み取れ、適切な援助と見守りのバランスが取れているかが分かります。
保育園で作品展を行う目的やねらい
保育園で作品展を行うことには、子どもたちの心と体の成長を促すための、多くの教育的な目的やねらいが込められています。
作品を完成させることだけがゴールではありません。
製作の過程で子どもたちが何を学び、どのような力を育むのかを理解しておくことが、保育士として適切な援助を行ううえで不可欠です。
ここでは、作品展が持つおもな4つの目的とねらいを解説します。
- 創造力や表現力を育む
- 最後までやり遂げる達成感を得る
- 友だちと協力する楽しさを学ぶ
- 自分の作品を認めてもらい自己肯定感を高める
これらのねらいを意識して、日々の製作活動に取り組みましょう。
創造力や表現力を育む
作品展のもっとも大きな目的の1つは、子どもたちの創造力や表現力を育むことです。
子どもたちは、粘土や絵の具、廃材などさまざまな素材に触れる中で、その感触や性質を五感で感じ取ります。
そして「こうしたらどうなるかな」と試行錯誤しながら、自分の心の中にあるイメージを形にしようとします。
この過程そのものが、豊かな感性や自由な発想力を養ううえで重要です。
保育士は、子どもたちのユニークな発想を否定せず、自由に表現できるような声かけや環境作りを心がけることが求められます。
最後までやり遂げる達成感を得る
1つの作品を最後まで作り上げる経験は、子どもに大きな達成感をもたらします。
製作活動では、すぐに完成する簡単なものから、時間をかけてじっくり取り組むものまでさまざまです。
とくに、少し難しい課題に挑戦し、試行錯誤の末に完成させたときの喜びは格別です。
この「やり遂げた」という経験が自信となり、次の活動への意欲や粘り強く取り組む力を育てます。
作品展で自分の作品が飾られることは、その達成感をさらに大きなものにし、子どもたちの頑張りを可視化する素晴らしい機会となります。
友だちと協力する楽しさを学ぶ
作品展では、クラス全体やグループで1つの大きな作品を作る「共同製作」が行われることも多くあります。
共同製作の過程では、子どもたちが「何を作りたいか」「どうやって作るか」を話し合い、役割を分担し、協力し合います。
ときには意見がぶつかることもありますが、それを乗り越えて1つの目標に向かう経験は、協調性や社会性を育むうえで欠かせません。
友だちと力を合わせて何かを成し遂げる喜びや楽しさを味わうことは、子どもたちの人間関係をより豊かなものにしていくでしょう。
自分の作品を認めてもらい自己肯定感を高める
作品展で自分の作品が展示され、保護者や先生、友だちに「すごいね」「上手だね」と褒めてもらう経験は、子どもの自己肯定感を高めます。
自分の頑張りが認められたという喜びは、大きな自信につながるからです。
この経験を通して、子どもは「自分は大切な存在なんだ」「自分にもできることがあるんだ」と感じます。
自己肯定感は、子どもがこれからさまざまなことに意欲的に挑戦していくための心の土台となります。
作品展は、子ども一人ひとりが主役となり、輝ける素晴らしい機会です。
作品展の準備から開催までの流れ
作品展を成功させるためには、計画的な準備が不可欠です。
テーマ決めから当日の展示まで、子どもたちの主体性を大切にしながら、見通しを持って進めていくことが求められます。
ここでは、作品展の準備から開催までの一般的な流れを5つ紹介します。
- 開催時期とテーマを決める
- 指導案を作成し製作を開始する
- 保護者へのお知らせと協力依頼をする
- 会場のレイアウトを考え設営する
- 作品の展示方法を工夫する
これらの流れを参考に、計画的に準備を進めていきましょう。
開催時期とテーマを決める
作品展の準備は、まず開催時期とテーマを決めることから始まります。
開催時期は、子どもたちの1年間の成長が見えやすい秋から年度末の2月頃にかけて行われることが多いです。
テーマは、作品展全体の方向性を決める要素です。
絵本の世界や動物、季節など子どもたちが興味を持ち、イメージを広げやすいものを選びましょう。
保育士が一方的に決めるのではなく、子どもたちと話し合って決めることで、製作への意欲を高められます。
園全体で1つのテーマに取り組む場合や、クラスごとに異なるテーマを設定する場合など、園の方針に合わせて決めましょう。
指導案を作成し製作を開始する
テーマが決まったら、具体的な指導案を作成し、計画的に製作を開始します。
指導案には、活動のねらいや必要な材料や道具、予想される子どもの姿、保育士の援助などを具体的に記述します。
年間指導計画や月案、週案と連動させ、無理のないスケジュールを組むことが大切です。
いきなり大きな作品に取り組むのではなく、個人製作でさまざまな技法を経験してから共同製作へと発展させるなど、活動の順序も工夫しましょう。
子どもたちが主体的に製作を楽しめるよう、環境構成にも配慮することが肝心です。
保護者へのお知らせと協力依頼をする
作品展の開催が近づいてきたら、保護者へのお知らせと協力依頼を行います。
案内状には、日時や場所といった基本情報だけでなく、作品展のテーマや見どころ、子どもたちが製作に励んでいる様子などを書き添えます。
製作には牛乳パックや食品トレー、木の実といった廃材や自然物が必要になることも多いです。
その場合は、必要なものをリストアップし、できるだけ早い段階で協力をお願いしましょう。
保護者の協力を得ることで、園と家庭が一体となって作品展を盛り上げられます。
会場のレイアウトを考え設営する
作品をより魅力的に見せるためには、会場のレイアウトや設営も重要です。
まず、子どもたちや保護者の動線を考え、安全で鑑賞しやすいレイアウトを計画します。
年齢順に展示スペースを配置すると、子どもの発達段階に応じた成長の様子が分かりやすくなります。
壁面や天井なども活用し、テーマに合わせた装飾を施すことで、会場全体に一体感が生まれるでしょう。
子どもたちの作品が主役であることを忘れず、作品が映えるような背景や照明を工夫することも欠かせません。
子どもたちも設営に参加することで、作品展への期待がさらに高まります。
作品の展示方法を工夫する
作品の展示方法を一工夫することで、子どもたちの頑張りや成長をより深く伝えられます。
完成した作品だけを飾るのではなく、製作途中の真剣な表情や、友だちと協力している様子の写真を添えてみましょう。
子ども自身が書いた作品のタイトルや「ここを頑張ったよ」というコメントをつけるのもおすすめです。
また、作品を子どもの目線の高さに展示したり、作品の中に入って遊べるようにしたりと、子ども自身も楽しめるような工夫を取り入れると喜ばれます。
展示方法の工夫1つで、作品展は単なる成果発表の場から、感動的な物語を伝える空間へと変わります。
作品展のテーマ例でアイデアを広げる
作品展のテーマは、子どもたちが「作ってみたい」と心から思えるような、魅力的で発展性のあるものを設定しましょう。
毎年同じようなテーマでマンネリ化してしまう、という悩みを持つ保育士もいるかもしれません。
ここでは、子どもたちの製作意欲をかき立てる、人気のテーマ例を6つ紹介します。
- 絵本の世界
- 動物園や水族館
- 季節(春夏秋冬)
- 宇宙や未来
- お祭りやお店屋さん
- 歌の世界
これらのテーマをヒントに、子どもたちと話し合いながらオリジナルの作品展を企画してみてください。
絵本の世界
子どもたちが大好きな絵本の世界は、作品展のテーマとして人気があります。
「はらぺこあおむし」や「ぐりとぐら」など、親しみのある物語の世界をクラス全体で表現します。
登場するキャラクターを個人製作で作り、背景や大きなアイテムを共同製作で担当するなど、役割分担もしやすいでしょう。
絵本を読み聞かせ、物語の世界観を共有してから製作に入ることで、子どもたちはイメージを膨らませやすくなります。
完成した展示空間は、まるで絵本の中に入り込んだような没入感を味わえ、子どもも大人も楽しめます。
動物園や水族館
動物園や水族館も、子どもたちの好奇心を刺激する人気のテーマです。
園全体を1つの動物園や水族館に見立て、各クラスがさまざまな動物や海の生き物を製作します。
段ボールで作った等身大のキリンやゾウ、天井から吊るした色とりどりの魚やクラゲなど、力強い展示が可能です。
遠足で実際に動物園や水族館に行った経験と結びつけると、子どもたちはより意欲的に製作に取り組むでしょう。
完成した会場では、飼育員さんになりきって作品の説明をするなど、ごっこ遊びに発展させられます。
季節(春夏秋冬)
日本の美しい四季の移ろいは、作品展のテーマとしても最適です。
園全体で1つの季節を表現するのもよいですし、クラスごとに「春」「夏」「秋」「冬」を分担するのも面白いでしょう。
春は満開の桜やチューリップ、夏はきらめく海や花火、秋は紅葉の森やハロウィン、冬は雪景色やクリスマスなど、各季節ならではのモチーフが豊富にあります。
散歩で見つけた落ち葉や木の実を製作に取り入れるなど、子どもたちの実体験と結びつけやすいのも魅力です。
季節感を表現することで、子どもたちの自然への関心も深まります。
宇宙や未来
宇宙や未来といったテーマは、子どもたちの無限の想像力をかき立てます。
折り紙やアルミホイルを使ってロケットやUFOを作ったり、惑星や星々を天井から吊るして宇宙空間を表現したりと、幻想的な世界観を作り出せます。
「未来の街」や「未来の乗り物」など、子どもたちが自由に発想を広げられるテーマ設定も面白いでしょう。
正解がないテーマだからこそ、子ども一人ひとりのユニークなアイデアが光ります。
暗い部屋でブラックライトを当てるといった演出も、子どもたちをワクワクさせるはずです。
お祭りやお店屋さん
お祭りやお店屋さんは、製作して終わりではなく、その後のごっこ遊びに発展させられるのが大きな魅力です。
たこ焼きやわたあめなどの屋台、金魚すくいや輪投げなどのゲームコーナーをみんなで作り、作品展当日にお祭りごっこを開催します。
お寿司屋さんやケーキ屋さん、おもちゃ屋さんなど、子どもたちの「なりたい」を形にするお店屋さんごっこも人気です。
作った品物を並べ、お客さんと店員さんに分かれて遊ぶことで、社会性やコミュニケーション能力も育まれます。
保護者も参加できる体験型の展示は好評です。
歌の世界
子どもたちが普段から親しんでいる童謡や季節の歌をテーマにするのも素敵なアイデアです。
「おもちゃのチャチャチャ」の歌に合わせておもちゃの兵隊やフランス人形を作ったり、「アイアイ」の歌からジャングルの世界を広げたりできます。
歌詞が具体的なイメージの手助けとなり、子どもたちも製作に取り組みやすいでしょう。
作品展の当日にテーマとなった歌をBGMとして流したり、みんなで合唱したりするのも楽しい演出です。
音楽と造形活動を結びつけることで、子どもたちの感性をより豊かに育めます。
【乳児編】保育園の作品展の年齢別アイデア
乳児クラスの作品展では、完成度の高さよりも、子どもたちが製作の過程そのものを楽しむことがもっとも大切です。
0~2歳では心身の発達に大きな違いがあるため、それぞれの発達段階に合わせた活動を取り入れる必要があります。
安全に配慮しながら、五感を存分に使って楽しめるようなアイデアを考えましょう。
ここでは、乳児クラス向けの年齢別アイデアを3つ紹介します。
- 0歳児:手形・足形アートや感触遊び
- 1歳児:シール貼りやちぎり絵
- 2歳児:のりやハサミを使った製作
子どもの「できた」という喜びを引き出すことを第一に考えましょう。
0歳児:手形・足形アートや感触遊び
0歳児の製作は、素材の感触を五感で楽しむことが中心です。
絵の具を手や足につけて画用紙にぺったんと押す手形・足形アートは、成長の記録にもなり保護者にも喜ばれます。
小さな手形や足形を動物や乗り物に見立てると、可愛らしい作品に仕上がります。
指で直接絵の具に触れて描くフィンガーペインティングもおすすめです。
絵の具のぬるぬるとした感触は、子どもにとって新鮮な体験となるでしょう。
保育士は子どもが口に入れても安全な素材を選び、汚れてもよい環境で、子どもの自由な表現を温かく見守ることが大事です。
関連記事:0歳児担任の保育士は大変?大切にしたいことや向いている人の特徴を紹介
1歳児:シール貼りやちぎり絵
1歳児になると、指先の使い方が少しずつ器用になり、つまんだり貼ったりする動きが楽しめるようになります。
台紙からシールを剥がして画用紙に貼るシール貼りは、集中力を養うのにも最適な活動です。
さまざまな色や形のシールを用意し、魚のうろこや果物などに見立てて自由に貼らせてあげましょう。
折り紙をビリビリと破るちぎり絵も、指先の感覚を養いながら楽しめる製作です。
ちぎった紙をのりで貼って、動物の毛並みや木の葉などを表現します。
子どもの「自分でやりたい」という気持ちを尊重し、必要に応じてそっと手伝う姿勢がおすすめです。
2歳児:のりやハサミを使った製作
2歳児になると、保育士の補助のもとで、のりやハサミといった道具を使い始めます。
最初は、保育士が切ったパーツを子どもがのりで貼る活動から始め、慣れてきたら一回切りができるハサミに挑戦してみましょう。
道具の安全な使い方を丁寧に伝えることが肝心です。
この時期は、見立て遊びやごっこ遊びが豊かになるため、作ったもので遊べるような製作も喜びます。
たとえば、お弁当の具材を作ってお弁当箱に詰めたり、お面を作って動物になりきったりするなど、遊びにつながるテーマを設定するとよいでしょう。
【幼児編】保育園の作品展の年齢別アイデア
幼児クラスになると、子どもたちは自分のイメージをより具体的に表現できるようになり、友だちと協力して活動を進める力も育ってきます。
3~5歳と年齢が上がるにつれて、より複雑でダイナミックな製作に挑戦できます。
保育士は、子どもの発達段階を見極め、少しだけ背伸びすれば達成できるような課題を設定することが大切です。
ここでは、幼児クラス向けの年齢別アイデアを3つ紹介します。
- 3歳児:身近な素材を使った個人製作
- 4歳児:グループで取り組む立体製作
- 5歳児:ストーリー性のある共同製作
子どもたちの成長に合わせて、製作活動の幅を広げましょう。
3歳児:身近な素材を使った個人製作
3歳児になると、ハサミやのりを自分で上手に使えるようになり、自分のイメージしたものを形にしようとする意欲が高まります。
空き箱やカップ、トイレットペーパーの芯といった身近な素材を自由に組み合わせ、動物や乗り物などを作る立体製作が楽しめます。
この時期は、まだ1人でじっくりと自分の世界に入り込んで製作することを楽しむ子どもが多いです。
保育士は、子どもたちの発想が広がるように、さまざまな種類の素材を豊富に用意しておくことが大切です。
完成した作品について「これは何を作ったの?」と尋ね、子どもの思いを受け止め、共感する言葉をかけるようにしましょう。
4歳児:グループで取り組む立体製作
4歳児になると、友だちと共通のイメージを持って、相談したり役割を分担したりしながら活動を進められます。
数人のグループで、1つのテーマに沿ってジオラマなどを作る立体製作に挑戦してみましょう。
たとえば「ぼくたちの街」というテーマで、それぞれが家やお店、乗り物を作り、大きな模造紙の上に並べて1つの街を完成させます。
製作の過程で子ども同士の話し合いを見守り、必要に応じて保育士が仲立ちをすることで、協調性やコミュニケーション能力を育めます。
5歳児:ストーリー性のある共同製作
5歳児(年長)になると、クラス全体で1つの目標に向かって、長期間にわたって粘り強く取り組む力が育ちます。
絵本の世界を再現したり、自分たちで考えた物語を形にしたりと、ストーリー性のある壮大な共同製作に挑戦できます。
たとえば、大きな段ボールを使ってお城や海賊船を作り、その中でごっこ遊びをするなど、ダイナミックな活動が可能です。
子どもたちのアイデアを最大限に尊重し、保育士は技術的なサポート役に徹することが求められます。
仲間と力を合わせて大きな作品を完成させた経験は、子どもたちにとって大きな自信と、クラスの絆を強めるかけがえのない思い出となるでしょう。
保育士が作品展で心がけたいポイント
作品展は子どもたちが主役のイベントです。
見栄えの良さや完成度の高さを求めるあまり、保育士が主導になってしまうと、作品展本来の目的を見失ってしまいます。
ここでは、作品展において保育士が心がけておきたいポイントを4つ解説します。
- 子どもの主体性を尊重する
- 製作過程を写真などで記録し共有する
- 一人ひとりの個性を大切にする
- 安全面に配慮する
詳しく見ていきましょう。
子どもの主体性を尊重する
作品展で優先すべきは、子どもの主体性を尊重することです。
作品を作るのはあくまで子どもたちであり、保育士は手伝いすぎてはいけません。
子どもが「こうしたい」と考え、試行錯誤する過程そのものが学びです。
保育士の役割は、子どもがイメージを形にできるよう、さまざまな素材を用意したり、道具の使い方を教えたりといった環境を整えることです。
子どもが困っているときにはヒントを与えることも必要ですが、答えを教えるのではなく、子ども自身が考え解決できるよう見守りましょう。
製作過程を写真などで記録し共有する
作品展で展示されるのは完成品ですが、そこに至るまでの過程にこそ子どもたちの成長が詰まっています。
真剣に色を選ぶ姿や友だちと相談する様子、完成時の笑顔など、さまざまな瞬間を写真や動画で記録します。
これらの記録は、展示の際に作品と一緒に掲示することで、見る人により深く伝わるでしょう。
日々の製作の様子をクラスだよりやブログで紹介することも効果的です。
保護者も製作過程を知ることで、完成作品への理解が深まり、子どもとの会話も弾みます。
記録は保育の振り返りにも活用でき、次年度の参考資料にもなります。
一人ひとりの個性を大切にする
子どもたちの作品を、上手か下手かという基準で評価してはいけません。
肝心なのは、その子らしい表現ができているかどうかです。
同じテーマで製作しても、できあがる作品は一人ひとり違って当たり前です。
その違いこそが、その子の個性であり魅力といえます。
保育士は、すべての子どもの作品のよいところを見つけ、具体的に褒めるように心がけましょう。
「この色使いが素敵だね」「面白い形ができたね」といった前向きな声かけが、子どもの自信と次の創作意欲につながります。
画一的な作品を目指すのではなく、多様な個性が輝く作品展を目指してください。
安全面に配慮する
子どもたちが安心して製作活動に取り組めるよう、安全面への配慮は徹底しなければなりません。
とくに、ハサミやカッター、接着剤などの道具を使用する際には、事前に正しい使い方を丁寧に指導し、活動中も目を離さないでください。
乳児クラスでは、ビーズやボタンなどの小さな素材の誤飲に注意が必要です。
子どもの年齢や発達段階に応じて、使用する素材や道具を慎重に選ぶことが求められます。
会場の設営においても、作品が倒れたり子どもがつまずいたりしないよう、安全確認を怠らないようにしましょう。
作品展から見抜く「よい保育園」の特徴
転職を考えている保育士にとって、作品展は園の保育の質や理念、職場の雰囲気などを知るための貴重な情報源です。
園見学などで作品展の様子を見る機会があれば、単に作品の上手さを見るだけでなく、その背景にある保育のあり方を読み解く視点を持つことが賢明です。
ここでは、作品展から「よい保育園」を見抜くための4つを紹介します。
- 作品に子どもの発達や個性が表れているか
- 保育士が過度に手伝いすぎていないか
- 子ども自身が楽しんで製作した様子が伝わるか
- 展示方法に子どもへの配慮が見られるか
それぞれ見ていきましょう。
作品に子どもの発達や個性が表れているか
まず注目したいのは、作品の多様性です。
もし、展示されている作品がどれも同じようにきれいに作られている場合、それは保育士の指示どおりに作らせる画一的な保育の表れかもしれません。
よい保育園の作品展では、同じテーマでも形や色がさまざまで、一つひとつの作品にその子らしさが表れています。
年齢ごとの展示を見ることで、その園が子どもの発達段階を正しく理解し、それに合った活動を提供できているかも分かるでしょう。
子どもの個性や発達を尊重する姿勢が、作品の多様性につながります。
保育士が過度に手伝いすぎていないか
作品の見栄えをよくしようとするあまり、保育士が手を加えすぎていないかどうかはよく見ると分かります。
大人が手伝った作品は、きれいで完成度が高いかもしれませんが、そこからは子どもの試行錯誤の跡が見えません。
少し歪んでいたり、色がはみ出していたりしても、それが子ども自身の力で作った証です。
保育士の手伝いが過度な園は、成果主義に偏っていたり、保育士の自己満足で保育を進めていたりする傾向があるかもしれません。
子どもが主役であるという基本を大事にしている園かどうかを見極めましょう。
子ども自身が楽しんで製作した様子が伝わるか
作品そのものから、子どもたちが楽しんで製作した様子が伝わってくるかどうかも感じ取ってみましょう。
生き生きとした線や大胆な色使い、自由な発想の形などからは、子どもが夢中になって取り組んだことがうかがえます。
さらに、製作過程の写真が展示されていれば、子どもたちの表情から楽しさや真剣さが直接分かります。
保育士が子どもたちの活動を丁寧に記録し、そのプロセスを大切にしている園は、子ども一人ひとりに寄り添う保育を実践している可能性が高いです。
関連記事:子どもたちに人気の手遊び7選!楽しくなるアレンジの仕方も紹介
展示方法に子どもへの配慮が見られるか
会場の展示方法からも、園の子どもたちに対する姿勢を読み取れます。
たとえば、車椅子でも通りやすいように通路の幅が確保されているか、鑑賞に疲れた親子が休憩できるスペースが設けられているかなどです。
すべての来場者に対する配慮が行き届いているかを確認しましょう。
また、子どもが自分の作品を見つけやすいように、名前や顔写真が分かりやすく添えられているかもポイントです。
子ども一人ひとりを尊重する姿勢が、展示の細部に表れます。
まとめ:魅力的な作品展で保育園の特色を伝えよう
子どもたちの成長と創造性を伝える作品展は、保護者や地域にとって貴重な機会です。
年齢に応じた製作活動を通じて、子どもたちの発達段階や個性が輝く作品が生まれます。
転職を検討されている保育士の方にとっては、園の保育方針や質を見極める判断材料にもなるでしょう。
「保育のせかい」では、現役の保育士や園の経営者が監修した、保育業界のリアルな情報を反映した求人情報を提供しています。
アドバイザーの多くが保育士有資格者であり、求職者が信頼できる情報にもとづいて理想のキャリアを築くための支援を行います。
希望する職場を見つけるために、ぜひ「保育のせかい」であなたにぴったりの求人を探してください。
この記事の監修者

森 大輔(Mori Daisuke)
保育のせかい 代表
《資格》
保育士、幼稚園教諭、訪問介護員
《経歴》
2017年 保育のせかい 創業。2021年 幼保連携型認定こども園を開園するとともに、運営法人として、社会福祉法人の理事長に就任。その他 学校法人の理事・株式会社の取締役を兼任中。
「役に立った!」と思ったらいいね!してね(^-^)
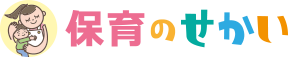

 2025.10.20
2025.10.20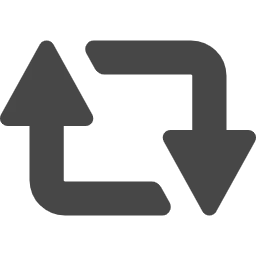 2026.01.05
2026.01.05