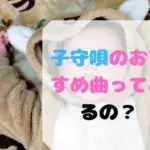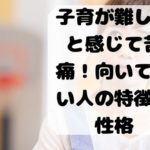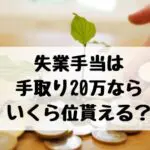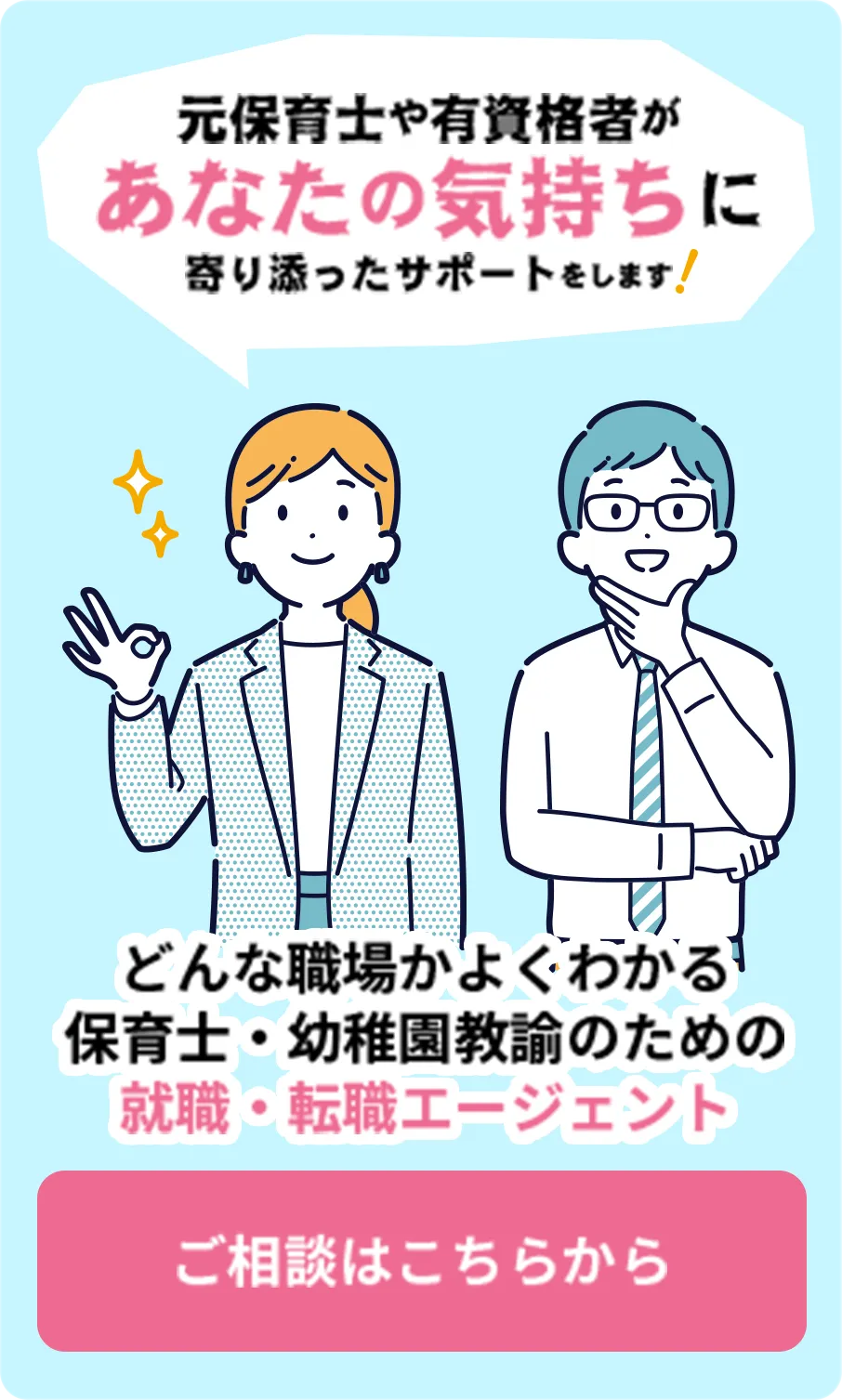異年齢保育を導入している園への転職を考えたとき、年齢別保育との違いや保育士に求められる役割について、不安を感じることもあるでしょう。
子どもたちの社会性や思いやりを育む大きな可能性がある一方で、保育士にはより柔軟な対応力や専門性が求められます。
本記事では、異年齢保育の基本的な考え方から子どもたちの育ちを促すねらい、メリット・デメリットを解説します。
室内や屋外で楽しめる遊びのアイデアもお伝えしますので、参考にしてください。
Contents
異年齢保育とは?
年齢の異なる子どもたちで1つのクラスを構成し、共に生活しながら保育を行う形態のことです。
一般的な年齢別のクラス編成とは異なり、子どもたちが実社会と同じように多様な年齢の人々とかかわりながら成長することを目指します。
ここでは、異年齢保育の基本について、以下3つを解説します。
- 年齢別保育との違い
- 縦割り保育や混合保育との関係
- 園によって異なる導入形態
これらの基本を理解することで、異年齢保育の全体像を掴めます。
年齢別保育との違い
年齢別保育は、同じ年齢の子どもたちでクラスを構成する「横割り保育」です。
同じ発達段階の子どもたちが集まるため、活動計画が立てやすいというのが特徴です。
一方、異年齢保育は、年齢の異なる子どもたちでクラスを構成する「縦割り保育」を指します。
少子化により、家庭や地域で異年齢の子どもとかかわる機会が減っている現代において、その重要性が注目されています。
年上の子が年下の子を助け、年下の子は年上の子から学ぶという、兄弟のような関係性を園生活の中で自然に築けるでしょう。
この違いを理解することが、異年齢保育を知る第一歩です。
縦割り保育や混合保育との関係
「異年齢保育」「縦割り保育」「混合保育」は、基本的には同じ意味で使われる言葉です。
いずれも、年齢の異なる子どもたちが同じクラスやグループで一緒に過ごす保育形態を指します。
園の方針や地域によって呼び方が異なる場合がありますが、その本質は同じです。
年齢という「横」のつながりだけでなく、異なる年齢間の「縦」のつながりを大切にすることから「縦割り保育」と呼ばれます。
さまざまな年齢の子どもたちが混ざり合って生活することから「混合保育」という言葉も使われます。
どの呼び方であっても、多様な人間関係の中で子どもたちの成長を促すという目的は共通です。
園によって異なる導入形態
異年齢保育の導入方法は、園によってさまざまです。
一日を通して異年齢のクラスで過ごす「完全縦割り型」の園もあれば、特定の時間帯や活動だけ異年齢のグループで行う「部分導入型」の園もあります。
たとえば、朝の会や外遊びの時間だけを異年齢で過ごしたり、運動会や発表会などの行事で異年齢のチームを組んだりするケースです。
また、利用する子どもの人数が少ない延長保育や土曜保育の時間帯に限定して、合同で保育を行う園もあります。
異年齢保育のねらいと子どもの育ち
異年齢保育は、子どもたちが多様な人間関係の中で心豊かに成長していくための、明確な教育的な「ねらい」を持って実践されます。
それは、実社会の縮図のような環境で、生きていくうえで不可欠な力を自然に身につけることです。
ここでは、以下4つを説明します。
- 社会性や協調性を育む
- 思いやりの心を育てる
- 自己肯定感を高める
- 生きる力を養う
これらのねらいを理解することで、異年齢保育の教育的価値をより深く知れます。
社会性や協調性を育む
異年齢保育のもっとも大きなねらいの1つは、子どもたちの社会性や協調性を育むことです。
年齢の違う子どもたちが一緒に遊んだり生活したりする中で、自然と協力し合う場面が生まれます。
たとえば、難しいブロックの組み立てを年上の子が手伝ってあげたり、遊びのルールを年下の子に分かりやすく説明したりする姿が見られます。
年上の子は他者をリードする経験をし、年下の子は年上の子の行動を模倣することで、社会のルールや人と協力する大切さを体感的に学んでいくでしょう。
このように、子どもたち同士のかかわり合いそのものが、社会性を育むための貴重な学びの場となります。
思いやりの心を育てる
自分より小さい子や困っている子に対して、自然と手を差し伸べる経験ができるのも異年齢保育の大きな特徴です。
たとえば、転んで泣いている年下の子に「大丈夫?」と声をかけたり、靴を履くのに苦労している子を手伝ってあげたりする場面が日常的に見られます。
こうした経験を通して、年上の子は相手の気持ちを考え、行動する優しさを身につけます。
年下の子も、優しくしてもらった経験から、自分も他者に親切にしようという気持ちが芽生えるでしょう。
このような心の交流を繰り返すことで、相手を思いやる豊かな心が育まれていきます。
自己肯定感を高める
異年齢保育は、子どもたち双方の自己肯定感を高める効果も期待できます。
年下の子は、さまざまなことに挑戦する年上の子の姿を見て「あんなお兄さん、お姉さんになりたい」という憧れの気持ちを抱きます。
この憧れが、新しいことへの挑戦意欲や向上心につながるでしょう。
一方、年上の子は年下の子から「すごいね」「ありがとう」と慕われることで、自分に自信を持ち、よき手本であろうと努力します。
お互いが刺激し合い認め合うこの関係性が、それぞれの「自分は大切な存在だ」という自己肯定感を育むうえで大切な役割を果たします。
生きる力を養う
異年齢のかかわりの中では、自分の思いどおりにならないことも多く経験します。
言葉の発達段階が違う相手にどうやって気持ちを伝えるか工夫したり、遊びのルールを年下の子にも分かるように変更したりする必要が出てきます。
たとえば、鬼ごっこで年長児が「小さい子を捕まえるときはタッチだけにする」というルールを自主的に提案することも。
こうした経験は、相手の状況を理解し、問題を解決しようとする思考力やコミュニケーション能力を養います。
これらは、予測困難な社会を生き抜くうえで不可欠な「生きる力」そのものといえるでしょう。
異年齢保育のメリット
異年齢保育は、子どもたちにとって多くの成長の機会をもたらします。
ここでは、異年齢保育がもたらすさまざまなメリットを6つ紹介します。
- 年上児に憧れの気持ちを持つ
- 興味関心の幅が広がる
- 友達の輪が広がる
- 発達差が目立ちにくくなる
- リーダーシップが身につく
- 保育士自身のスキルアップにつながる
詳しく見ていきましょう。
年上児に憧れの気持ちを持つ
年下の子どもにとって、年上の子どもは身近な憧れの存在です。
鉄棒で逆上がりができたり、難しい漢字が読めたりする姿を見て、「自分もあんな風になりたい」という強い動機付けが生まれます。
この憧れの気持ちは、新しいことに挑戦する意欲や向上心を引き出す大きな力となります。
保育者が「〇〇をしましょう」と促すよりも、子どもが自らの意思で「やってみたい」と感じる場面が増えるからです。
身近に目標とする人がいることで、子どもたちは日々の生活の中で自然と成長へのエネルギーを得られます。
興味関心の幅が広がる
異年齢保育では、同年齢の集団だけでは出会えないような、多様な遊びや活動に触れる機会が増えます。
これにより、子どもたちの興味や関心の幅が大きく広がります。
たとえば、3歳児が普段遊ばないような少し難しいルールのあるゲームを5歳児がしているのを見て、興味を持って仲間に入れてもらうことがあるでしょう。
反対に、5歳児が2歳児のごっこ遊びに加わることで、新たな発想を得て遊びがさらに発展することもあります。
異なる発達段階の子どもたちが互いの遊びに影響を与え合うことで、一人ひとりの世界が豊かになり、知的好奇心や探究心が刺激されます。
友達の輪が広がる
年齢別のクラスでは、交友関係が同年齢の特定のグループに固定されがちです。
しかし、異年齢保育では、年齢の垣根を越えて友達を作れます。
活発な5歳児と少しおっとりした4歳児が、遊びの好みが合うことから親友になる、といったことも珍しくありません。
自分と違う年齢の友達とかかわることで、多様な価値観に触れ、より柔軟な人間関係を築く力が養われます。
年齢に関係なく気の合う仲間を見つけられる環境は、子どもにとって安心できる居場所を増やすことにもつながります。
発達差が目立ちにくくなる
同じ年齢の集団の中では、月齢による発達の差が目立ちやすいことがあります。
しかし、異年齢の集団では、さまざまな発達段階の子どもがいるのが当たり前です。
そのため、個々の発達のペースの違いが「差」として意識されにくくなります。
たとえば、3歳児クラスでまだお話が苦手な子も、2歳児や1歳児がいる環境では、むしろ「お話ができるお兄さん」として見られることも。
これにより、子どもは他者と比較して劣等感を抱くことなく、自分のペースで安心して成長できます。
リーダーシップが身につく
年上の子どもは、年下の子どもとかかわる中で、自然とリーダーシップを発揮する場面が増えます。
遊びのルールを教えたり、グループをまとめたり、困っている子を助けたりする経験を通して、責任感や人を思いやる気持ちが育まれます。
保育者にいわれて行動するのではなく、子どもが自ら「自分がやらなくては」と感じて行動することが肝心です。
このような経験は、自信を育むとともに、将来社会で求められる協調性やリーダーシップの素地を養うことにつながります。
保育士自身のスキルアップにつながる
異年齢保育は、保育士にとっても専門性を高める絶好の機会です。
0歳から5歳まで、幅広い年齢の子どもたちと日常的にかかわることで、子どもの発達の連続性を肌で感じられます。
年齢別保育では分断されがちな発達のつながりを一体として捉えられるようになり、保育士としての視野が格段に広がります。
多様な発達段階の子どもが楽しめる活動を計画する力や、個々に応じた柔軟な声かけなど、保育士としての総合的なスキルアップが期待できるでしょう。
関連記事:0歳児担任の保育士は大変?大切にしたいことや向いている人の特徴を紹介
異年齢保育のデメリット
異年齢保育には多くのメリットがある一方で、実践するうえでの難しさや課題も存在します。
ここでは、異年齢保育で起こりうるデメリット4つを解説します。
- 力関係で解決してしまう
- 発達段階に適した遊びができない
- 個別のニーズに合わない
- 安全への配慮がより一層必要になる
それぞれ見ていきましょう。
力関係で解決してしまう
異年齢の集団では、どうしても年上で体の大きい子どもが優位に立ちやすい傾向があります。
おもちゃの取り合いなどのトラブルが発生した際に、言葉での交渉ではなく、力で解決しようとしてしまう場面が見られることがあります。
年下の子どもが自分の意見をいえずに、常に年上の子どもの言いなりになってしまう可能性も否定できません。
保育士は、子ども同士の力関係が一方的にならないよう注意深く見守り、必要に応じて介入し、対等な関係で話せるようサポートすることが大切です。
発達段階に適した遊びができない
活動内容の設定が難しいことも、異年齢保育の課題の1つです。
年長児にとっては簡単すぎて退屈に感じてしまう遊びが、年少児にとってはルールが複雑で参加できない、という状況が起こり得ます。
すべての子どもが満足できる活動を計画することは容易ではありません。
結果として、一部の子どもが遊びの輪に入れず、疎外感を覚えてしまう可能性があります。保育士には、同じ活動の中でも年齢に応じて役割を変えたり、ルールを調整したりするなど、全員が楽しめるような工夫と創造力が求められます。
個別のニーズに合わない
一人ひとりの子どもに丁寧にかかわることが難しくなる側面もあります。
多様な年齢の子どもたちの要求に同時に応えなければならないため、保育士の注意は常に分散されがちです。
たとえば、甘えたい盛りの3歳児と、じっくり話を聞いてほしい5歳児のニーズに、同時に応えるのは困難な場合があります。
保育士が「一人ひとりに十分にかかわれていない」と感じ、精神的な負担が増加する可能性も。
個々のニーズを把握しつつ、クラス全体を運営していくバランス感覚が保育士には求められます。
安全への配慮がより一層必要になる
体格差の大きい子どもたちが同じ空間でダイナミックに遊ぶため、常に怪我のリスクが伴います。
たとえば、走り回って遊んでいる幼児が、ハイハイしている乳児に気づかずにぶつかってしまう危険性も。
幼児向けのおもちゃに含まれる小さな部品を、乳児が誤飲してしまうリスクも高まります。
保育士は、年齢別保育以上に広い視野で全体を見渡し、危険な箇所がないか、ヒヤリハットにつながる状況が生まれていないかを常に予測しましょう。
環境設定や声かけを通じて事故を未然に防ぐ、より高度な安全管理能力が不可欠です。
異年齢保育の指導案と年間指導計画の立て方
異年齢保育を成功させるためには、綿密な指導計画が不可欠です。
複数の年齢の発達を同時に視野に入れながら、子どもたち一人ひとりの育ちを支える計画を作成する必要があります。
全体の目標と、年齢ごとの具体的なねらいを明確にすることがポイントです。
ここでは、異年齢保育における指導案や年間指導計画を作成する際の要点3つを紹介します。
- 全体のねらいと年齢別のねらいを立てる
- 子どもの姿を具体的に予測する
- 年齢ごとの援助と配慮を明記する
これらのポイントを押さえることで、質の高い指導計画を作成できます。
全体のねらいと年齢別のねらいを立てる
指導案を作成する際、まずはクラス全体としての大きな「ねらい」を設定します。
たとえば、「協力して1つのことを成し遂げる喜びを感じる」といった、社会性や情動面に関するものが中心です。
次に、その全体のねらいを達成するために、各年齢の子どもにどのような育ちを期待するか、具体的な「年齢別のねらい」を立てます。
同じ活動でも3歳児は「年上児の真似をして楽しむ」、5歳児は「年下児が楽しめるよう工夫する」と、発達段階に応じた目標を設定することが肝心です。
子どもの姿を具体的に予測する
指導案作成では、活動中の子どもたちの姿を年齢ごとに具体的に予測することが有用です。
たとえば、共同製作では「5歳児が率先して材料を準備し、4歳児が製作の中心となり、3歳児は簡単な作業を担当する」といった姿が予想されます。
トラブルが起きやすい場面も予測し、「順番待ちで年下の子どもが我慢できずに泣く」「年上の子どもが指示的になりすぎる」などの状況も想定します。
このような予測を立てることで、事前に対策を考えられるでしょう。
実際の活動後は予測と実際の姿を比較し、次回の計画に活かしていくことが大切です。
年齢ごとの援助と配慮を明記する
設定した年齢別のねらいを達成し、予測される子どもの姿を支えるために、保育士がどのような援助や配慮を行うべきかを具体的に記述します。
これは、指導案の核となる部分です。
たとえば、同じ製作活動でも「2歳児にはのりの使い方を丁寧に伝える」「4歳児にはハサミを安全に使うための約束事を再確認して見守る」と記述。
子ども同士のかかわりは「年上の子が年下の子に教える場面ではやり取りを見守る」など、保育士の立ち位置を明確にしておきます。
これにより、複数の保育士が共通認識を持って保育にあたれます。
異年齢保育で気をつけることと保育士のかかわり方
異年齢保育の成功は、保育士がどのような役割を担い、子どもたちとどうかかわるかにかかっています。
年齢別保育とは異なる、異年齢保育ならではの専門的な視点と配慮が求められます。
子どもたちの主体性を尊重し、安全な環境の中で豊かな育ち合いを促すことが保育士の役割です。
ここでは、以下5つのポイントを解説します。
- 一人ひとりの発達段階を正確に把握する
- 年齢差を考慮した声かけを心がける
- 子ども同士のかかわりを丁寧に見守る
- トラブル発生時は双方の気持ちを受け止める
- 保育者間で密に連携する
これらを意識することで、保育の質を大きく向上させられます。
一人ひとりの発達段階を正確に把握する
異年齢保育の基本は、クラスにいる一人ひとりの子どもの発達段階を正確に理解することです。
たとえば3歳児と5歳児では、できることも興味の対象も大きく異なります。
保育士は、それぞれの平均的な発達だけでなく、子ども一人ひとりの個性や得意なこと、苦手なことを把握しなければなりません。
この深い子どもへの理解があるからこそ、個々に合った適切な援助や声かけが可能になります。
日々の観察を丁寧に行い、子どもの小さな成長や変化を見逃さない姿勢が肝心です。
年齢差を考慮した声かけを心がける
異年齢の集団では、声かけの仕方には工夫しなければなりません。
クラス全体に向けて話すときは、一番小さい子にも理解できるような、具体的で分かりやすい言葉を選ぶことが大切です。
一方で、年長児と個別に話す際には、彼らの思考力を刺激するような、少し難しい言葉を使ったり、問いかけたりすることも要します。
また、年上の子が年下の子を手伝った際には、「ありがとう、助かったよ」と具体的に褒め、その行動の価値を伝えることが、思いやりの心を育むうえで効果的です。
状況に応じて言葉を使い分ける柔軟性が求められます。
子ども同士のかかわりを丁寧に見守る
異年齢保育では、子ども同士の自発的なかかわり合いが学びの宝庫です。
子どもたち自身で解決できるトラブルには、保育士はすぐに介入せず、じっと見守る忍耐力も必要になります。
年上の子が年下の子に何かを教えている場面や、一緒に何かを作り上げようとしている場面を丁寧に見守り、その育ち合いの過程を尊重しましょう。
ただし、安全が脅かされる場合や、一方的な関係になりそうなときには、適切に介入する判断力も同時に求められます。
トラブル発生時は双方の気持ちを受け止める
おもちゃの取り合いなどのトラブルは、子どもたちが社会性を学ぶ絶好の機会です。
保育士の対応で肝心なのは、すぐに善悪を判断して裁定を下すことではありません。
まずは、双方の言い分をじっくりと聞き、「貸してほしかったんだね」「まだ使いたかったんだね」と、それぞれの気持ちを代弁し、受け止めることが第一です。
子どもは自分の気持ちを理解してもらえたと感じることで、落ち着きを取り戻し、相手の気持ちを考える余裕が生まれます。
そのうえで「どうしたらよいかな?」と問いかけ、子どもたち自身で解決策を見つけられるように導くことが理想的なかかわり方です。
保育者間で密に連携する
異年齢保育を円滑に進めるためには、保育者間のチームワークが不可欠です。
クラスにいる複数の保育者が、一人ひとりの子どもの情報やクラス全体の状況を常に共有し、共通の認識を持って保育にあたらなければなりません。
たとえば、「Aちゃんは最近、Bくん(年下)のお世話に疲れ気味かもしれない」といった情報を共有することで、チーム全体でフォローできます。
日々の打ち合わせや連絡ノートなどを活用し、密にコミュニケーションを取ることで、一貫性のある質の高い保育を提供できます。
異年齢保育で盛り上がる室内での遊び
異年齢の子どもたちが一緒に室内で遊ぶ際には、誰もが参加でき、かつ年齢に応じてかかわり方を工夫できるような遊びが理想的です。
ここでは、異年齢保育で盛り上がる室内での遊び3つを紹介します。
- 役割分担が楽しいごっこ遊び
- 協力して作る共同製作
- ルールが簡単なゲーム遊び
詳しく見ていきましょう。
役割分担が楽しいごっこ遊び
お店屋さんごっこやおままごとなどのごっこ遊びは、異年齢保育の定番であり、子どもたちが大好きな活動の1つです。
この遊びの優れた点は、子どもたちが自然に自分の発達段階に合った役割を見つけ出せることです。
たとえば、年長児が店員さんやお父さん・お母さん役を担い、年少児がお客さんや赤ちゃん役になるといったように、無理なく役割分担が生まれます。
年上の子は年下の子をリードし、年下の子は年上の子のやり取りを真似ることで、社会のルールやコミュニケーションの方法を楽しく学べます。
協力して作る共同製作
1つの大きな作品をみんなで協力して作る共同製作は、異年齢の子どもたちの団結力を高めるのに効果的です。
たとえば、大きな模造紙に季節の絵を描いたり、段ボールで秘密基地を作ったりする活動があげられます。
この活動では、それぞれの発達段階に応じた役割分担が可能です。
年長児が全体のデザインを考えたり、ハサミなどの難しい道具を使ったりする部分を担当。
年少児はちぎった折り紙を貼ったり、絵の具で色を塗ったりする部分を担当します。
全員で力を合わせて1つのものを作り上げる経験は、子どもたちに大きな達成感と連帯感をもたらします。
関連記事:保育園の作品展を成功させるには?テーマ例や年齢別のアイデアを紹介
ルールが簡単なゲーム遊び
異年齢でゲームをする際は、誰でもすぐに理解できるシンプルなルールであることが大切です。
たとえば、「じゃんけん列車」は、じゃんけんをして負けた人が勝った人の後ろにつながっていくだけなので、小さい子も直感的に楽しめます。
「フルーツバスケット」も、自分のフルーツを覚えて移動するという簡単なルールで参加できます。
年長児は空いている椅子を素早く見つける戦略性を楽しむなど、年齢に応じて楽しみ方を見出せるでしょう。
全員が同じルールのもとで一体感をもちながら楽しめるのが、こうしたゲームの魅力です。
異年齢保育で楽しめる屋外での遊び
屋外での遊びは、子どもたちが思い切り体を動かし、心を開放できる貴重な時間です。
異年齢で戸外遊びを行う際は、体格差や運動能力の違いを考慮しつつ、全員が一緒に楽しめるような工夫が求められます。
ここでは、異年齢保育の屋外活動としておすすめの遊びを3つ紹介します。
- 全員で楽しめる集団遊び
- 発見が広がる自然探索
- 協力が生まれるルールのある鬼ごっこ
これらの遊びを通じて、子どもたちは心身ともに健やかに成長できます。
全員で楽しめる集団遊び
「だるまさんがころんだ」や「かごめかごめ」といった昔ながらの集団遊びは、異年齢保育に適しています。
これらの遊びは、ルールがシンプルで、運動能力の差が出にくいというのが特徴です。
鬼の言葉に合わせて動きを止めたり、わらべうたに合わせて動いたりするため、小さい子も無理なく参加できます。
また、大縄跳びも人気のある活動です。
縄を揺らす役を年長児が担い、年少児がそれを跳び越えるなど、協力しながら楽しめます。
全員で1つの遊びを共有する経験は、クラスの一体感を高めるのに役立ちます。
発見が広がる自然探索
公園や園庭での散歩や自然探索は、子どもたちがそれぞれの興味関心に応じてかかわれる、優れた異年齢活動です。
たとえば、2歳児が地面を歩くアリの行列を夢中で観察している横で、5歳児が図鑑を使ってその虫の名前を調べている、といった光景が生まれます。
年長児が発見した珍しい形の葉っぱやきれいな石を、年少児に「見て!」と教えてあげるなど、自然な学び合いの交流が生まれることも少なくありません。
保育者は子どもたちの発見に共感し、その興味をさらに深めるような声かけをすることが大切です。
協力が生まれるルールのある鬼ごっこ
一般的な鬼ごっこは、走る速さの違いから年長児が有利になりがちですが、ルールを少し工夫することで、協力と思いやりの気持ちを育む遊びに変えられます。
その代表例が「しっぽ取り」です。
このゲームでは個人戦だけでなく、年長児と年少児でペアを組み、「年長児はペアになった年少児のしっぽを守る」というルールが加えられます。
年長児は自分のしっぽだけでなく、パートナーのしっぽも守ろうと必死になるでしょう。
この協力プレーを通して、自然と相手を思いやる気持ちや責任感が育まれていきます。
異年齢保育で子どもが安心して過ごせる環境作りの工夫
異年齢保育における環境構成は、すべての年齢の子どもが安心して過ごせることを最優先に考える必要があります。
年齢による活動量や興味の違いを考慮し、それぞれが自分のペースで過ごせる空間を確保することが大切です。
物理的な環境だけでなく、心理的な安心感を生み出す工夫も欠かせません。
ここでは、以下3つの環境構成のポイントを説明します。
- 動と静の活動スペースを分ける
- 1人で落ち着けるコーナーを確保する
- さまざまな発達段階に対応できるおもちゃを用意する
これらの工夫により、保育士のよりきめ細やかな配慮と指導を可能にし、より豊かな保育を展開できます。
動と静の活動スペースを分ける
保育室内には、ダイナミックに体を動かして遊びたい子もいれば、静かに集中して遊びたい子もいます。
とくに異年齢保育ではその差が大きいため、活動内容によってスペースを分ける「コーナー保育」の考え方が有効です。
たとえば、部屋の一方にはマットを敷いて体を動かせる「運動コーナー」を設け、もう一方には絵本やパズル、お絵かきなどができる「静的コーナー」を設けます。
こうして空間を緩やかに区切ることで、走り回る年長児と、座って遊ぶ年少児との接触による事故を防げます。
1人で落ち着けるコーナーを確保する
集団生活の中では、どのような子どもでも時には1人になりたい、少し休憩したいと感じることがあります。
異年齢の集団では、さまざまな刺激に疲れてしまう子も少なくありません。
そのため、部屋の隅にカーテンで仕切られたスペースや1人だけが入れるようなテントなどを設置し、落ち着けるコーナーを確保することが大切です。
そこには、肌触りのよいクッションや、お気に入りのぬいぐるみなどを置いておくとよいでしょう。
このような「逃げ場」があることで、子どもは安心して集団生活を送れます。
さまざまな発達段階に対応できるおもちゃを用意する
各コーナーに置くおもちゃや素材は、さまざまな発達段階の子どもが楽しめるように、多様な種類を準備することが重要です。
たとえば、ブロックコーナーには乳児でも安全に扱える大きなソフトブロックと、幼児が複雑な形を作れる小さなブロックの両方を用意します。
製作コーナーにはちぎるだけの紙やシール(2~3歳児向け)から、ハサミやのり、細かい装飾パーツ(4~5歳児向け)まで幅広くそろえておきましょう。
子どもたちは、そのときの自分の「やってみたい」「できそう」という気持ちに合わせて、自ら素材を選び、主体的に遊びを展開できます。
まとめ:異年齢保育を理解して保育の幅を広げよう
異年齢保育は、単なる年齢混合の保育ではなく、子どもたちの社会性や思いやりの心を育む重要な保育方法として、多くの園で実施されています。
メリット・デメリットを理解し、適切な環境構成や指導方法を身につけることで、保育の質を大きく向上できます。
転職を考えている保育士の方にとって、異年齢保育の経験は貴重なキャリアアップの機会となるでしょう。
保育のせかいでは、全国の認可保育園や認定こども園、小規模保育園など、さまざまな施設の求人情報を掲載しています。
異年齢保育を実施している園の求人も取り扱っており、保育士資格をお持ちのアドバイザーが、あなたの希望に合った職場探しをサポートします。
大阪の保育士求人なら、保育のせかいへお任せください。
まずは無料の求人紹介サービスをご利用ください。
この記事の監修者

森 大輔(Mori Daisuke)
保育のせかい 代表
《資格》
保育士、幼稚園教諭、訪問介護員
《経歴》
2017年 保育のせかい 創業。2021年 幼保連携型認定こども園を開園するとともに、運営法人として、社会福祉法人の理事長に就任。その他 学校法人の理事・株式会社の取締役を兼任中。
「役に立った!」と思ったらいいね!してね(^-^)
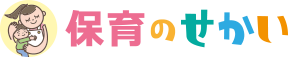

 2025.10.20
2025.10.20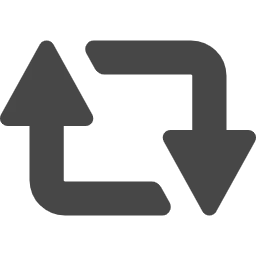 2026.01.05
2026.01.05