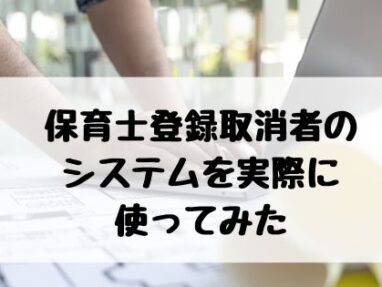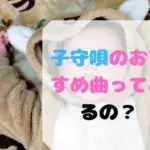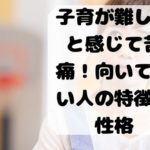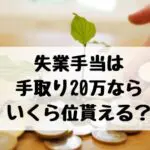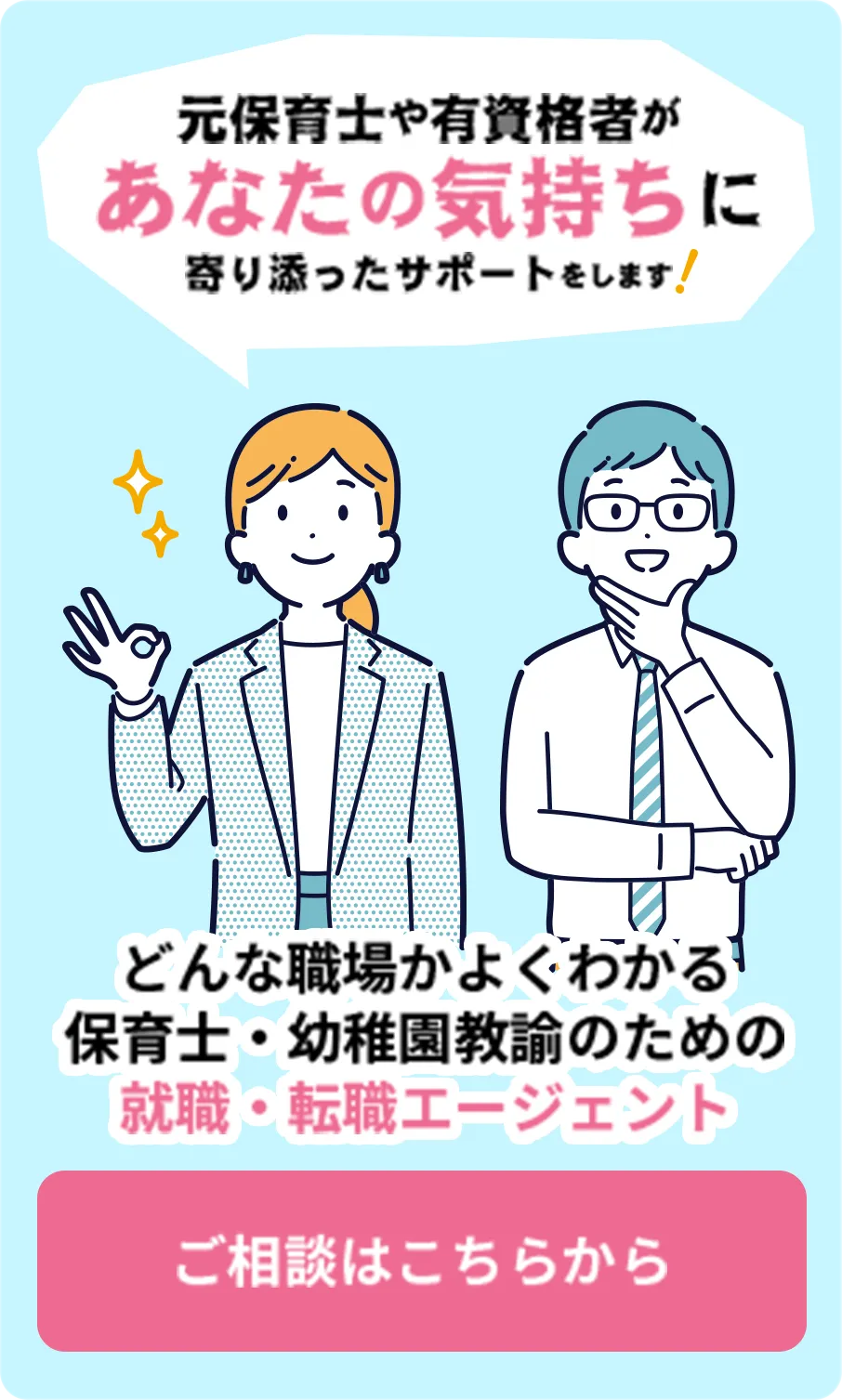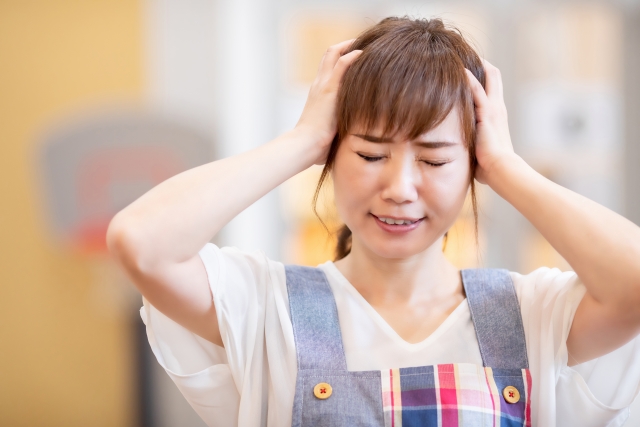
保育士として働く中で、人間関係や仕事量の多さにストレスを感じていませんか。
毎日子どもたちの笑顔に触れる素敵な仕事である一方、体力的・精神的な負担から「もう限界かもしれない」と感じる瞬間もあるでしょう。
本記事では、保育士がストレスを感じる8つの原因と、今すぐ実践できるストレス解消法を解説します。
ストレスと上手に付き合いながら、保育士として長く働き続けるためのヒントを見つけてください。
Contents
保育士がストレスを感じる8つの原因
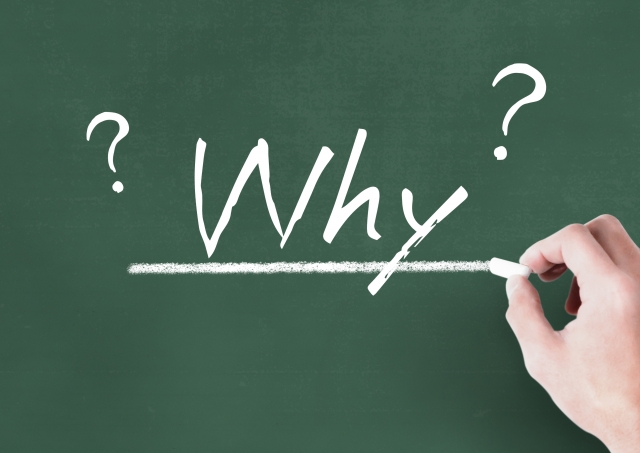
保育士の仕事は子どもたちの成長を支える重要な役割を担っていますが、その責任の重さゆえに多くのストレスを抱えやすい職業でもあります。
ストレスとなる以下8つの原因を正しく理解することで、適切な対処法を見つけられます。
- 職場の人間関係が原因で心が疲れる
- 仕事量の多さでキャパオーバーになる
- 体の疲労が限界を超える
- 給料の安さが将来不安を増大させる
- 職場環境や方針が合わない
- 給与や待遇に不満を持つ
- 責任の重さにプレッシャーを感じる
- 保護者対応に苦労する
詳しく見ていきましょう。
職場の人間関係が原因で心が疲れる
先輩保育士からの厳しい指導や同僚との価値観の違い、派閥や陰口などが日常的に存在する職場では、心が疲弊してしまいます。
とくに女性が多い職場環境では、人間関係が複雑になりやすく、些細なことがトラブルに発展することも。
また、園長や主任との関係性も大きなストレス要因となります。
理不尽な要求や努力を認めてもらえない環境では、モチベーションを保つことが困難になります。
人間関係のストレスは、仕事のパフォーマンスにも影響を与え、結果として子どもたちへの保育の質にもかかわってくるため、早めの対処が必要です。
仕事量の多さでキャパオーバーになる
保育士の業務は子どもの保育だけでなく、書類作成から行事の準備、保護者対応など多岐にわたります。
日誌や指導計画、個別記録などの書類は勤務時間内に終わらず、持ち帰り仕事になることも少なくありません。
とくに行事前は準備に追われ、休憩時間も取れないほど忙しくなります。
慢性的な人手不足により、1人あたりの業務量は増加する一方です。
本来なら複数人で分担すべき仕事を1人でこなさなければならず、物理的にも精神的にも限界を超えてしまいます。
このような状況が続くと、仕事へのやりがいを見失い、燃え尽き症候群に陥る危険性もあります。
体の疲労が限界を超える
保育士の仕事は想像以上に体力を消耗します。
子どもを抱っこしたり、一緒に遊んだり、常に中腰の姿勢で作業することが多く、腰痛や肩こりに悩む保育士は多いです。
また、感染症のリスクも高く、体調を崩しやすい環境にあります。
しかし、人手不足のため簡単に休むこともできず、無理をして働き続けることに。
年齢を重ねるにつれて体力の衰えを感じ、若い頃のように動けなくなることへの不安も募ります。
十分な休息が取れない状況では、疲労が蓄積し、慢性的な体調不良につながります。
体の疲労は心の疲労にも直結するため、早めのケアが必要です。
給料の安さが将来不安を増大させる
保育士の平均年収は、令和6年賃金構造基本統計調査で約412万円となっています。
日本の給与所得者の平均年収460万円(国税庁調査)と比べると48万円低い水準です。
月収は28万1,000円ですが、手取りにすると約21万円前後。
新人や地方では手取り17〜18万円も珍しくありません。
1人暮らしでは家賃と生活費でほとんどが消え、貯金する余裕がないのが現実です。
同年代の他業種で働く友人との給与格差は依然として大きく、結婚や出産、老後の生活を考えると経済的な不安は募るばかりです。
経済的な安定は心の安定にもつながるため、この問題は保育士のストレスの根本的な原因となっています。
職場環境や方針が合わない
園の運営方針や保育理念が自分の考えと合わない場合、大きなストレスになります。
たとえば、子ども一人ひとりに寄り添った保育をしたいのに、効率重視の方針で画一的な保育を求められることも。
理想の保育ができない環境では、保育士としてのやりがいを見失ってしまいます。
また、設備の老朽化や教材不足など、物理的な環境の悪さもストレスの原因となります。
エアコンが効かない、おもちゃが古い、安全対策が不十分など子どもたちによい環境を提供できないことへのもどかしさを感じるでしょう。
このような環境では、自分の保育スキルを十分に発揮できず、専門職としての成長も期待できません。
給与や待遇に不満を持つ
基本給の低さに加えてサービス残業の常態化、有給休暇が取れない、賞与が少ないなど、待遇面での不満は尽きません。
保育士不足が叫ばれているにもかかわらず、待遇改善は遅々として進まず、現場の保育士の負担は増すばかりです。
産休・育休制度はあっても、実際には取得しづらい雰囲気があったり、復帰後の待遇が悪化したりすることも。
同じ保育士でも公立と私立、正社員とパートでは待遇に大きな差があり、不公平感を覚える場合もあるでしょう。
このような待遇の悪さは、保育士という仕事への誇りや意欲を削ぎ、離職の大きな要因となっています。
責任の重さにプレッシャーを感じる
保育士は子どもの命を預かる仕事であり、その責任の重さは計り知れません。
ケガや事故を起こさないよう常に緊張感を持って保育にあたる必要があり、精神的な負担は相当なものです。
アレルギー対応や服薬管理など、1つのミスが重大な事故につながる可能性があるため、神経を張り詰めています。
また、子どもの発達や成長にかかわる責任も重大です。
保護者からの期待も大きく、さまざまな言葉でプレッシャーをかけられることもあります。
このような責任の重さに押しつぶされそうになり、自信を失ってしまう保育士も少なくありません。
保護者対応に苦労する
保護者対応は保育士の重要な業務の1つですが、理不尽なクレームや過度な要求に悩まされることが多くあります。
子どものケガに対する過剰な反応、ほかの子との比較、保育方針への口出しなど、対応に苦慮する場面は日常的です。
中にはモンスターペアレントと呼ばれるような、常識を超えた要求をしてくる保護者もいます。
コミュニケーション不足から誤解が生じることもあり、信頼関係を築くまでに時間と労力を要します。
連絡帳の書き方1つでクレームになることもあり、言葉選びにも細心の注意が必要です。
保護者対応のストレスは、本来の保育業務にも影響を与え、子どもたちに向き合う余裕を奪ってしまいます。
保育士が実践できるストレス解消法【セルフケア編】

日々の生活の中で実践できる方法を身につけることで、ストレスと上手に付き合えるようになります。
ここでは、以下5つのセルフケア方法を紹介します。
- 運動で心身をリフレッシュする
- 信頼できる人に話してストレスを発散する
- 好きなことに没頭して思考を切り替える
- 質のよい睡眠で身体を休ませる
- 栄養バランスの取れた食事を意識する
それぞれ見ていきましょう。
運動で心身をリフレッシュする
運動はストレス解消に効果的な方法の1つです。
激しい運動でなくても、20分程度のウォーキングやヨガ、ストレッチでも十分な効果が期待できます。
保育士の仕事柄、子どもと一緒に体を動かす機会も多いため、それを活用することもおすすめです。
休日にはジムに通ったり、好きなスポーツを楽しんだりすることで、仕事のストレスから解放されます。
運動後の爽快感は、心のモヤモヤを吹き飛ばしてくれるでしょう。
無理のない範囲で、自分に合った運動を習慣化することが大切です。
定期的な運動は、ストレス耐性を高める効果もあります。
信頼できる人に話してストレスを発散する
1人で抱え込まずに、信頼できる人に話を聞いてもらうことは、ストレス解消の基本です。
同じ保育士の友人なら共感してもらえることも多く、アドバイスももらえるでしょう。
家族や恋人、学生時代の友人など、保育の現場を知らない人に話すことで、客観的な意見を聞けます。
話すことで頭の中が整理され、問題解決の糸口が見つかることもあります。
愚痴をいうことに罪悪感を持つ必要はありません。ストレスを溜め込むよりも、適度に発散することの方が健全です。
大切なのは、1人で悩まないことです。
好きなことに没頭して思考を切り替える
仕事のことを忘れて、趣味に没頭する時間を持つことは、心のリフレッシュに欠かせません。
読書や映画鑑賞、音楽・手芸・料理など、自分が心から楽しめることに時間を使いましょう。
没頭することでネガティブな思考から離れ、気持ちをリセットできます。
保育士の仕事は感情労働でもあるため、オフの時間は自分の感情を大切にすることがおすすめです。
好きなアーティストのライブに行く、美術館でアートに触れる、カフェでゆっくり過ごすなど、心が喜ぶことを積極的に取り入れましょう。
「自分へのご褒美」の時間を作ることで、また明日から頑張ろうという気持ちが湧いてきます。
質のよい睡眠で身体を休ませる
十分な睡眠は、心身の疲労回復に不可欠です。
理想的には7〜8時間の睡眠時間を確保したいところですが、忙しい保育士にとっては難しいこともあるでしょう。
その場合は、睡眠の質を高めることに注力しましょう。
寝る前のスマホは控え、部屋を暗くして適温に保つことで、深い睡眠が得られます。
入浴は就寝の1〜2時間前に済ませ、体温が下がるタイミングで眠りにつくとよいでしょう。
アロマオイルやハーブティーを活用することも効果的です。
休日の寝だめは体内リズムを崩すため、できるだけ規則正しい生活を心がけましょう。
良質な睡眠は、ストレス耐性を高め、翌日のパフォーマンス向上にもつながります。
栄養バランスの取れた食事を意識する
忙しさのあまり食事が疎かになりがちな保育士ですが、バランスのよい食事はストレス対策の基本です。
朝食を抜かずに3食きちんと摂ることで、血糖値の安定と共に精神的な安定も得られます。
コンビニ弁当や外食も多くなりがちですが、週末に作り置きをしたり、簡単な自炊を心がけたりすることで、栄養バランスは改善できます。
また、ストレス発散のための暴飲暴食は避け、適度な量を楽しむことが大切です。
水分補給も忘れずに行い、カフェインの摂りすぎには注意しましょう。
体の内側から健康になることで、ストレスに強い体質作りができます。
保育士が実践できるストレス解消法【環境改善編】

セルフケアだけでは限界がある場合、環境そのものを変える勇気も必要です。
自分の心身の健康を守るために、時には大きな決断をすることも大切です。
ここでは、以下3つの環境改善方法を提案します。
- 今の職場で働きやすさを追求する
- 思い切って休職し心と体を休める
- 環境を変えるため転職活動を始める
状況に応じて適切な選択をすることで、保育士として長く健康的に働き続けられます。
今の職場で働きやすさを追求する
すぐに転職や休職ができない場合は、現在の職場で少しでも働きやすい環境を作る努力をしてみましょう。
まずは、信頼できる上司や同僚に相談し、業務量の調整や役割分担の見直しを提案することから始めます。
1人で抱え込んでいた仕事を、チームで分担することで負担は大きく軽減されます。
また、園内研修でストレスマネジメントやメンタルヘルスについて学ぶ機会を設けてもらうことも有効です。
職場全体でストレスケアの重要性を共有することで、お互いをサポートし合える環境が生まれます。
働きやすい職場は、結果として子どもたちにもよい影響を与えます。
思い切って休職し心と体を休める
心身の限界を感じたら、休職という選択肢を検討することも重要です。
医師の診断書があれば、傷病手当金を受給しながら療養することも可能です。
一度立ち止まって、じっくりと自分と向き合う時間を持つことで、本当に大切なものが見えてきます。
休職期間中は治療に専念すると共に、今後のキャリアについても考えるよい機会となります。
焦らず、ゆっくりと心身を回復させることが大切です。
休職は決して恥ずかしいことではなく、よりよい保育士として再スタートを切るための準備期間と捉えましょう。
環境を変えるため転職活動を始める
現在の職場では改善が見込めない場合、転職を視野に入れることも必要です。
保育士の求人は多く、よりよい環境で働けるチャンスは必ずあります。
転職活動は在職中から始められ、保育士専門の転職サイトや転職エージェントを活用することで効率的に進められます。
転職先を選ぶ際は給与面だけでなく、職場の雰囲気や保育方針、福利厚生・研修制度などを総合的に判断することが大切です。
転職は人生の新しいスタートです。
今までの経験を生かしながら、自分に合った職場で再び保育の喜びを感じるでしょう。
まとめ:保育士がストレスと向き合いながら働くために
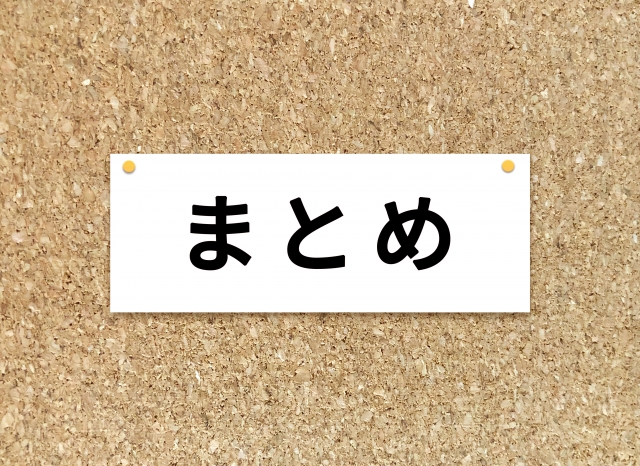
保育士のストレスは決して個人の問題ではなく、多くの方が同じ悩みを抱えています。セルフケアや環境改善の方法を実践することで、今よりも働きやすい状況を作ることは可能です。それでも限界を感じたら、新しい環境を探すことも前向きな選択です。
保育のせかいでは、保育士資格を持つアドバイザーが、あなたの状況を理解したうえで最適な職場をご提案します。年休120日以上、宿舎借り上げ制度など、好条件の求人も多数。電話(0120-553-092)やLINEで、まずは今の悩みをお聞かせください。1人で悩まず、一緒に解決策を見つけましょう。
この記事の監修者

森 大輔(Mori Daisuke)
保育のせかい 代表
《資格》
保育士、幼稚園教諭、訪問介護員
《経歴》
2017年 保育のせかい 創業。2021年 幼保連携型認定こども園を開園するとともに、運営法人として、社会福祉法人の理事長に就任。その他 学校法人の理事・株式会社の取締役を兼任中。
「役に立った!」と思ったらいいね!してね(^-^)
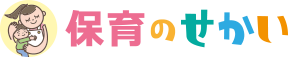

 2025.06.30
2025.06.30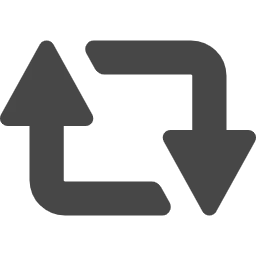 2025.07.02
2025.07.02