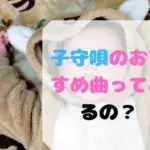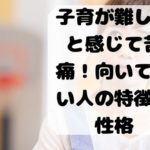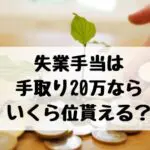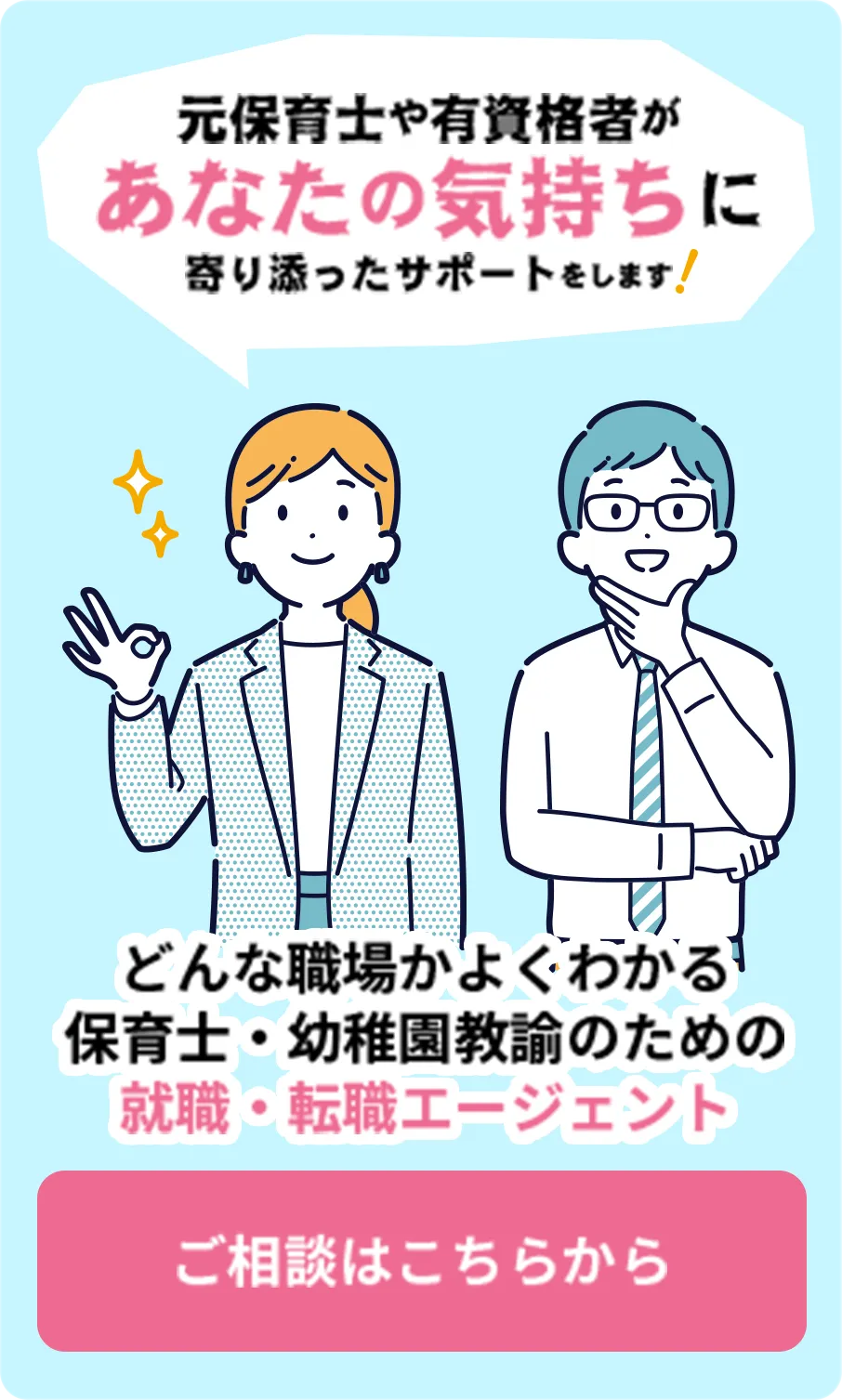日々の保育で「この対応は医療行為にあたらないか」と疑問に感じていませんか?
責任の所在が曖昧な職場では、安心して子どもたちと向き合うことも難しいでしょう。
曖昧な判断は、あなたと子どもたちの双方を危険に晒すことになりかねません。
本記事では、厚生労働省の通知をもとに、保育士がどこまで医療行為を行えるのか、明確な境界線を具体例と共に解説します。
安心して働ける環境を見つけるための、参考にしてください。
Contents
保育士の医療行為は法律で原則禁止されている
保育士による医療行為は、法律によって原則として禁止されています。
しかし、日々の保育現場では、どこまでが許されるのか判断に迷う場面も少なくありません。
ここでは、以下2つを解説します。
- 判断基準となる医師法第17条
- 医療行為が法律で禁止される理由
それぞれ見ていきましょう。
参考資料:医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)
判断基準となる医師法第17条
保育士の医療行為を制限する法律は、医師法第17条と歯科医師法第17条、及び保健師助産師看護師法第31条です。
この法律では、医師免許を持たない者が医業を行うことを固く禁じています。
医業とは、専門的な知識や技術がなければ人体に危害を及ぼすおそれのある「医行為」を、仕事として繰り返し行うことです。
保育士は医師免許を持っていないため、医療行為を行えません。
この法律の存在が、保育士ができることの境界線を考えるうえでの大前提となります。
医療行為が法律で禁止される理由
保育士による医療行為が法律で禁止されているもっとも大きな理由は、子どもの安全を確保するためです。
医療行為には、専門的な医学知識と技術が不可欠であり、1つ間違えれば子どもの健康や生命に重大な危険を及ぼす可能性があります。
たとえば、薬の投与は簡単な作業に見えるかもしれません。
しかし量や種類、時間を間違えれば、深刻な副作用を引き起こすかもしれません。
子どもたちを不測の事態から守るために、医療は資格を持つ専門家に委ねるというルールが法律で定められています。
保育士の医療行為はどこまで可能?「できること」の境界線
ここでは、保育士が対応できることの明確な境界線について、以下3つの観点から解説します。
- 原則として医療行為ではない11の行為
- 医薬品の介助に必須となる3つの条件
- 医療行為に変わりうるグレーゾーン
これらの基準を正しく知ることが、自信を持った保育につながります。
関連記事:保育士で心がけていることは?仕事で気を付けるべきこと
原則として医療行為ではない11の行為
以下に、原則として医療行為にはあたらないとされる11の行為を紹介します。
- 体温の計測
- 自動血圧測定器での血圧測定
- パルスオキシメーターの装着
- 軽微な切り傷や擦り傷の処置
- 安定した状態での医薬品使用の介助
- 異常のない爪の爪切り
- 日常的な口腔内の清掃
- 耳垢の除去
- ストマ装具の排泄物の破棄
- 自己導尿の補助
- 市販の浣腸器を用いた浣腸
それぞれ見ていきましょう。
体温の計測
保育園での日常的な健康管理として、子どもの体温を測ることは医療行為に該当しません。
これには、一般的な電子体温計を脇の下に挟んで測る方法や、耳式体温計で計測する方法が含まれます。
ただし、測定した体温を見て病気の診断をしたり、薬の投与を独自に判断したりすることはできません。
保育士の役割は、あくまで体温を正確に測定し、その結果を記録・報告することです。
もし異常があれば、速やかに園の看護師や保護者に連絡しましょう。
自動血圧測定器での血圧測定
自動血圧測定器を使用して子どもの血圧を測ることも、医療行為には該当しません。
このタイプの測定器は、専門的な技術を必要とせず、ボタン1つで自動的に数値を測定できるためです。
保育士が行うのは、子どもが落ち着いた状態で腕帯を正しく巻き、測定を開始する操作までとなります。
体温測定と同様に、測定結果から医学的な判断を下すことは許されません。
あくまで子どもの健康状態を把握するための1つの手段として捉えましょう。
パルスオキシメーターの装着
パルスオキシメーターを子どもの指先に装着し、血液中の酸素飽和度を測定する行為も医療行為ではありません。
ただし、これは入院治療の必要がなく、容体が安定している子どもに限られます。
機器の装着自体は簡単で体への負担も少ないため、保育士による測定が認められています。
測定の目的は、子どもの呼吸状態を継続的に見守ることです。
数値に異常が見られた場合は、自己判断せずに速やかに看護師や保護者に報告することが肝心です。
軽微な切り傷や擦り傷の処置
子どもが園生活で負った軽い切り傷や擦り傷などに対して、専門的な判断や技術を必要としない処置は医療行為にあたりません。具体的には、傷口を水道水で洗浄したり絆創膏を貼ったり、汚れたガーゼを交換したりする行為などです。
ただし、塗り薬を塗る行為は医療行為にあたるため、医師や保護者の許可がない場合は行わないようにしましょう。
傷が深くて出血が止まらない、異物が混入しているといった場合は、保育士が処置できる範囲を超えています。
安定した状態での医薬品使用の介助
医師から処方された薬の使用を介助することは、後述する3つの条件を満たしていれば医療行為とはみなされません。
たとえば、皮膚への軟膏塗布や湿布の貼付、点眼・一包化された内服薬を飲ませるサポートなどが該当します。
あくまで保育士は「介助」をする立場です。
保護者からの具体的な依頼と指示に基づき、決められた用法・用量を厳守しなければなりません。
自己判断で薬の種類や量を変えると重大な健康被害につながるおそれがあります。
異常のない爪の爪切り
爪自体やその周りの皮膚に化膿や炎症がなく、糖尿病などの専門的な管理が不要な場合に限り、爪切りで爪を切ることは医療行為にあたりません。
爪が伸びていると、子ども自身やほかの子を傷つけてしまう危険性があります。
そのため、安全確保の観点から保育士が爪を切ることは可能です。
ただし、爪が割れている、巻き爪であるといった異常が見られる場合は、専門的なケアが必要なため保育士は対応できません。
保護者に状況を伝えて対応を相談しましょう。
日常的な口腔内の清掃
子どもの日常的な口腔ケアとして、歯ブラシや綿棒などを使って口の中を清潔に保つ行為は医療行為にはあたらないとされています。
具体的には、歯や舌、口腔粘膜に付着した汚れを取り除くことなどです。
ただし、重度の歯周病があるなど、専門的な管理が必要な場合は含まれません。
あくまで健康な状態の口腔内を清潔に保つためのケアが目的です。
食後の歯磨き習慣を身に付けさせるなど、保育の一環として行われる行為と理解しておきましょう。
耳垢の除去
耳掃除も、原則として医療行為には含まれません。
ただし、耳の入り口から見える範囲の耳垢を、綿棒などで安全に取り除く場合に限られます。
耳の奥まで器具を入れたり、固まって取れない耳垢塞栓(じこうそくせん)を除去したりする行為は、耳を傷つける危険があるため医療行為とみなされます。
保育士が行えるのは、あくまで日常的なケアの範囲です。
少しでも難しいと感じた場合は無理をせず、保護者に専門医の受診を促すようにしましょう。
ストーマ装具の排泄物の破棄
ストーマ(人工肛門・人工膀胱)を造設している子どもへのケアのうち、パウチ(袋)に溜まった排泄物を捨てる行為は医療行為に該当しません。
パウチの交換は皮膚を傷つける可能性があるため医療行為とされますが、溜まったものをトイレに流すだけの単純な作業は保育士でも実施可能です。
これは、子どもの体を清潔に保ち、快適に園生活を送るための重要なサポートとなります。
正しい手順を学び、安全に配慮しながら行いましょう。
自己導尿の補助
子ども自身がカテーテルを使って尿を排出する「自己導尿」の補助も、医療行為には該当しません。
保育士が行えるのは、カテーテルの準備や消毒、子どもがスムーズに導尿できるよう体位を保持するなどの間接的なサポートです。
カテーテルを尿道に挿入する行為そのものは医療行為であり、保育士は行えません。
あくまで子どもが自分で行う行為を、安全かつ衛生的に実施できるよう手助けする役割に徹することが賢明です。
市販の浣腸器を用いた浣腸
市販の使い捨てグリセリン浣腸器を用いて浣腸する行為も、一定の条件下で医療行為ではないとされています。
これは、家庭で一般的に行われるケアの1つとみなされているためです。
ただし、使用する浣腸器のサイズや容量には規定があり、それを超えるものは使用できません。
また、浣腸は子どもの身体に負担をかける可能性もあるため、実施する際は園のルールや保護者の意向を必ず確認し、慎重に行う必要があります。
医薬品の介助に必須となる3つの条件
ここでは、保育士が医薬品の介助を行う前に、確認すべき3つの必須条件を解説します。
- 子どもの容態が安定している
- 医師や看護師による経過観察が不要
- 誤嚥など専門的配慮の必要がない
詳しく見ていきましょう。
子どもの容態が安定している
第一の条件は、薬を使用する子どもの容態が安定していることです。
これは、入院や入所による治療が必要な状態ではなく、症状が落ち着いていることを指します。
たとえば、持病の管理のために日常的に同じ薬を使用している場合などがこれにあたります。
反対に、急な発熱や体調不良など、症状が変化する可能性のある不安定な状態では、保育士による与薬の介助はできません。
専門家による医学的判断が必要な場面では、安易に介助を行わないことが鉄則です。
医師や看護師による経過観察が不要
薬の使用にあたって、医師や看護師による継続的な経過観察が必要ないことも条件です。
これは、副作用のリスクが低く、投薬量の細かな調整などを必要としない、状態が安定した子どもに対する薬であることを意味します。
もし、薬を投与したあとの子どもの様子を専門家が注意深く観察する必要がある場合は、保育士が介助できる範囲を超えています。
薬の性質や子どもの状態を正確に把握し、専門的な管理が必要かを見極めることが肝要です。
誤嚥など専門的配慮の必要がない
最後の条件は、薬の使用方法そのものに専門的な配慮が不要であることです。
たとえば、内服薬の場合、子どもに飲み込む力が十分にあり、誤嚥(ごえん)の危険性がないことが前提となります。
坐薬であれば肛門からの出血がないなど、介助行為自体に特別な技術や観察が求められない状態でなければなりません。
少しでも介助に危険が伴うと予測される場合は、医療行為と判断されます。
安全に介助できるかどうかを冷静に判断しましょう。
医療行為に変わりうるグレーゾーン
ここでは、どのような場合に医療行為となりうるのか、とくに注意すべき3つを紹介します。
- 子どもの病状が不安定な場合
- 測定値に基づく保育士の医学的判断
- 異常値が出た際の医療専門職への報告
これらの知識は、現場での的確な判断力につながります。
子どもの病状が不安定な場合
たとえ普段は医療行為にあたらない簡単な処置でも、子どもの病状が不安定な場合は医療行為とみなされることがあります。
たとえば、容態が安定している子の軽い擦り傷に絆創膏を貼ることは問題ありません。
しかし、体調が急変している最中の子への処置は、専門的な管理下で行うべきです。
いつもと同じ行為でも「子どもの状態がいつもと違う」と感じたときには、医療の領域に入ると考え、慎重に対応する必要があります。
測定値に基づく保育士の医学的判断
体温や血圧、酸素飽和度の測定自体は医療行為ではありません。
しかし、その測定値を見て「熱が高いから解熱剤を使おう」といった医学的な判断を下すことは、保育士には許されていない医療行為です。
保育士の役割は、あくまで客観的な数値を測定し、事実を記録・報告することにあります。
測定結果から子どもの状態を推測し、独自の判断で次の行動を決められません。
測定と判断は、全く別の行為であると明確に区別しておきましょう。
異常値が出た際の医療専門職への報告
体温や血圧などの測定で、あらかじめ示されていた範囲を超える異常値が出た場合、保育士がすべきことは1つだけです。
それは、速やかに園の看護師や保護者、場合によっては提携医に連絡し、その後の対応について指示を仰ぐことです。
異常値を前に「どうしよう」と自分で判断に悩むことは、対応の遅れにつながるだけでなく、医療行為を行ってしまうリスクも高めます。
測定したら報告する、そして指示を待つ。
この流れを徹底することが、安全管理の基本です。
まとめ:保育士の医療行為に関する正しい知識で安全に子どもを預かる
医療行為のルールが曖昧な職場で、1人で判断することに不安を感じるかもしれません。
安心して保育に専念できる環境は、子どもとあなた自身を守るために不可欠です。
医療的ケアへの対応力は、転職市場でも重要なスキルとして評価されています。
正しい知識と経験を積むことで、よりよい条件での転職も可能になるでしょう。
「保育のせかい」は、保育園の経営者や現役保育士が監修しており、現場のリアルな情報を反映した求人を提供しています。
保育士資格を持つアドバイザーが、あなたが理想のキャリアを築くための職場探しを全力でサポートします。
大阪の保育士求人なら「保育のせかい」へお任せください。
この記事の監修者

森 大輔(Mori Daisuke)
保育のせかい 代表
《資格》
保育士、幼稚園教諭、訪問介護員
《経歴》
2017年 保育のせかい 創業。2021年 幼保連携型認定こども園を開園するとともに、運営法人として、社会福祉法人の理事長に就任。その他 学校法人の理事・株式会社の取締役を兼任中。
「役に立った!」と思ったらいいね!してね(^-^)
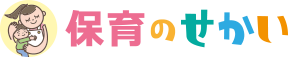

 2025.09.24
2025.09.24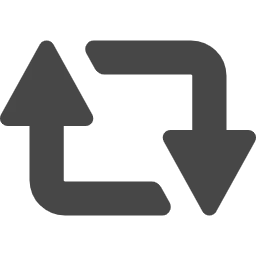 2025.11.12
2025.11.12