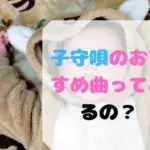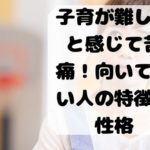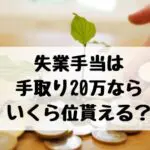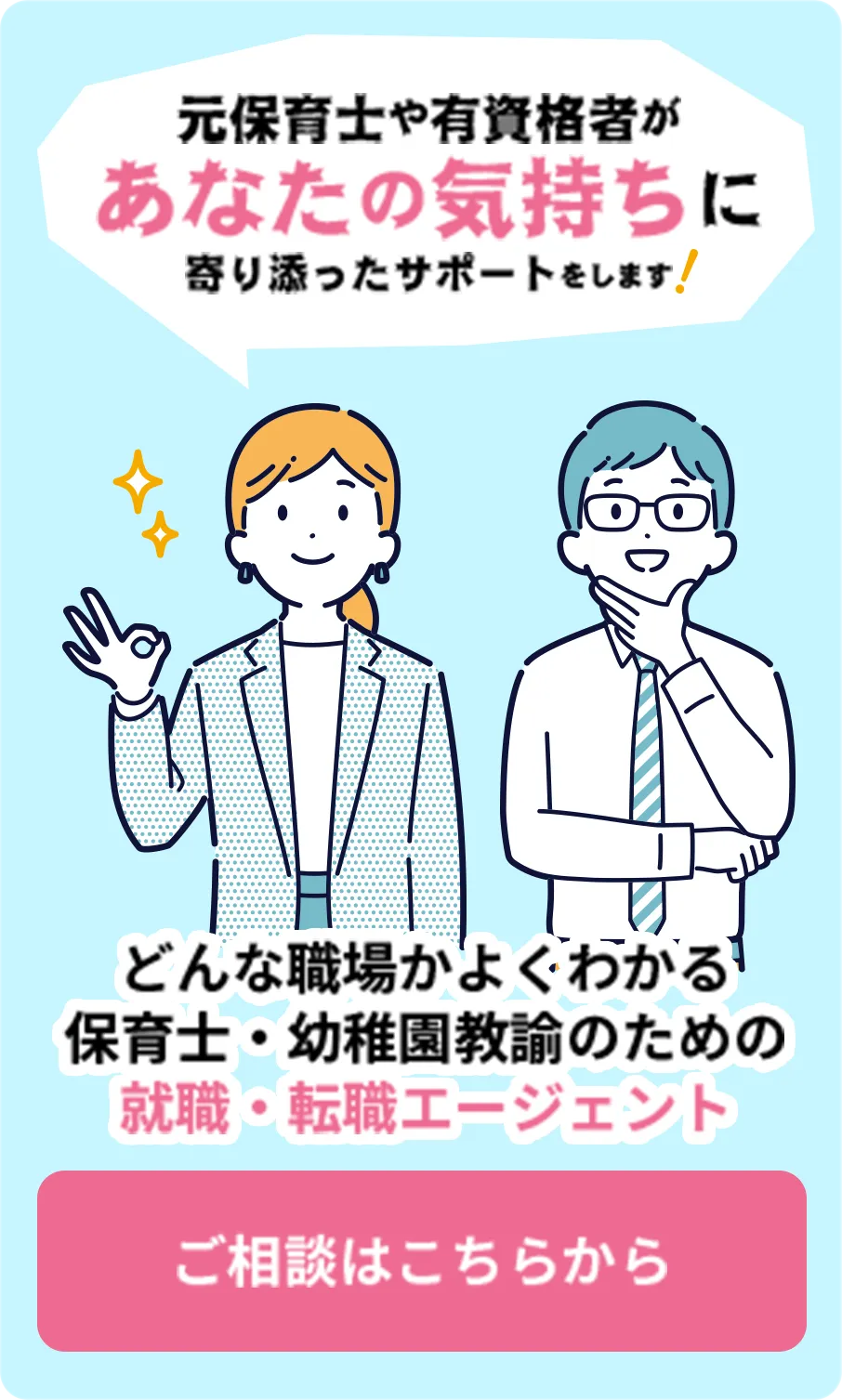保育士からの転職先として学童保育を検討しているものの、「仕事がきつい」「すぐ辞める人が多い」といった声を聞いて不安を感じていませんか?
学童保育の仕事は、やりがいが大きい一方で、特有の大変さがあるのも事実です。
転職後を成功させるためには、仕事内容や続かない理由を正しく理解し、自分に合っているか見極めなければなりません。
本記事では、学童保育指導員の具体的な仕事内容から、多くの人が辞めてしまう8つの理由、そして仕事のやりがいを解説します。
ご自身のキャリアを考えるうえでの参考にしてください。
Contents
学童保育の仕事はきつい?指導員の具体的な仕事内容
学童保育指導員の仕事は、安全管理や事務作業など多岐にわたります。
放課後や長期休暇中に、子どもたちが安全で豊かな生活を送れるようサポートするのがおもな役割です。
具体的にどのような仕事があるのか、おもな業務内容5つを紹介します。
- 子どもの安全を見守り遊びを提供する
- 宿題や学習をサポートする
- おやつを準備して提供する
- イベントを企画し運営する
- 事務作業や保護者連絡を行う
これらの業務を通じて、子どもたちの健全な育成を支援しています。
子どもの安全を見守り遊びを提供する
学童保育指導員のもっとも重要な仕事は、子どもたちが安全に過ごせる環境を整え、見守ることです。
施設内外での怪我や事故を防ぐため、常に子どもたちの行動に注意を払う必要があります。
また、遊びは子どもたちの心身の発達には欠かせないものです。
指導員は集団での遊びを提案したり、室内で楽しめる工作やゲームを用意したりして、子どもたちの自主性や社会性を育むきっかけを提供します。
異年齢の子どもたちが交流できるような働きかけも、大切な役割の1つです。
宿題や学習をサポートする
放課後の時間を使って、子どもたちが学校の宿題や自主学習に取り組むのを見守り、サポートすることも指導員の仕事です。
勉強を強制するのではなく、子どもたちが自主的に机に向かえるような環境作りを心がけます。
分からない問題があればヒントを与えたり、集中力が続くように声をかけたりと、個々の学習ペースに合わせた支援が求められます。
指導員は、子どもたちが「勉強は楽しい」と感じられるよう、根気強く寄り添いながらサポートするのが基本です。
学習のサポートを通じて、子どもたちの知的好奇心を引き出し、学ぶ意欲を育てていきます。
おやつを準備して提供する
子どもたちにとって、おやつは放課後の楽しみの1つです。
指導員は、栄養バランスやアレルギーに配慮しながら、おやつの準備と提供を行います。
また、おやつの時間は子どもたちがリラックスして過ごせる、貴重なコミュニケーションの場です。
指導員は子どもたちと会話を楽しみながら、その日の出来事や体調の変化などを把握します。
みんなで同じものを食べる経験を通じて、食事のマナーや感謝の気持ちを育む食育の役割もあります。
イベントを企画し運営する
学童保育での生活がより楽しく、充実したものになるよう、季節に応じたイベントを企画・運営するのも指導員の仕事です。
夏祭りやクリスマス会、遠足に工作教室など、子どもたちの興味や関心を引き出すような活動を考えます。
イベントは、子どもたちにとって特別な思い出になるだけでなく、協調性や創造性を育む好機です。
指導員は、子どもたちが主体的に参加し、楽しめるような工夫を凝らします。
イベントを通じて、子どもたちの新たな一面を発見したり、成長を実感したりできることも、この仕事の大きな魅力の1つです。
事務作業や保護者連絡を行う
子どもたちの対応以外にも、指導員には多くの事務作業があります。
日々の活動を記録する業務日誌の作成、出欠管理やおたよりの作成、備品の管理・発注などがおもな業務です。
これらの記録は、子どもの様子を正確に把握し、指導員間で情報を共有するために欠かせません。
保護者との連携も主要な業務で、連絡帳の記入やお迎え時の口頭での報告を通じて、その日の子どもの様子や成長を伝えます。
保護者との信頼関係を築くことで、家庭と学童保育が一体となって子どもの成長を支えられます。
学童保育指導員とほかの職種との違い
学童保育指導員と混同されやすい職種に、「放課後児童支援員」や「保育士」があります。
ここでは、学童保育指導員とほかの職種との違いについて解説します。
- 放課後児童支援員
- 保育士
それぞれ見ていきましょう。
放課後児童支援員
放課後児童支援員は、2015年度に新設された専門資格を持つ職員のことです。
学童保育指導員が施設で働くスタッフの総称であるのに対し、放課後児童支援員は都道府県が実施する研修を修了した有資格者を指します。
法律により、学童保育施設には支援単位ごとに2名以上の指導員を配置し、そのうち1名以上は放課後児童支援員でなければならないと定められています。
保育士資格など特定の要件を満たせば研修を受講できるため、キャリアアップを目指すうえで重要な資格です。
参考資料:こども家庭庁「放課後児童健全育成事業の目的 及び制度内容」
保育士
保育士とのもっとも大きな違いは、対象となる子どもの年齢です。
保育士がおもに0歳から小学校就学前までを対象とするのに対し、学童保育指導員は小学生を対象とします。
保育士は食事や排泄、着替えといった基本的な生活習慣の自立を支援することが中心です。学童保育指導員は、子どもたちの自主性や社会性を育むためのサポートがおもな役割です。
保育士は国家資格が必須ですが、学童保育指導員は無資格でも働けます。
ただし、保育士資格があれば、放課後児童支援員の資格取得要件を満たすため、転職の際に有利に働くことが多いでしょう。
参考資料:厚生労働省「保育士になるには?」
関連記事:保育士で心がけていることは?仕事で気を付けるべきこと
学童保育の指導員が続かない理由8つ
学童保育の仕事はやりがいがある一方で、離職率が高いという厳しい現実もあります。
転職してから「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、指導員が直面しがちな課題を事前に知っておくことが賢明です。
ここでは、学童保育の指導員が続かないといわれるおもな理由を8つ解説します。
- 給料が仕事内容に見合わない
- 職員との人間関係が難しい
- 保護者対応のストレスがある
- 子どもの体力についていけない
- 子どもの命を預かる責任の重さ
- 慢性的な人員不足による業務量の多さ
- 人手不足で休暇が取れない
- 勤務時間が不安定で生活リズムが崩れやすい
詳しく見ていきましょう。
給料が仕事内容に見合わない
学童保育指導員の給与水準は、その業務内容や責任の重さに比べて低いと感じる人が多いのが現状です。
厚生労働省の調査によると、平均年収は396万円程度で、日本の給与所得者全体の平均給与478万円を下回っています。
保育士の全国の平均年収は406.8万円であり、学童保育指導員の平均年収はそれを下回ります。
非正規職員の割合が高く、パートやアルバイトの場合、十分な収入を得ることが難しいケースも少なくありません。
昇給や賞与、退職金といった福利厚生が整っていない施設も多く、長期的なキャリアを築くうえでの経済的な不安が、離職の大きな原因となっています。
関連記事:保育士の給料はいつから上がる?処遇改善の最新情報と今後の見通しを解説
職員との人間関係が難しい
学童保育は、比較的少人数の職員で運営されることが多いため、人間関係が密になりやすい環境です。
職員同士の相性がよければチームワークを発揮できますが、一度関係がこじれると逃げ場がなく、精神的に大きなストレスを抱えることになります。
保育観や子どもへの接し方の違いから意見が対立したり、経験の長いベテラン指導員との間に世代間のギャップが生じたりすることも少なくありません。
狭い職場環境の中で、こうした人間関係の悩みを抱え続けることが、仕事へのモチベーション低下につながり、最終的に退職を決意する一因となります。
保護者対応のストレスがある
保護者との良好な関係構築は、学童保育の運営において不可欠ですが、同時にストレスの大きな要因にもなり得ます。
日々の送迎時のコミュニケーションから、子どもの怪我やトラブルに関する報告、時には指導方針に対するクレーム対応まで、その内容は多岐にわたります。
多くの保護者は協力的ですが、中には理不尽な要求をするケースもあり、精神的に疲弊してしまう指導員も少なくありません。
とくに人員不足で忙しい中、一人ひとりの保護者に丁寧に対応する時間を確保するのが難しく、すれ違いや誤解が生じやすい状況もあります。
こうした保護者対応の難しさが、仕事を続けるうえでの大きな負担となります。
子どもの体力についていけない
小学生、とくに低学年の子どもたちは多くのエネルギーがあり、活発に過ごしています。
指導員は、屋外で一緒に鬼ごっこやドッジボールをしたり、室内で活発に遊んだりする子どもたちに付き合うため、相当な体力が望まれます。
とくに夏休みなどの長期休暇中は、朝から夕方まで一日中子どもたちと過ごすため、その負担はさらに大きくなるでしょう。
保育園での乳幼児の世話とはまた違った種類の身体的なきつさがあり、体力に自信があった人でも、日々の疲れが蓄積していくことがあります。
年齢を重ねるにつれて、子どもたちのパワーについていくのが体力的に限界だと感じ、離職を考える人も少なくありません。
子どもの命を預かる責任の重さ
指導員は、子どもたちの楽しい放課後をサポートすると同時に、その安全と命を預かるという重い責任を負っています。
施設内での転倒や怪我、子ども同士のトラブル、食物アレルギーによる事故、不審者対応など、常にさまざまなリスクに備えなければなりません。
一瞬の気の緩みが重大な事故につながる可能性があるというプレッシャーは、精神的に大きな負担となります。
人員不足で多くの子どもを少数の職員で見なければならない状況では、そのプレッシャーは計り知れません。
この絶え間ない緊張感と責任の重さに耐えられなくなり、仕事を続けることが困難になるケースがあります。
慢性的な人員不足による業務量の多さ
共働き世帯の増加に伴い、学童保育の需要は年々高まっていますが、低い労働条件から指導員のなり手が不足しているのが現状です。
この慢性的な人員不足は、現場で働く指導員一人ひとりへの過剰な業務負担に直結します。
本来複数人で行うべき業務を1人でこなさなければならなかったり、休憩時間が十分に取れなかったりすることも珍しくありません。
また、1人の指導員が見る子どもの数が多くなりすぎると、安全管理が行き届かなくなり、保育の質も低下してしまいます。
終わらない業務と増え続ける責任に心身ともに疲弊し、燃え尽きてしまうことが離職の大きな原因です。
人手不足で休暇が取れない
慢性的な人手不足は、休暇の取得しにくさにもつながります。
学童保育は、子どもたちの生活を支える社会インフラであり、簡単に休めません。
しかし、職員の数がぎりぎりの状態で運営されている施設では、誰かが体調不良などで急に休むと、残りの職員でカバーしなければならず、現場は混乱します。
そのため、自分が休むとほかの同僚に迷惑がかかるというプレッシャーから、有給休暇を思うように取得できない指導員は少なくありません。
心身のリフレッシュに必要な休日が確保できず、疲労が蓄積していくことで、仕事を続ける意欲が削がれてしまいます。
勤務時間が不安定で生活リズムが崩れやすい
学童保育指導員の勤務時間は、学校がある平日と、土曜日や長期休暇で大きく異なります。
平日は午後からの勤務が多いですが、夏休みなどの長期休暇中は朝から夕方までの長時間勤務となり、シフト制が導入されることがほとんどです。
この繁閑の差が激しい勤務形態は、生活リズムを整えるのを難しくします。
年間を通して安定したスケジュールで働くことに慣れている人にとっては、この不規則さが身体的な負担となることがあります。
また、平日の勤務時間が短いことで十分な収入が得られない一方、長期休暇中は体力的に厳しいというジレンマも抱えがちです。
学童保育指導員は本当にすぐ辞める?本音をデータから知る
学童保育の離職率が高いことは事実ですが、一方で長く続けている人も存在します。
ここでは、指導員の本音を示す3つのデータを紹介します。
- 6割以上の人が仕事を辞めたいと思ったことがある
- 9割以上が仕事にやりがいを感じている
- 10年以上働く長期就労継続者も全体で25%にのぼる
厳しい側面だけでなく、仕事の魅力もデータから読み解くことで、よりバランスの取れた視点を持てます。
参考資料:「学童保育指導員の就労継続―就労継続者と離職者に対するインタビュー調査から―」
6割以上の人が仕事を辞めたいと思ったことがある
調査によると、勤続3年未満の学童保育指導員の6割以上が「仕事を辞めたいと思ったことがある」と回答。
この数字は、多くの指導員が仕事の厳しさに直面している現実を浮き彫りにしています。
給与の低さや人間関係のストレス、業務量の多さなどが、離職を考える大きな要因となっていることがうかがえます。
とくに理想と現実のギャップに悩み、心身ともに疲弊してしまうケースは少なくありません。
このデータは、学童保育への転職を考える際に、仕事の大変さを覚悟しておく必要があることを示唆しています。
しかし、辞めたいと感じながらも仕事を続けている人がいることも事実です。
9割以上が仕事にやりがいを感じている
一方で、勤続3年未満の指導員9割以上が仕事に対して「やりがいを感じている」と回答。
この結果は、学童保育が大きな魅力を持っていることを示しています。
子どもたちの成長を感じられることや、保護者から感謝されること、子どもたちとの信頼関係を築けることなどが、大きな喜びとなっているのでしょう。
多くの人が困難に直面しながら、9割以上の人がやりがいを感じているという事実は、この仕事が持つ本質的な価値を物語っています。
厳しい現実と大きなやりがいが共存しているのが、学童保育の仕事のリアルな姿です。
10年以上働く長期就労継続者も全体で25%にのぼる
離職率の高さが課題とされる一方で、10年以上同じ職場で働き続けている指導員が全体の25%にのぼるというデータもあります。
これは、学童保育の仕事が決して「すぐ辞める」だけの仕事ではないことを示しています。
適切な労働環境や支援体制が整った職場であれば、専門性を高めながら長期的にキャリアを築くことが可能です。
この仕事に強い使命感と愛情を持ち、困難を乗り越えながら働き続けるベテラン指導員が数多く存在することも事実です。
長く働き続ける人がいることは、この仕事が人生をかける価値のある、奥深いものであることの証しといえます。
大変だけど楽しい!学童保育指導員のやりがい
学童保育の仕事は、低賃金や人員不足など多くの課題を抱えていますが、それを乗り越えてでも続けたいと思わせる大きなやりがいがあります。
転職を考える際には、仕事の厳しい側面だけでなく、こうした側面にも目を向けることが肝心です。
ここでは、学童保育の仕事のやりがいについて4つ紹介します。
- 子どもの成長を間近で支えられる
- 保護者から直接感謝を伝えられる
- イベント企画など創造性を発揮できる
- 自分の特技や趣味が生かせる
これらのやりがいが、日々の困難を乗り越える原動力となっています。
子どもの成長を間近で支えられる
学童保育指導員の最大のやりがいは、子どもの成長を日々、間近で感じられることです。
昨日までできなかった逆上がりができるようになった瞬間や、友達と喧嘩しても自分から謝れるようになった姿など、子どもたちの成長の瞬間に立ち会えます。
とくに学童期は、心も体も大きく成長する時期です。
その多感な時期に、家庭や学校とは違う「第三の居場所」として寄り添い、子どもたちの小さな変化や努力を見守り、支えられることは大きな喜びです。
保護者から直接感謝を伝えられる
保護者との連携はときに大変なこともありますが、直接感謝の言葉を伝えられる機会が多いのも、この仕事の魅力です。
お迎えの際に「先生のおかげで学童に行くのが楽しいと言っています」といった言葉をかけてもらえると、日々の苦労が報われる気持ちになります。
保護者が安心して仕事に取り組めるよう、その子どもを支えるという社会貢献性の高さも実感できるでしょう。
子どもだけでなく、その家庭全体をサポートしているという自負が、仕事への誇りとモチベーションにつながります。
イベント企画など創造性を発揮できる
学童保育では、指導員が主体となってさまざまなイベントを企画します。
季節の行事や誕生日会、工作コンテストなど、子どもたちが楽しめるような活動を自分たちのアイデアで形にできるのは、大きなやりがいの1つです。
そして、イベント当日に子どもたちの輝くような笑顔や夢中になっている姿を見たときの達成感は格別です。
自分のアイデアや工夫が、子どもたちの思い出作りに貢献できることに、大きな喜びを感じられるでしょう。
自分の特技や趣味が生かせる
学童保育の仕事は、自分自身の特技や趣味を生かせる場面が多いです。
たとえば、絵を描くのが得意なら、子どもたちと一緒にお絵かきや工作を楽しめます。
スポーツが得意なら、ドッジボールやサッカーで子どもたちと汗を流せます。
自分の好きなことや得意なことを通じて、子どもたちに新しい楽しさを伝えられるのは、この仕事ならではの魅力です。
自分の個性を生かしながらいきいきと働ける環境は、仕事の満足度を高めてくれます。
学童保育の指導員に向いている人の特徴
学童保育の仕事は、子どもが好きであることは大前提ですが、それ以外にも求められる資質や能力があります。
自分自身の性格や得意なことが、この仕事で生かせるかどうかを見極めることは、転職を成功させるためには必須です。
ここでは、どのような人が学童保育の指導員に向いているのか、具体的な特徴を5つ紹介します。
- 子どもに愛情を持って接せる人
- 子どもと一緒に全力で遊べる体力がある人
- 感情的にならずに子どもを叱れる人
- 子どもの様子の変化によく気づける人
- 職員や保護者と円滑に連携できる人
それぞれ見ていきましょう。
子どもに愛情を持って接せる人
学童保育指導員の根幹をなす資質は、子ども一人ひとりに対して愛情を持てるかどうかです。
子どもたちは、自分が大切にされている、受け入れられていると感じることで、安心して過ごせます。
どのような子どもに対しても分け隔てなく、その子のありのままを受け入れ、健やかな成長を心から願える温かい気持ちが大事です。
子どもたちの言動の裏にある気持ちを汲み取り、寄り添う姿勢が、信頼関係を築く第一歩となります。
子どもと一緒に全力で遊べる体力がある人
小学生の有り余るエネルギーに付き合うためには、体力がなくてはなりません。
外でドッジボールや鬼ごっこをしたり、室内で体を動かすゲームをしたりと、子どもたちと一緒に全力で遊べる体力と気力が求められます。
とくに、1日保育となる長期休暇中は、朝から晩まで子どもたちと活動するため、相当なスタミナが必要です。
体力に自信があるだけでなく、子どもたちと体を動かすことを心から楽しめる人は、この仕事に向いているといえるでしょう。
感情的にならずに子どもを叱れる人
子どもたちを指導するうえで、「叱る」という行為は避けられません。
しかし、大切なのは感情的に「怒る」のではなく、子どもの成長を願って冷静に「叱る」ことです。
危険な行為や他者を傷つける言動に対して、毅然とした態度で注意する必要があります。
その際、自分の感情をコントロールし、なぜその行為がいけないのかを子どもが理解分かるように、落ち着いて説明できる能力が期待されます。
突発的なトラブルが起きてもパニックにならず、冷静に状況を判断し、適切に対応できる人は、子どもたちに安心感を与えられるでしょう。
子どもの様子の変化によく気づける人
優れた指導員は、子どもたちの小さな変化を見逃さない観察力を持っています。
「今日はいつもより元気がないな」といった日々の様子の変化に気づくことは、トラブルを未然に防ぎ、子どもの心のケアをするうえで重要です。
言葉には出さない子どもの悩みや不安を察知し、適切な声かけをすることで、子どもは「先生は自分のことを見てくれている」と安心します。
一人ひとりの個性や発達段階を理解し、その子に合ったかかわり方を見つけるためにも、鋭い観察力は不可欠なスキルです。
職員や保護者と円滑に連携できる人
学童保育の仕事は、1人で完結するものではありません。
ほかの指導員や保護者、学校の先生など、多くの人々と連携しながら子どもたちを支えていく必要があります。
そのため、高いコミュニケーション能力が望まれます。
指導員同士で子どもの情報を共有し、一貫した方針で指導にあたることや、保護者に子どもの様子を的確に伝え、信頼関係を築くことが肝心です。
相手の意見に耳を傾け、自分の考えを分かりやすく伝えられる人は、チームの一員として円滑に業務を進められます。
学童保育の指導員に向いていない人の特徴
自分の性格や働き方のスタイルが、学童保育の現場で求められるものと大きく異なると、自分自身もつらい思いをし、結果的に長続きしない可能性があります。
転職活動を始める前に、自分の特性を客観的に見つめ直し、ミスマッチを防ぐことが賢明です。
ここでは、学童保育の指導員には向いていない可能性のある人の特徴を5つ紹介します。
- 自分のペースで仕事を進めたい人
- 子ども視点で物事を考えられない人
- ストレスを溜め込みやすい人
- 体力に自信がないと感じる人
- 複数のことを同時にこなせない人
これらの特徴は、仕事の満足度や継続性に大きく影響します。
自分のペースで仕事を進めたい人
学童保育の現場は、常に子どもが中心です。
子どもたちの行動は予測不可能で、突然の喧嘩や怪我など、予期せぬトラブルが次々と発生します。
そのため、自分が立てた計画どおりに仕事を進めることは困難です。
自分のペースで黙々と作業を進めたい、計画どおりに進まないとストレスを感じるという人は、働きにくさを感じるかもしれません。
子どもたちの状況に合わせて、柔軟に優先順位を変えながら動くことが求められるため、自分の思いどおりに仕事を進めたい人には不向きな環境といえます。
子ども視点で物事を考えられない人
子どもたちと良好な関係を築くためには、大人の論理を押し付けるのではなく、子どもたちの視点に立って物事を考える姿勢が大事です。
子どもたちの言動には、本人なりの理由や気持ちが隠されています。
それを理解しようとせず、頭ごなしに否定したり、自分の価値観を一方的に押し付けてしまうと、子どもとの信頼関係を築くのが難しくなります。
子どもたちの世界観や発達段階を理解し、その気持ちに共感しようと努めることが大切です。
子どもを尊重する意識が低いと、子どもとの間に溝が生まれ、信頼関係を築くことは難しいでしょう。
ストレスを溜め込みやすい人
学童保育の仕事は、子どもとのかかわりや保護者対応、同僚との人間関係など、さまざまな場面でストレスを感じることがあります。
子どもがいうことを聞いてくれなかったり、保護者から厳しい意見を受けたりすることもあるでしょう。
そうした出来事を一つひとつ重く受け止め、気持ちの切り替えがうまくできない人は、精神的に追い込まれてしまう可能性があります。
仕事で起きた嫌なことを引きずらず、「こんな日もある」と前向きに捉えることが、この仕事を長く続けるためには必須です。
体力に自信がないと感じる人
前述のとおり、学童保育の仕事は想像以上に体力を消耗します。
子どもたちと一緒に走り回ったり、重い荷物を運んだりすることもあります。
とくに、夏休みなどの長期休暇中は、一日中立ちっぱなしで動き回ることも珍しくありません。
体力に自信がない、疲れやすいと感じる人は、日々の業務をこなすだけで精一杯になってしまう可能性があります。
身体的な疲労は、精神的な余裕も奪ってしまいます。
子どもたちと安全に、そして楽しく過ごすためには、ある程度の体力は必須条件といえるでしょう。
複数のことを同時にこなせない人
学童保育の現場では、常に複数のタスクを同時に処理する能力が要求されます。
たとえば、子どもたちの遊びを見守りながら、宿題をしている子の質問に答え、お迎えに来た保護者に対応するといった状況は日常茶飯事です。
同時に複数のことを考えるとパニックになってしまう人は、マルチタスクをこなさなければならない学童保育の仕事に、大きな負担を感じるかもしれません。
広い視野を持ち、状況に応じて素早く頭を切り替えながら行動できる器用さが必要です。
子どもの叱り方とかかわる際のコツ
学童保育で子どもたちとかかわるうえで、避けては通れないのが「叱る」場面です。
しかし、叱り方を間違えると、子どもとの信頼関係を損なったり、子どもの心を傷つけたりする可能性があります。
指導員の役割は、ただ間違いを指摘することではなく、子どもが自ら考えて行動を改められるように導くことです。
ここでは、子どもたちの健やかな成長を促すための、叱り方とかかわり方のコツを5つ紹介します。
- 感情的に怒らず冷静に伝える
- 叱る理由を具体的に説明する
- 人格を否定せず行動を注意する
- 叱ったあとには必ずフォローする
- 意地悪な態度を取る子への対処法を学ぶ
これらのコツを実践することで、子どもとのよりよい関係を築けます。
感情的に怒らず冷静に伝える
子どもを叱る際にもっとも大切なのは、指導員自身が感情的にならないことです。
大声で怒鳴ったりイライラした態度を見せたりすると、子どもは恐怖心から話を聞けなくなり、なぜ叱られているのかを理解できません。
叱るべき行動があったときは、まず一呼吸おいて自分の気持ちを落ち着かせましょう。
そして、子どもの目を見て、冷静かつ毅然とした口調で「その行動はいけないことだ」と伝えます。
感情をぶつける「怒り」ではなく、子どもの成長を願う「叱り」であることを意識することが肝心です。
叱る理由を具体的に説明する
なぜ叱られているのか、その理由を子どもが理解できなければ、同じ過ちを繰り返してしまいます。
「ダメだからダメ」ではなく、「なぜその行動がいけないのか」を具体的に説明しましょう。
たとえば、「お友達を叩くと、お友達が痛い思いをして悲しむから、叩くのはやめようね」というように、相手の気持ちや行動の結果を分かりやすい言葉で伝えます。
理由を丁寧に説明することで、子どもは善悪の判断基準を学び、自分の行動を客観的に振り返る力が育ちます。
人格を否定せず行動を注意する
叱る対象は、あくまで子どもの「行動」そのものであり、その子の人格や存在自体を否定してはいけません。
「本当にダメな子だね」といった言葉は、子どもの自尊心を深く傷つけ、自己肯定感を低下させてしまいます。
注意すべきは、「おもちゃを片付けない」という行動であり、「おもちゃを片付けないあなた」ではありません。
「〇〇という行動はよくないよ」と、問題となる行動に焦点を当てて伝えることで、子どもは人格を否定されたと感じることなく反省しやすくなります。
叱ったあとには必ずフォローする
叱りっぱなしで終わらせてしまうと、子どもとの間に気まずい空気が残り、関係がこじれてしまうことがあります。
叱ったあとは、必ずフォローを入れることを忘れないでください。
子どもが自分の行動を反省して謝れたら「ちゃんと謝れて偉いね」と褒めてあげましょう。
そして、「先生はあなたのことが大切だから、いけないことをしたときはちゃんと叱るからね」と伝え、愛情は変わらないことを示します。
叱ることは、信頼関係を深める機会にもなり得ます。
意地悪な態度を取る子への対処法を学ぶ
学童保育では、ときにほかの子に意地悪をしてしまう子もいます。
そうした子への対応には、とくに配慮が必要です。
まず、意地悪な行動の裏には寂しさや不安、注目されたいという気持ちが隠れていることが多いことを理解しましょう。
一方的に責めるのではなく、「どうしてそんなことをしたの?」とその子の気持ちに寄り添い、話を聞く姿勢が大切です。
そのうえで、意地悪をされた子の気持ちを代弁し、相手がどう感じるかを考えさせます。
学童保育指導員での人間関係のストレス対処法
学童保育の仕事を続けるうえで、人間関係のストレスは大きな課題です。
同僚やベテラン指導員、保護者など、さまざまな立場の人とかかわる中で、意見の対立や誤解が生じることは避けられません。
ここでは、学童保育の現場で直面しがちな人間関係のストレスに対して、具体的な対処法を4つ紹介します。
- 同僚との意見の違いを建設的に話し合う
- ベテラン指導員との世代間ギャップを理解する
- 保護者からのクレームを個人的に受け止めすぎない
- 職場外でストレスを発散する方法を持つ
これらの対処法は、よりよい職場環境を築くためにも役立ちます。
同僚との意見の違いを建設的に話し合う
同僚との保育観の違いは、ストレスの原因になりがちです。
しかし、それを対立と捉えるのではなく、よりよい保育を生み出すための機会と考えることが賢明です。
相手の意見を感情的に否定するのではなく、まずは「なぜそう考えるのか」という背景に耳を傾け、尊重する姿勢を示しましょう。
そのうえで、「私はこう思うのですが、いかがでしょうか」と、自分の意見を提案として伝えます。
目的は相手を論破することではなく、子どもたちにとって最善の環境を作ることです。
ベテラン指導員との世代間ギャップを理解する
経験豊富なベテラン指導員は頼りになる存在ですが、時にはそのやり方や価値観が古いと感じ、ギャップに悩むこともあるでしょう。
しかし、長年の経験に裏打ちされた知識や知恵には、学ぶべき点が多くあります。
頭ごなしに否定するのではなく、「昔はこうだったんですね。勉強になります」と敬意を払い、まずはそのやり方を学んでみましょう。
そのうえで現代の子どもたちに合った方法を「こんなやり方はどう思われますか?」と相談する形で提案すると、相手も受け入れやすくなります。
保護者からのクレームを個人的に受け止めすぎない
保護者からのクレームは、精神的に大きなダメージを受けやすいものです。
しかし、クレームを受けた際に、それを自分個人への攻撃だと捉えないことが賢明です。
保護者は、大切な我が子を思うがゆえに、不安や不満を口にしている場合がほとんどといえます。
まずは冷静に保護者の話を聞き、その気持ちに共感する姿勢を示しましょう。
そして、1人で抱え込まずに、必ずほかの職員や上司に報告し、組織として対応することが肝心です。
職場外でストレスを発散する方法を持つ
仕事で溜まったストレスは、職場外で上手に発散することが心身の健康を維持するためには欠かせません。
仕事のことは一旦忘れ、自分の好きなことに没頭する時間を意識的に作りましょう。
友人と食事に行ったり、趣味のスポーツや創作活動に打ち込んだり、ゆっくりと温泉に浸かったりするのもおすすめです。
自分に合ったリフレッシュ方法をいくつか持っておくと、ストレスを溜め込まずにすみます。
オンとオフを切り替えることが、仕事を長く続けるための秘訣です。
学童保育指導員を辞めたいと感じたときどうする?
どれだけやりがいのある仕事でも、困難に直面し「もう辞めたい」と感じる瞬間は誰にでも訪れます。
感情的に決断してしまう前に、一度立ち止まって冷静に状況を分析し、自分にとって最善の選択肢を考える時間を持つことが賢い選択です。
ここでは、仕事が続かない、辞めたいと感じたときに試してみたい5つの対処法を解説します。
- まず1週間だけ様子を見てみる
- 信頼できる同僚や上司に相談する
- 有給休暇を取って気持ちをリセットする
- 心身の不調が出たら無理せず休職を検討する
- 転職活動を始めながら働き続ける選択もある
これらの選択肢を検討することで、後悔のない決断につながります。
まず1週間だけ様子を見てみる
「辞めたい」気持ちが一時的な感情の高ぶりによるものか、それとも根本的な問題から来ているのかを見極めるために、短期間様子を見る方法があります。
「とりあえず今週いっぱいだけ頑張ってみよう」と目標を短く設定することで、精神的な負担を少し軽減できます。
その期間でなぜ辞めたいのか、何が1番つらいのかを客観的に考えてみましょう。
一時的な疲れが原因であれば、少し休むことで乗り越えられるかもしれません。
信頼できる同僚や上司に相談する
1人で悩みを抱え込んでいると視野が狭くなり、ネガティブな思考に陥りがちです。
職場に信頼できる同僚や上司がいる場合は、勇気を出して相談してみましょう。
同じ職場で働く仲間であれば、あなたの状況を理解し、共感してくれるはずです。
話を聞いてもらうだけでも気持ちが楽になりますし、自分では思いつかなかったアドバイスや解決策をもらえることもあります。
悩みを共有することで、精神的な孤立感から抜け出せます。
有給休暇を取って気持ちをリセットする
心身ともに疲れ切っているときは、正常な判断が難しくなります。
一度仕事から物理的に距離を置き、心と体を休ませる時間を作りましょう。
有給休暇を取得して旅行に出かけたり、趣味に没頭したりと、自分をリフレッシュさせるための時間を過ごすことが大切です。
仕事のことを考えない時間を持つことで、凝り固まった思考がほぐれ、自分の気持ちを客観的に見つめ直せます。
リフレッシュして心に余裕が生まれれば、「もう少し頑張ってみよう」という前向きな気持ちが湧いてくるかもしれません。
今後のキャリアについて冷静に考えるきっかけにもなります。
心身の不調が出たら無理せず休職を検討する
ストレスが原因で眠れない、食欲がない、朝起きられないといった心身の不調が現れている場合は、無理を続けるべきではありません。
それは、あなたの心が発している危険信号です。
まずは医療機関を受診し、専門家の診断を仰ぎましょう。
医師から休養が必要だと判断された場合は、休職制度を利用することも選択肢の1つです。
まずは心と体を回復させることを最優先に考えてください。
休職期間中に、今後の働き方についてじっくりと考える時間を持てます。
転職活動を始めながら働き続ける選択もある
現在の職場に改善の見込みがなく、辞めたいという気持ちが固まっている場合は、転職活動を始めるのも1つの手です。
しかし、すぐに退職してしまうと経済的な不安から焦って次の職場を決めてしまい、再びミスマッチを起こす可能性があります。
可能であれば、現在の仕事を続けながら、情報収集や応募といった転職活動を進めるのが賢明です。
ほかの学童保育の求人情報を見ることで、現在の職場の労働条件を客観的に比較できますし、自分の市場価値も分かります。
次の選択肢があるという安心感が、現在の仕事に対する精神的な余裕にもつながります。
学童保育指導員から転職する場合の選択肢と準備
学童保育指導員を辞める決意をした場合、次のキャリアをどのように築いていくかを具体的に考える必要があります。
ここでは、転職する場合の選択肢と、そのために必要な準備について4つ解説します。
- 円満退職のための引き継ぎ準備をする
- よりよい条件の学童保育施設を探す
- 保育士や児童発達支援などほかの職種を検討する
- 保育分野に特化した転職エージェントを活用する
それぞれ見ていきましょう。
円満退職のための引き継ぎ準備をする
退職を決めたら、まずは職場に迷惑をかけないよう、円満に退職するための準備を進めましょう。
法律上は退職の2週間前までに申し出ればよいとされていますが、就業規則を確認し、できるだけ早めに直属の上司に退職の意向を伝えます。
後任の担当者が困らないように、担当していた業務内容や子どもたちの情報、保護者対応の注意点などをまとめた引き継ぎ資料を作成しましょう。
最後まで責任を持って業務を全うする姿勢を見せることで、良好な関係を保ったまま退職できます。
お世話になった職場への感謝の気持ちを忘れず、丁寧な引き継ぎを心がけてください。
よりよい条件の学童保育施設を探す
現在の職場で感じていた不満を解消できる、よりよい条件の学童保育施設に転職するのも1つの選択肢です。
給与や福利厚生、職員の配置人数と施設の設備、運営方針など自分が何を重視するのかを明確にし、求人情報を比較検討しましょう。
転職活動では、施設見学をさせてもらい、実際の職場の雰囲気や職員の様子、子どもたちの表情などを自分の目で確かめると安心です。
面接では条件面だけでなく、研修制度やキャリアアップの支援体制についても質問し、職員を尊重する施設かどうかを見極めましょう。
保育士や児童発達支援などほかの職種を検討する
学童保育での経験を生かして、子どもとかかわる別の職種に転職することも可能です。
たとえば、保育士資格を持っていれば保育園で働けますし、放課後等デイサービスで発達に特性のある子どもたちを支援する仕事も選択肢の1つです。
これらの職場では、学童保育で培った小学生とのコミュニケーション能力や、多様な子どもたちに対応してきた経験が大きな強みとなります。
自分の興味や関心、スキルに合わせてより専門性を高められる分野に進むことで、新たなキャリアの可能性が広がります。
保育分野に特化した転職エージェントを活用する
働きながら効率的に転職活動を進めたい場合は、保育分野に特化した転職エージェントを活用するのがおすすめです。
専門のキャリアアドバイザーが、あなたの希望や経験に合った求人を紹介してくれます。
履歴書の添削や面接対策、給与交渉の代行など、転職活動全体をサポートしてくれるでしょう。
何より、業界の動向に詳しいプロに相談できることは、大きな安心材料です。
1人で悩まず専門家の力を借りることで、よりスムーズで満足度の高い転職を実現できます。
まとめ:学童保育指導員が続かない理由を理解して自分に合う職場を見つけよう
学童保育指導員が続かない理由は、給料の低さや人間関係、体力的な負担など複数の要因が絡み合っています。
一方で、子どもの成長を見守るやりがいも確かに存在し、長く続けている人もいます。
大切なのは、自分に合った働き方を見つけることです。
もし、あなたが次のキャリアに悩んでいるなら、保育士・幼稚園教諭のための転職求人サイト「保育のせかい」がお手伝いします。
保育のせかいは、保育園の経営者や現役保育士が監修しており、業界のリアルな情報にもとづいた求人のみが掲載しています。
保育士資格を持つアドバイザーも多数在籍しているため、専門的な視点からあなたに合った職場探しをサポート。
学童保育や児童指導員の求人も豊富に扱っていますので、お気軽にご相談ください。
この記事の監修者

森 大輔(Mori Daisuke)
保育のせかい 代表
《資格》
保育士、幼稚園教諭、訪問介護員
《経歴》
2017年 保育のせかい 創業。2021年 幼保連携型認定こども園を開園するとともに、運営法人として、社会福祉法人の理事長に就任。その他 学校法人の理事・株式会社の取締役を兼任中。
「役に立った!」と思ったらいいね!してね(^-^)
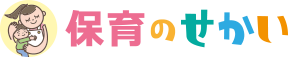

 2025.10.20
2025.10.20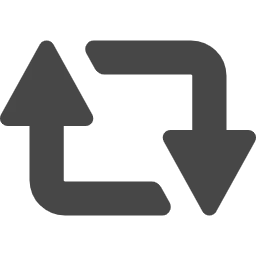 2026.01.05
2026.01.05