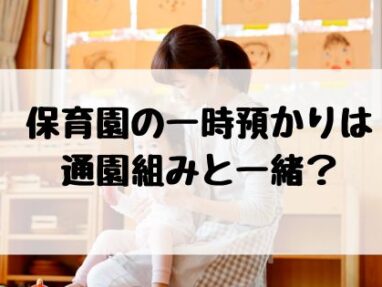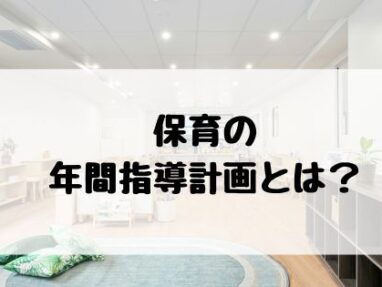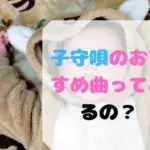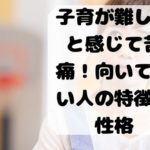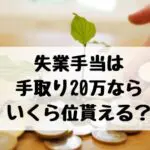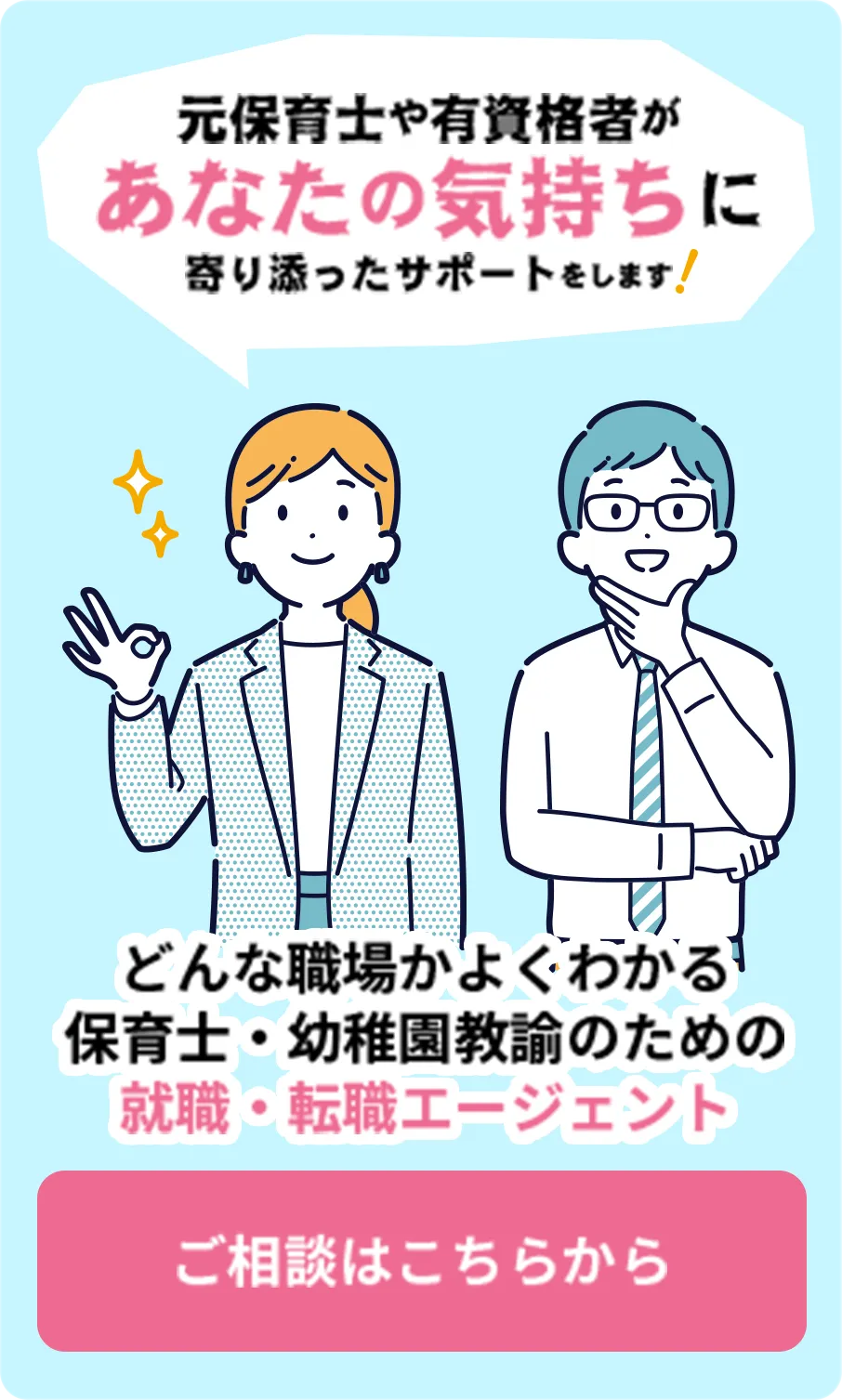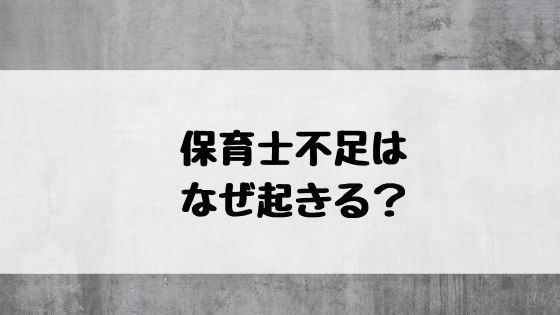
待機児童問題や少子高齢化問題を改善するためにも、保育士の役割は重要になってきます。
保育園や保育施設によっては、保育士の数が足りなくて待機児童問題や、少子高齢化問題の影響を受けているところもあるからです。
保育士の数が足りない職場もたくさんあるので、保育士1人あたりの負担が増えて人間関係や労働環境が悪化するところも少なくありません。
そもそも、保育士不足はなぜ起きているのか気になる人もいるのではないでしょうか。
今回は、保育士不足はなぜ起きるのかや、いつまで続くのかについてとZ世代との関係性や、問題点と解決策などについてお伝えしていきます。
Contents
保育士不足はなぜ起きる?
社会的な視点で見ると保育士不足が引き起こされる要因として、待機児童問題や少子高齢化問題が関係しています。
社会的な問題は個々で解決に向けて取り組んでも、大きな課題となるのでたくさんの時間を必要とし、今すぐ改善するのは難しいです。
保育業界からの視点で見ると保育士不足は、潜在保育士や早期退職者の多さが関係していると言えるでしょう。
保育士の早期退職者や潜在保育士の問題については、保育業界全体の労働環境や待遇面が改善されてもっと魅力的に思われるようになると、解決に向かう可能性があります。
保育士不足は社会的な課題である待機児童問題や少子高齢化問題、個人では保育士の早期退職者や潜在保育士の問題などが、影響を及ぼしているから起きていると言えます。
保育士不足はいつまで続く?
日本の現状として少子高齢化社会に突入しているので、今後は子どもの数がどんどん減ってくると考えられています。
子どもの数が減少してくると保育園や、保育施設に預けられる子どもも少なくなるから、保育士の負担は減るのではと思う人もいるのではないでしょうか。
確かに保育園や保育施設に預けられる子どもの数が、少なくなると予想されているので保育士1人あたりの負担は減る可能性があります。
子どもの数が減少しても、保育士不足の解消に結びつくとは言えません。
なぜなら、子どもを預けるママやパパがどちらも働くケースが増えているからです。
共働き世帯が増えて家庭で日中は子どもの面倒を見られない保護者が増えている影響で、少子高齢化社会になっても保育士に頼る保護者の数はあまり減少しないことが予想されます。
いつまで保育士不足が続くのかは断定はできませんが、上記のような理由があるため、今後もしばらく解消されないでしょう。
保育士不足の保育園は多い?
保育業界全体で保育士不足が叫ばれているため、保育士の数が足りない職場は多いです。
国や自治体が様々な支援を行ったり、保育園や保育施設も職場環境や待遇面の改善を行ったりしていますが、今すぐに人材不足の問題が解決するのは厳しいでしょう。
潜在保育士の多さや少子高齢化社会が、保育士不足に大きな影響を及ぼしていると言えますが、保育士になるためには国家資格が必要です。
保育士資格という国家資格の合格率は、20%台ですから難関資格と言えます。
国家資格の試験は1年間に2回しか実施されていないので、受験回数を増やしたり試験の難易度を優しくしたりなど、見直しも保育士不足を解消するために重要でしょう。
保育士になりたいけれど、国家資格に何度も落ちて合格する自信を失ってしまう人も少なくありません。
簡単に保育士になれると、保育の質が低下を招いてしまう恐れがあるので、国家資格の取得を簡単にし過ぎるのも良くありません。
バランスがとても難しいところですが、保育士の国家資格の見直しをすることで、少しは保育士不足の改善に役立つはずです。
保育士不足と潜在保育士の関係性
保育士不足に陥っていることに関して、潜在保育士が関係していると言えます。
潜在保育士とは保育士資格を持ちながら現在は、保育士として働いていない人です。
保育士資格を持ちながらも保育現場で一度も働いたことのない方や、長年働いていた上で離職して、そのまま復職しない方が含まれます。
潜在保育士は保育士不足の解消に大きな鍵を握っています。
多くの潜在保育士が保育士として再び働かない理由として、責任の重さ、給与の低さ、労働環境の厳しさなどネガティブな要因を持つ職場もたくさんあるからです。
潜在保育士の再就職を促進したり、上記の問題を解決したりできると保育士不足の解消に繋がるはずです。
Z世代向けた保育士不足への取り組み
保育士不足を解消するためには、日本の将来を担う若者の力が必要になってくるでしょう。
特に、Z世代向けた保育士不足への取り組みに力を入れることは重要です。
Z世代は1995年~2010年生まれの若者を指し、テクノロジーに対する理解が深い世代です。
Z世代向けた保育士不足への取り組みとして、デジタル化を有効活用することで若者の保育士確保に繋がる可能性があります。
例えば、SNSを活用した情報発信やオンラインでの研修プログラムです。
デジタル化を上手く活用できると、若い世代が保育士という職業に興味を持ちやすくなり、新しい働き方や教育方法に対する理解も深まります。
保育士不足が進むのは若者から人気がない職業だから?
多くの保育園や保育施設で保育士不足が進んでいますが、若者から人気が全くない職業ではありません。
若い世代の多くが保育士という職業は認知しています。
自分が小さい頃に実際に保育園に通っていたり、成長する過程で保育士の職業を理解したりして認知しているからです。
世間的には保育士のイメージは、大変そうだと思われがちですが毎年、若者が学校を卒業して新卒で保育現場で働いているのも事実です。
保育士という職業自体は、まだまだ根強い人気があります。
労働環境や待遇面が充実していない職場がたくさんあるため、保育士の不平不満が溜まり我慢の限界がきて退職する人が続出して、離職率が高くなり保育士不足に繋がっています。
根本的に保育士不足を改善するなら、若者の新卒者の採用を増やすだけでは厳しいかもしれません。
もっと、潜在保育士が再就職しやすい環境を整えたり、未経験者やブランクがある人が就職や転職しやすい状況を作ったりすることが大切でしょう。
保育士不足が進むがZ世代では保育士人気は低くない
保育業界の救世主となるのは、やはりモチベーションが高い若い人材でしょう。
特に、すぐに戦力となってくれる可能性がある、Z世代に向けたアピールの仕方は重要です。
Z世代でも決して保育士人気は低くないからです。
保育士不足に悩んでいる保育園や保育施設のなかには、定期的に求人募集をしているところも少なくありません。
ただし、Z世代を含めた若者に保育士の魅力を、効果的にアピールできていないケースが多いため職業の人気は高くても、なかなか人材確保に繋がっていません。
デジタル社会になっていますので、インターネットを上手く活用して若者にアプローチしていくことが大切です。
保育士不足の職場では、人材がなかなか集まらないのはもしかしたら、ハローワークやフリーペーパーだけで求人情報を掲載しているからという可能性もあります。
SNSやWebサイトなどを上手く活用していないから、若者に情報が届いていないだけかもしれません。
保育士不足に逆行する保育園もある
保育士不足が深刻化する一方で、一部の保育園では逆に人材を確保し、保育士不足を解消しているところもあります。
また、人材不足を解消するだけではなく、下記のように職場環境が改善されて離職率の低下に繋がっているところもあります。
・給与の見直しをする
・労働環境を改善する
・人間関係を改善する
・保育士同士の絆を深める
・地域住民や地方自治体と協力する
・ICTを導入する
保育士が働きやすい環境を整えることで、保育士を確保したり新たな人材の流入を促進したりしているのです。
保育士不足の問題点
保育士不足の問題点をお伝えしていきます。
仕事量の増加
保育士の仕事量は年々増加しており、ストレスを増加させ離職率の上昇に繋がる可能性があります。
例えば、子どもの人数が増えたにもかかわらず、保育士の人数がそのペースに追いつかずに1人あたりが担当する子どもの数が増えてしまったりです。
仕事が忙しくなると、1人ひとりの子どもにかける時間が減少し、質の高い生活サポートを行うことが困難になります。
人間関係の悪化
職場の人間関係が悪化すると、保育士が仕事を続けるモチベーションを失う可能性があります。
例えば、上司や同僚とのコミュニケーションがうまくいかない場合などが考えられます。
チームワークが求められる保育現場で、コミュニケーションの問題が生じると、ストレスの原因となり結果的には退職者が増えて保育士不足に繋がってしまうのです。
低賃金になってしまう
保育士の仕事は専門的な知識と技術を必要とする一方で、賃金が他の業種に比べて低い傾向にあります。
賃金が低いと生活が厳しくなったり、あまり職業への魅力が感じられなくなったりして、他の職種への転職を考える保育士も少なくありません。
低賃金になってしまうと保育士を目指す人々を減らし、結果的に保育士不足を引き起こします。
保育の質を担保できなくなる
保育士が不足すると子ども一人ひとりに対する、生活サポートが十分に行えなくなります。
働く職員に大きな負担がかかってしまうからです。
子ども達に深く寄り添えなくなったり、保育士の注意が散漫になったりして、安全や教育の質が低下してしまいます。
保育士不足は、保育の質を担保できなくなる恐れがあります。
保育士不足の解決策
保育士不足の解決策をお伝えしていきます。
労働環境を良くする
保育士の労働環境を良くすることで、離職率が下がり保育士不足の改善に繋がる可能性があります。
労働環境を改善するためには、例えば、下記のようなことが挙げられます。
・休憩時間の確保
・人間関係の改善
・職場の環境整備
・人員の適正配置
保育士不足に悩む保育園や保育施設のなかには、すでに労働環境は改善しているというところもあるでしょう。
しかし、上記でお伝えした内容を全て実践できていることが望ましいです。
労働環境を改善しているけれど、相変わらず保育士が定着しない職場は、労働環境の改善に向けての取り組みは、考えられること全て実践できているのかを改めて見直すことが重要です。
ICTの導入などデジタル化に取り組む
ICTの導入などデジタル化に取り組むことで、保育士がより効率的に仕事を行えるようになります。
例えば、保育記録をデジタル化して、紙の記録にかかる時間を削減するなどです。
保育士は記録作業に費やす時間を減らせると、子ども達と一緒に過ごす時間を増やしたり、業務負担が軽減したりなどに繋がります。
デジタル技術の導入により、保育の質が向上する可能性があります。
国や自治体の対策
保育士不足は、日本全体で深刻な社会問題となっています。
子育て支援の重要性が増す中で、資格を持ちながらも保育士として就業する人が少ない現状があるため、国や自治体ではさまざまな対策を行っています。
例えば、働き方改革や処遇改善等加算などです。
今後も、国や自治体が積極的に保育士不足の解決策を打ち出して、支援を行うことも重要です。
待遇を改善させる
保育士の待遇改善も保育士不足の解消に繋がります。
例えば、賃金の見直しや福利厚生の充実、キャリアアップの機会提供などが考えられます。
保育業界全体で保育士の待遇がもっと改善できれば、職業としての魅力も高められるはずです。
まとめ
保育士不足に悩んでいる保育園や、保育施設はたくさんあります。
潜在保育士や離職者の多さが、保育士不足を引き起こしている大きな要因と言えますが、若い人材の確保が進んでいないというのも関係しています。
保育士の職業に関して、若者人気は決して低くはないので、デジタル化を上手く活用したアプローチが鍵になるでしょう。
まだまだ、デジタル化に対応できていない保育園や保育施設も少なくありません。
デジタル化に取り組みインターネットを有効活用すると、多くの若者に職場の魅力や保育士という職業そのものの素晴らしさをアプローチしやすくなります。
保育士不足の解消はすぐには難しいと言えますが、将来的には改善に向けて様々な取り組みが行われていくでしょう。
この記事の監修は

保育のせかい 代表 森 大輔
2017年 保育のせかい 創業。保育士資格・訪問介護員資格を保有。2021年 幼保連携型認定こども園を開園するとともに、運営法人として、社会福祉法人の理事長に就任。
その他 学校法人の理事・株式会社の取締役を兼任中。
この記事の監修者

森 大輔(Mori Daisuke)
保育のせかい 代表
《資格》
保育士、幼稚園教諭、訪問介護員
《経歴》
2017年 保育のせかい 創業。2021年 幼保連携型認定こども園を開園するとともに、運営法人として、社会福祉法人の理事長に就任。その他 学校法人の理事・株式会社の取締役を兼任中。
「役に立った!」と思ったらいいね!してね(^-^)
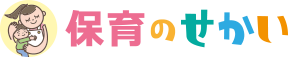

 2024.06.27
2024.06.27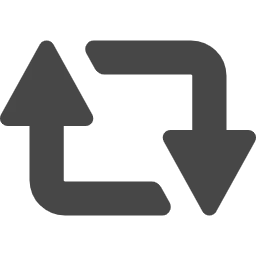 2024.07.26
2024.07.26